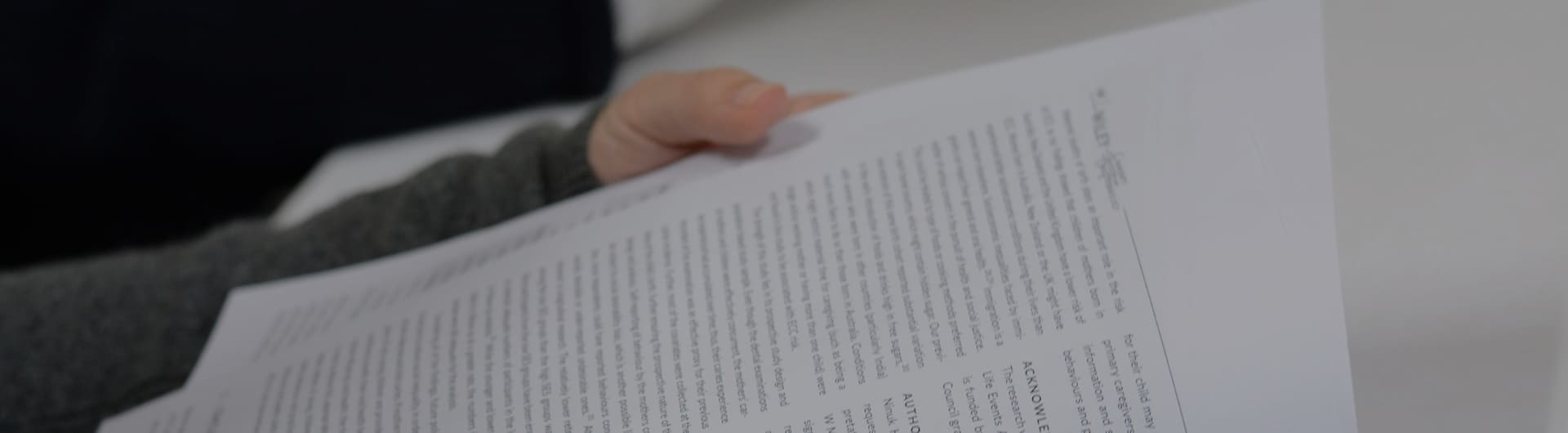
研究業績Publication
2020
-
Isumi A, Doi S, Yamaoka Y, Takahashi K, Fujiwara T*. Do suicide rates in children and adolescents change during school closure in Japan? The acute effect of the first wave of COVID-19 pandemic on child and adolescent mental health. Child Abuse Negl. 2020 Dec;110(Pt 2):104680.
日本語アブストラクト
「休校中に子どもの自殺がどう変化するか:新型コロナウイルス感染症流行の第一波が子どものメンタルヘルスに与える短期的影響」
【背景】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は子どもたちの生活に甚大な影響を及ぼしている。第一波の間に起こった重要な変化のひとつである休校によって、子どもたちは友達や先生など人との接触が減り、家族と過ごす時間が増えた。これは、メンタルヘルスの客観的指標である自殺に良い影響も悪い影響も与えうる。しかし、COVID-19の流行が子どもの自殺にどのような影響を与えているかはまだわかっていない。
【目的】
本研究では、日本で学校が休校になっている期間に注目し、COVID-19流行の第一波が子どもの自殺に与える短期的影響を検討した。
【方法】
データは2018年1月から2020年5月における、20歳未満の子どもの月間自殺数を用いた。ポワソン回帰分析を用いて、休校期間中(2020年3〜5月)と2018年、2019年の同時期の自殺数を比較した。2018年1月から2020年5月の全てのデータを用いたポワソン回帰分析、さらには、過分散をモデル化できる負の2項回帰分析も行い、頑健性を確認した。
【結果】
休校期間中の自殺率は、休校期間外の自殺率と有意な違いが見られなかった(罹患率比 1.15、95%信頼区間 0.81ー1.64)。月の主効果は有意に見られた、つまり、3月に比べて5月は1.34倍(95%信頼区間 1.01ー1.78)自殺が増加していることがわかった。しかし、月と休校の交互作用は統計的に有意でなかった(p>0.1)。
【結論】
本研究は暫定的な結果として、COVID-19流行の第一波が子どもの自殺に与える短期的影響は休校期間中に見られなかったことを明らかにした。
-
Matsuyama Y, Isumi A, Doi S, Fujiwara T*. Poor parenting behaviours and dental caries experience in 6- To 7-year-old children. Community Dent Oral Epidemiol. 2020 Dec;48(6):493-500.
日本語アブストラクト
「養育行動と小学1年生のう蝕の関連の横断研究」
【目的】不適切な養育行動と子どものう蝕の関連が示唆されているが、いまだ明らかでない。本研究は保護者の養育行動と小学1年生のう蝕および口腔の健康行動の関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】2015年と2017年に東京都足立区で実施された「子どもの健康・生活実態調査」の横断調査に参加した小学1年生計6,703名を対象とした。保護者への質問紙調査で養育行動および子どもの口腔の健康行動(1日2回未満の歯磨き、好きな時間の間食、毎日ジュースを飲むこと)を測定した。学校歯科検診データからう蝕の情報を得、質問紙調査データと突合した。因子分析の結果、不適切な養育行動として、親子の関わりが少ないこと、虐待傾向であること、子の健康行動に注意を払わないこと、の3因子が抽出された。これらの因子得点とう蝕経験歯数および口腔の健康行動との関連をポワソン回帰分析で検証した。
【結果】親子の関わりが少ないことおよび子の健康行動に注意を払わないことは、子どものう蝕が多いことと有意に関連した。因子得点が1標準偏差増加するごとに、う蝕の平均本数がそれぞれ1.05倍(95%信頼区間: 1.03, 1.07)、1.18倍(95%信頼区間: 1.16, 1.21)増加した。これらは口腔の健康行動とも関連した。虐待傾向はう蝕との関連はみられなかったが(平均本数の比: 0.99; 95%信頼区間: 0.96, 1.01)、子どもの口腔の健康行動に有意に関連し、因子得点が1標準偏差増加するごとに1日2回未満の歯磨き、好きな時間の間食、毎日ジュースを飲むことがそれぞれ1.11倍(95%信頼区間: 1.06, 1.16)、1.11倍(95%信頼区間: 1.06, 1.16)、1.06倍(95%信頼区間: 1.00, 1.11)多く見られた。
【結論】親子の関わりが少ないことおよび子の健康行動に注意を払わないことはう蝕が多いことに有意に関連した。虐待傾向も含め、今回抽出された3つの不適切な養育行動のすべてが子の口腔の健康行動が悪いことに関連した。
-
Morishita S, Yoshii T*, Okawa A, Inose H, Hirai T, Ogawa T, Fushimi K, Fujiwara T. Comparison of Perioperative Complications Between Anterior Fusion and Posterior Fusion for Osteoporotic Vertebral Fractures in Elderly Patients: Propensity Score-Matching Analysis Using Nationwide Inpatient Database. Clin Spine Surg. 2020 Dec;33(10):E586-E592.
-
Matsuyama Y, Fujiwara T*, Sawada Y, Yagi J, Mashiko H, Kawachi I, Great East Japan Earthquake Follow-up for Children Study Team. Delay discounting in children exposed to disaster. PLoS ONE. 2020 Des 30;15(12):e0243994.
日本語アブストラクト
「東日本大震災を経験した子どもにおける遅延割引」
遅延割引は、子どもの将来の健康や学業成就の重要な予測因子であるが、災害後などの不確実性の高い環境において変化する可能性がある。本研究では、2011年の東日本大震災で住宅を失った経験が、愛する人を失ったなどの他の心理的外傷ではなく、子どもの遅延割引と関連があることが分かった。2014年、震災時に就学前だった子ども(N = 167、平均年齢 = 8.3歳)を対象に、「今」(トークン1個につきキャンディ1個を当日)と「1ヶ月後」(トークン1個につきキャンディ2個を1ヶ月後)の報酬を設定し、5つのトークンを割り振る時間投資演習で遅延割引を評価した(被災時の平均年齢 = 4.8歳)。住宅が倒壊または浸水した子どもは、住宅に被害がなかった子どもに比べて、「今」に割り当てるトークンの数が0.535個(95%信頼区間:-0.012、1.081)多かった。他の種類のトラウマ体験は、遅延割引と関連しなかった。 -
Tani Y, Fujiwara T*, Isumi A, Doi S. Home Cooking Is Related to Potential Reduction in Cardiovascular Disease Risk among Adolescents: Results from the A-CHILD Study. Nutrients. 2020 Dec 16;12(12):3845.
日本語アブストラクト
「家庭料理は青少年の心血管疾患リスク低減と関連する: A-CHILD研究の結果」
【背景と目的】
本研究は、日本の思春期における家庭料理の頻度と心血管疾患リスクとの関連性を調査することを目的とした。
【方法】
日本の東京都足立区の中学2年生(13~14歳)の中学生を対象とした「2018年足立区子ども健康生活実態調査」の横断データを使用した。保護者553名による家庭料理の頻度を質問票で評価し、高(ほぼ毎日)、中(4~5日/週)、低(≦3日/週)に分類した。心血管疾患の危険因子として、血圧、血清コレステロール(総量、LDL、HDL)、ヘモグロビンA1c、BMIを用いた。
【結果】
重回帰分析の結果、家庭料理の頻度が低い思春期の子どもは、性、世帯収入、親の合併症を調整しても、家庭料理の頻度が高い子どもに比べて、拡張期血圧が高く(β = 3.59, 95% 信頼区間 [CI]: 0.42 to 6.75)HDL コレステロールが低い(β = -6.15, 95% CI: -11.2 to -1.07 )ことがわかった。
【結論】
家庭料理が思春期の子どもの心血管健康に影響を与える因果関係やメカニズムを明らかにするためには、今後の研究が必要である。 -
Nawa N, Kuramochi J, Sonoda S, Yamaoka Y, Nukui, Miyazaki Y, Fujiwara T*. Seroprevalence of SARS‐CoV‐2 in Utsunomiya City, Greater Tokyo, after the first pandemic in 2020. Journal of General and Family Medicine. 2020 Dec 16;22(3):160-162.
日本語アブストラクト
「2020年新型コロナウイルスパンデミック第1波後の宇都宮市における新型コロナウイルス感染症の血清有病率に関する研究」
【背景】
世帯ベースのランダムサンプルによるコホート調査を宇都宮市で実施することで、宇都宮市における新型コロナウイルス感染症の血清有病率を明らかにすることを目的とした。
【方法】
対象者の血中IgG抗体レベルをCLIA法を用いて評価した。また、新型コロナウイルス感染症の人口ベースの血清有病率を推定した。
【結果】
3例の無熱性陽性症例が確認された。新型コロナウイルス感染症の有病率はweightをかける前およびかけた後で、それぞれ0.40%、1.23%と推定された。
【結論】
本研究は、新型コロナウイルス感染症の有病率が過小評価されている可能性を示唆している。より広範な新型コロナウイルス感染症に対する検査戦略を実施すると、新型コロナウイルス感染症の症例がより多く同定される可能性が示唆された。 -
Fujiwara T*, Isumi A, Sampei M, Miyazaki Y, Yamada F, Noma H, Ogita K, Mitsuda N. Effectiveness of an Educational Video in Maternity Wards to Prevent Self-Reported Shaking and Smothering during the First Week of Age: A Cluster Randomized Controlled Trial. Prev Sci. 2020 Nov;21(8):1028-1036.
日本語アブストラクト
「産科病棟における生後1週の揺さぶりと口塞ぎ予防のための教育ビデオの効果: クラスターランダム化比較試験」
本研究の目的は、産科病棟で産後1週以内に乳児の泣きを引き金とする揺さぶりや口塞ぎの危険性に関する教育ビデオを視聴することにより、1ヵ月健診時に自己報告の揺さぶりや口塞ぎが減少するかどうかを検討することである。
大阪府の産科病院、産科クリニック45施設において、地域と病院機能で層別化したクラスターランダム化比較試験を行った。介入群では、産科病棟に入院中の母親が、生後1週以内に、乳児の泣きと乳児を揺さぶったり口塞ぎしたりすることの危険性に関する教育ビデオを、群の割り付けに関する盲検化なしに視聴した。対照群は通常のケアを受けた。2014年10月1日~1月31日に出産した母親(未熟児出産および妊娠週数22週未満は除外)計4722人(介入群2350人、対照群2372人)を参加対象とした。アウトカムは、自己申告による揺さぶり行動と口塞ぎ行動、乳児の泣きと揺さぶりに関する知識、乳児の泣きへの対処行動で、1ヵ月健診時の質問票で評価した。質問紙に回答したのは2718人(N=1078人、1640人)で(回答率58.3%)、分析標本数は2655(介入群1058、対照群1597)であった。クラスター内の相関を調整するためにマルチレベル分析を用いた。揺さぶりの有病率は介入群(0.19%)で対照群(1.69%)より有意に低かった。intention-to-treat解析では、介入により、自己申告による揺さぶりの有病率が89%減少した(OR:0.11、95%CI:0.02-0.53)。しかし、自己報告による口塞ぎ行動は有意な減少を示さなかった(OR:0.66、95%CI:0.27-1.60)。副作用は報告されなかった。産科病棟で分娩後1週以内に乳児の泣きと揺さぶりや口塞ぎの危険性に関する教育ビデオを視聴することにより、生後1ヵ月時の自己報告による揺さぶりが減少した。UMIN臨床試験レジストリUMIN000015558. -
Nawa N, Garrison-Desany H, Kim Y, Ji Y, Hong X, Wang G, Pearson C, Zuckerman BS, Wang X, Surkan P*. Maternal persistent marijuana use and cigarette smoking are independently associated with shorter gestational age. Paediatr Perinat Epidemiol. 2020 Nov;34(6):696-705.
日本語アブストラクト
「母親のマリファナの使用と喫煙は、妊娠期間の短縮と独立して関連している。」
【背景】
早産に対するマリファナ使用の影響を評価する研究では、妊娠中の母親の喫煙の役割に注意が払われていないこともあり、結果が定まっていない。
【目的】
本研究の目的は、母親のマリファナ使用が妊娠期間、早産、および2つの早産のサブタイプ(自然分娩vs誘発分娩)と独立して関連しているかどうかを検討することである。
【方法】
参加者はBoston Birth Cohortの母子8261組である。妊娠週数に関する情報は電子カルテから収集した。妊娠中のマリファナ使用と喫煙は、出産後の標準的な質問票により評価した。線形回帰モデルおよび対数線形回帰モデルを用いて、妊娠中の喫煙の有無それぞれの場合においてマリファナ使用とアウトカムとの関連を検討した。
【結果】
8261人の母親のうち、27.5%が早産であった。正期産の母親の約3.5%、早産の母親の約5.2%が妊娠中にマリファナを使用していた。マリファナの使用と喫煙は、それぞれ独立して妊娠週数の0.50週(95%信頼区間[CI]-0.87、-0.13)および0.52週(95%CI-0.76、-0.28)の減少と関連していた。妊娠初期または後期のマリファナ使用を分けて検討した場合も、それぞれ同様に妊娠週数の0.50週減少に関連していた。早産のサブタイプへの影響を検討したところ、マリファナ使用と喫煙がともにある場合には、自然早産リスクの上昇と関連していた(RR 1.64、95%CI 1.23、2.18)。誘発分娩による早産ではリスクの上昇は観察されなかった。
【結論】
今回の米国における高リスク集団を対象にしたコホートデータ研究において、妊娠中の母親の大麻使用および喫煙は、妊娠期間の短縮と独立して関連していた。早産のサブタイプへの影響を検討したところ、リスクの上昇は自然早産でのみ観察された。 -
Nakahara N, Matsuyama Y, Kino S, Badrakhkhuu N, Ogawa T, Moriyama K, Fujiwara T*, Kawachi I. The Consumption of Sweets and Academic Performance among Mongolian Children. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 30;17(23):8912.
日本語アブストラクト
「モンゴルの子どもにおけるお菓子消費と学業成績との関連」
お菓子の常食は、先進国では子どもの学業成績に悪影響を及ぼすことが示されているが、発展途上国の状況はあまり明らかではない。そこで、モンゴルの首都ウランバートルの公立学校2校に通う8~16歳の子ども787人のデータを用いて、モンゴルの子どもたちのお菓子摂取と学業成績との関連を横断研究で調べた。子どもたちのお菓子の摂取頻度をアンケートで把握し、学業成績との関連を他の共変量で調整した重回帰で評価した。787人の生徒のうち58.6%が毎日お菓子を食べており、共変量で調整した結果、お菓子の消費量と数学の得点の間には有意な関連は認められなかった(係数:0.15、95%信頼区間(CI):-0.02-0.32)。一方、お菓子の消費量が多いほど、モンゴル語の得点は有意に高かった(係数:0.25、95%CI:0.09-0.41)。本研究で見られた関連は、他の研究の報告とは異なる結果であることがわかった。 -
Aoki H, Ozeki N, Katano H, Hyodo A, Miura Y, Matsuda J, Takahashi K, Suzuki K, Masumoto J, Okanouchi N, Fujiwara T, Sekiya I*. Relationship between medial meniscus extrusion and cartilage measurements in the knee by fully automatic three-dimensional MRI analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Nov 12;21(1):742.
-
Morishita S, Yoshii T*, Okawa A, Inose H, Hirai T, Yuasa M, Fushimi K, Fujiwara T. Risk factors related to perioperative systemic complications and mortality in elderly patients with osteoporotic vertebral fractures-analysis of a large national inpatient database. J Orthop Surg Res. 2020 Nov 10;15(1):518. doi: 10.1186/s13018-020-02050-5.
-
Nagamine Y, Fujiwara T*, Tani Y, Murayama H, Tabuchi T, Kondo K. Gender difference in the association between subjective socioeconomic mobility across life course and mortality at older ages: Results from the JAGES longitudinal study. J Epidemiol. 2020 Nov 5;30(11):497-502.
日本語アブストラクト
「ライフコースにわたる主観的社会経済的地位の流動性と高齢期死亡率との関連における男女差: JAGES縦断研究の結果」
【背景】
社会経済的移動はライフコースを通じて健康に影響を与える。しかし、ライフコースにおける主観的社会経済的地位(SSS)の流動性と高齢時の死亡率との関連に性差があるかどうかはわかっていない。
【方法】
参加者は、日本老年学的評価研究(JAGES)の65~100歳の地域在住成人16,690人である。2010年に人口統計学的特徴、うつ病、生活習慣要因を含むベースライン情報を収集した。参加者の生命状態は、死亡記録とのリンクにより2013年に確認された。ライフコースの社会経済的地位の流動性を以下のカテゴリーに分類した:「持続的に高い」、「下方移動」、「上方移動」、「持続的に低い」。Cox比例ハザードモデリングを用いて、全死因死亡率のハザード比(HR)を推定した。
【結果】
「下方」群の死亡率HRは、「持続的に高い」群と比較して、男性で1.37(95%信頼区間[CI]、1.08-1.74)、女性で1.27(95%CI、0.94-1.71)であった。持続的に低い」群との比較では、「上昇」群のHRは女性で0.54(95%CI、0.35-0.83)、男性で0.91(95%CI、0.73-1.24)であった。客観的な社会経済的地位で調整しても関連は変わらなかったが、うつ病によって減弱した。
【結論】
「下方移動」は、男性では死亡率と関連していたが、女性では関連していなかった。うつ病はこの関連を媒介するようであった。上方移動の保護効果は女性で観察されたが、男性では観察されなかった。 -
Amagasa S, Inoue S*, Murayama H, Fujiwara T, Kikuchi H, Fukushima N, Machida M, Chastin S, Owen N, Shobugawa Y. Associations of sedentary and physically-active behaviors with cognitive-function decline in community-dwelling older adults: compositional data analysis from the NEIGE study. J Epidemiol. 2020 Nov 5;30(11):503-508.
-
Arai K*, Kunisaki R, Kakuta F, Hagiwara S-I, Murakoshi T, Yanagi T, Shimizu T, Kato S, Ishige T, Aomatsu T, Inoue M, Saito T, Iwama I, Kawashima H, Kumagai H, Tajiri H, Iwata N, Mochizuki T, Noguchi A, Kashiwabara T, Shimizu H, Suzuki Y, Hirano Y, Fujiwara T. Phenotypic characteristics of pediatric inflammatory bowel disease in Japan: results from a multicenter registry. Intest Res. 2020 Oct;18(4):412-420.
-
Nakagawa M, Nawa N, Takeichi E, Shimizu T, Tsuchiya J, Sato A, Miyoshi M, Kawai-Kitahata F, Murakawa M, Nitta S, Itsui Y, Azuma S, Kakinuma S, Fujiwara T, Watanabe M, Tanaka Y, Asahina Y*; Ochanomizu Liver Conference Study Group. Mac-2 binding protein glycosylation isomer as a novel predictive biomarker for patient survival after hepatitis C virus eradication by DAAs. J Gastroenterol. 2020 Oct;55(10):990-999.
-
Fujiwara T*, Doi S, Isumi A, Ochi M. Association of Existence of Third Places and Role Model on Suicide Risk Among Adolescent in Japan: Results From A-CHILD Study. Frontiers in Psychiatry. 2020 Oct 23;11:529818.
日本語アブストラクト
「サード・プレイスとロールモデルの存在が日本の思春期の子どもの自殺リスクに及ぼす影響: A-CHILD研究の結果」
【目的】
思春期の子どもの自尊心の低さは、自殺のリスク因子と考えられている。そこで、本研究の目的は、自尊心の低い子どもが多い日本において、サードプレイスとロールモデルの存在が自尊心の低さに及ぼす影響について検討することである。
【方法】
東京都足立区在住の小学4年生、6年生、中学2年生の生徒(N = 1,609)を対象に学校ベースの質問紙調査を実施した2016年足立区児童健康影響調査(A-CHILD)のデータを分析した。子どもたちは自尊心を自己評価した。自尊心の尺度において、10パーセンタイル以下のグループを自尊心が低いと定義した。また、サードプレイスの存在を「自宅や学校以外の放課後を過ごす場所」と定義し、ロールモデルを「親以外に尊敬する人がいる」と定義し、これらを自記式の質問紙で評価した。
【結果】
サードプレイスを持たない子どもは10.5%、ロールモデルを持たない子どもは6.1%であった。サードプレイスを持たない子どもは、低い自尊心と有意な関連を示した(OR:1.75、95%信頼区間(CI):1.09-2.81)。同様に、ロールモデルを持たない子どもは、低い自尊心を持つ可能性が3.34倍高かった(95%CI:1.98-5.62)。
【結論】
サードプレイスとロールモデルの存在は、日本の子どもにおける低い自尊心を予防するために重要であると考えられる。 -
Koyama Y, Fujiwara T*, Isumi A, Doi S. Association of parental social network diversity with behaviour problems and resilience of offspring in a large population-based study of Japanese children. BMJ Open. 2020 Oct 21;10(10):e035100. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035100.
日本語アブストラクト
「親の社会的つながりの多様性と、子どもの問題行動およびレジリエンスとの関連:日本における子どもの大規模調査より」
【背景】ソーシャルネットワークとは、個人を取り巻く社会関係の構造や特性のことであり、親のソーシャルネットワークと子どもの健康との関係について報告されてきた。しかし、ソーシャルネットワークの多様性については、その関係は明らかになっていない。本研究は、親のソーシャルネットワークの多様性が、その子どもの問題行動およびレジリエンスに与える影響を解明することを目的とした。
【方法】2016年に実施された「高知県子どもの生活実態調査」のデータを用いて、小学1年生・5年生・中学2年生の子ども(n=9653)を対象に解析を行った。親が日常的につながっている人の社会的役割の種類の数により親の構造的ソーシャルネットワークの多様性を、ソーシャルサポートを与えてくれる人の社会的役割の種類の数により機能的ソーシャルネットワークの多様性を算出した。親のソーシャルネットワークの多様性および子どもの問題行動とレジリエンスは、質問紙により親の回答を得た。
【結果】親の構造的・機能的ソーシャルネットワークが多様である子どもは問題行動が少なく、向社会的行動とレジリエンスが高かった。構造的・機能的ソーシャルネットワークの多様性と問題行動の関係はそれぞれ36%および43%が親のメンタルヘルスによって説明された。一方、機能的ソーシャルネットワークの多様性と向社会的行動との関係は、親の子に対するポジティブな関わりによって31%説明された。
【考察】子どものメンタルヘルス向上のために子どもに対して直接介入するのではなく、親のソーシャルネットワークの多様性に焦点を当てた新たな介入の可能性を提示した。
-
Fukuya Y, Matsuyama Y, Isumi A, Doi S, Ochi M, Fujiwara T*. Toothbrushing and School Refusal in Elementary School: A Longitudinal Study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 15;17(20):7505.
日本語アブストラクト
「小学校における歯磨き頻度と登校しぶりの関連: 縦断研究」
【目的】
本研究の目的は、小学生における歯磨き頻度と登校しぶりの関連を検討することである。
【方法】
2015年から2016年にかけて東京都足立区で実施された足立区子どもの健康・生活実態調査(A-CHILD)のデータを用いた。6~7歳の小学1年生全児童に質問票を配布した。傾向スコア(PS)マッチングを適用し、小学1年生時の歯磨き頻度に関する既知の共変量を、小学2年生時の登校しぶりとの関連を調べた(N=3697、追跡率:86.2%)。
【結果】
追跡した子どものうち、2年生で登校しぶりを示した子どもは2.4%(89人)であり、1年生での歯磨き回数が1日1回または1回未満であった子どもは23.5%(870人)であった。傾向スコアマッチングを行った結果、小1で歯磨きが1日1回以下の子どもは、1日2回以上の子どもに比べて、小2で登校しぶりを示すリスクが2.25倍(95%信頼区間:1.25-4.05)高かった。この結果から、歯磨きが1日1回または1回未満であることは、子どもの登校しぶりの独立したリスク因子であることが示唆された。
【結論】
1日2回以上の歯みがきを推奨する口腔ヘルスプロモーションは、登校しぶりを予防できる可能性がある。そのメカニズムや因果関係を明らかにするため、さらなる介入研究が必要である。 -
Koyama Y, Fujiwara T*, Isumi A, Doi S. Is Japan’s child allowance effective for the well-being of children? A statistical evaluation using data from K-CHILD study. BMC Public Health. 2020 Oct 6;20(1):1503.
日本語アブストラクト
「子ども手当は、子どものウェルビーイングに効果的か?:高知県子どもの生活実態調査による結果」
【背景】子ども手当は、世帯に対する金銭的サポートによって、子どもの貧困格差を縮小することを目的とした社会保障制度の一つであるが、この制度が子どもの健康に与える影響については明らかになっていない。したがって、本研究は子ども手当が、子どもの身体的・精神的健康に与える影響および、親の子どもに対する投資に与える影響を明らかにすることを目的とした。
【方法】2016年に実施された「高知県子どもの生活実態調査」のデータを用い、高知県に在住している小学1年生・小学5年生・中学2年生(n=8207)を対象とした横断研究である。保護者は子ども手当の受給状況、子どものBMI、問題行動について質問紙で回答した。抑うつ症状および主観的健康度については子ども自らが回答した。プロペンシティスコアマッチングおよび多重回帰分析を用いて交絡因子について調整した。
【結果】子ども手当を受け取っている世帯の子どもは問題行動が少なく、肥満のリスクが少なかった。親の子どもに対する投資およびその他の健康指標については統計的な優位差は見られなかった。
【結論】子ども手当は、子どもの問題行動および肥満のリスクを減らす可能性のあることが示唆された。今後、縦断調査などを用いて、子ども手当の用途について詳細に検討すること、また子どもの健康との関係のメカニズムを明らかにすることが必要である。
-
Koyama Y, Fujiwara T*, Isumi A, Doi S. Degree of influence in class modifies the association between social network diversity and well-being: Results from a large population-based study in Japan. Social Science & Medicine. 2020 Sep;260:113170.
日本語アブストラクト
「子どものクラス内における影響力は、ソーシャルネットワークの多様性とウェルビーイングの関係性を修飾するのか」
【背景】ソーシャルネットワークの多様性は身体的・精神的健康と関係があることが知られている。しかし、この関係は、家族以外の人との関係性が重要度を増してくる思春期の子どもにおいて報告がなく、また、この関係を修飾すると考えられる子ども自身の社会的地位を考慮した研究はない。そこで、本研究は、思春期の子どもにおいて、ソーシャルネットワークの多様性と身体的・精神的健康との関係を明らかにすること、およびクラス内における主観的な影響力がその関係性を修飾するのかを明らかにすることを目的とした。
【方法】2016年に実施された「高知県子どもの生活実態調査」のデータを用いて、小学5年生・中学2年生・高校2年生の子ども(n=9998)を対象に解析を行った。ソーシャルネットワークの多様性は、日常的な人間関係において担っている社会的役割の種類によって評価した。社会的地位は、「あなたの意見や行動はクラスメイトにどの程度影響を与えていますか」という質問を用いて、クラスにおける影響力により評価した。
【結果】ソーシャルネットワークが多様である子どもは、抑うつ症状及び問題行動が少なく、主観的健康度が高く、向社会的行動が多いことが明らかとなった。ソーシャルネットワークの多様性と抑うつ症状および主観的健康度の関係は、クラス内における主観的影響力の低い子どもにおいて強くなることが示された。
【考察】ソーシャルネットワークの多様性と思春期の子どもの身体的・精神的健康の間には用量反応関係があり、多様であるほど健康であることが明らかとなった。また、クラスでの影響力が低い子どもではその関係性が強くなることが示され、ソーシャルネットワークの多様性とクラスにおける社会的地位が子どもの健康を高める手掛かりとなることが示唆された。
-
Sato R, Fujiwara T*, Kino S, Kawachi I. The association between father involvement in caregiving and early childhood overweight or obesity. Pediatr Obes. 2020 Sep;15(9):e12652. doi: 10.1111/ijpo.12652.
日本語アブストラクト
「父親の育児参加と幼児期の子供の肥満との関連」
【背景】近年、父親の育児参加が増加傾向であるにもかかわらず、育児と子供の肥満に関する研究において父親が与える影響は明らかになっていない。
【目的】日本の縦断データを用いて、父親の育児参加の有無と子供の肥満との関連を検討する。
【方法】本研究は日本におけるコホート研究である21世紀出生縦断調査の2001年、2002年、2004年のデータを用いた(対象者29,584名)。父親の育児参加の有無(18カ月時)と3.5歳時の子供の肥満の有無を変数とした解析を行った。また、父親の育児参加の有無と母親の就業の有無に基づいて対象者を4つの集団に割り付け、交互作用を評価した。
【結果】父親の育児参加の度合いが高い子供は肥満である割合が低かった(オッズ比:0.96、95%信頼区間:0.94-0.98)。また、母親が就業している場合、父親の育児参加の度合いが高い子供は低い子供と比較して肥満である割合が30%低かった(95%信頼区間:0.55-0.90)。
【結論】本研究から、父親の育児参加の有無は幼児期の子供の肥満と関連することが明らかになり、また、母親の就業の有無と子供の肥満との関連にも影響することが示唆された。育児休暇の拡張等、両親がともに育児に参加することを支援する社会的制度を整備することが、子供の肥満の防止のために必要であると考えられる。
-
Doi S*, Isumi A, Fujiwara T. The association between parental involvement behavior and self-esteem among adolescents living in poverty: Results from the K-CHILD study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 28;17(17):6277.
日本語アブストラクト
「生活困難下にある思春期児童における養育行動と自己肯定感の関連:高知県子どもの生活実態調査」
【背景】生活困難下にある児童のなかでも、自己肯定感が高い児童とそうではない児童がいますが、その理由は明らかになっていません。生活困難下にある児童の自己肯定感を向上する重要な要因として親の養育行動が挙げられます。本研究では、生活困難下にある児童において、どの養育行動がより自己肯定感の向上につながるかを明らかにすることを目的としました。
【方法】2016年に実施された高知県子どもの生活実態調査(K-CHILD)のデータ(N=10,784)の一部を用いて、高知県に住む小学5年生、中学2年生、高校2年生の児童およびその保護者を対象としました。児童と保護者は、親子の関わりに関する9個の養育行動(例:「学校生活について話す」)、子どもの身体的健康へのケアに関する5個の養育行動(例:「必要なときに病院に連れていく」)を含む14個の養育行動、社会経済的状況などについて質問紙で回答しました。14個の養育行動、9個の親子の関わり、5個の子どもの身体的健康へのケアそれぞれについて、自己肯定感との関係を検証しました。
【結果】養育行動が多ければ多いほど、児童の自己肯定感の高さを関係していました。この関係性は、生活困難下にある児童においても、そうではない児童においても示され、生活困難と養育行動の相互作用は認められませんでした。また、親子の関わり、子どもの身体的健康へのケアのいずれも、自己肯定感の高さと関係していましたが、親子の関わりの方が効果量は大きいことが明らかになりました。
【考察】生活困難下にある児童の自己肯定感を向上するために、保護者は子どもとの関わりを増やし、子どもの身体的健康面へのケアをすることが重要だと考えられます。
-
Sampei M, Fujiwara T*. Association of Infertility Treatment with Perception of Infant Crying, Bonding Impairment and Abusive Behavior towards One’s Infant: A Propensity-Score Matched Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 21;17(17):6099.
日本語アブストラクト
「不妊治療と乳児の泣き声の認知、ボンディング障害、乳児に対する虐待行動との関連: 傾向スコアマッチ分析」
【背景】
不妊治療と乳幼児に対する否定的感情との関連を示唆する先行する質的研究があるが、不妊治療と乳幼児の泣き、ボンディング障害、乳幼児に対する虐待行動の認知との関連を調査した実証的集団ベースの研究はほとんどない。
【方法】
愛知県の4ヵ月健診に参加した女性(n=6590)を対象に、不妊治療歴、乳児の泣き声の認知、Mother to Infant Bonding Scale日本語版で評価した母子のボンディング障害、乳児に対する虐待行動などの質問票に回答してもらった。アウトカムは2値化され、既知の共変量で調整した不妊治療曝露の傾向スコアマッチを用いて条件付きロジスティック回帰を適用した。
【結果】
合計690例(11.1%)が不妊治療歴を報告し、625例がマッチした。その結果、不妊治療歴のある母親は、乳児の泣き声の頻度が高いと感じる可能性が1.36倍高かった(95%信頼区間(CI):1.05-1.78)が、母子のボンディング障害(オッズ比(OR):1.18、95%CI:0.81-1.72)および乳児に対する虐待行動(OR:0.82、95%CI:0.49-1.36)との関連は認められなかった。
【結論】
不妊治療は、乳児の泣く頻度が高いという認識と関連しているかもしれないが、ボンディング障害や虐待行動とは関連していない。この知見を再現するためには、さらなる縦断的研究が必要である。 -
Hirata K, Nambara T, Kawatani K, Nawa N, Yoshimatsu H, Kusakabe H, Banno K, Nishimura K, Ohtaka M, Nakanishi M, Taniguchi H, Arahori H, Wada K, Ozono K, Kitabatake Y*. 4-Phenylbutyrate ameliorates apoptotic neural cell death in Down syndrome by reducing protein aggregates. Sci Rep. 2020 Aug 20;10(1):14047.
-
Amagasa S, Inoue S*, Murayama H, Fujiwara T, Kikuchi H, Fukushima N, Machida M, Chastin S, Owen N, Shobugawa Y. Changes in rural older adults’ sedentary and physically-active behaviors between a non-snowfall and a snowfall season: compositional analysis from the NEIGE study. BMC Public Health. 2020 Aug 17;20(1):1248.
-
Yoshii T*, Morishita S, Inose H, Yuasa M, Hirai T, Okawa A, Fushimi K, Fujiwara T. Comparison of perioperative complications in anterior decompression with fusion and posterior decompression with fusion for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: Propensity score matching analysis using a nation-wide inpatient database. Spine. 2020 Aug 15;45(16):E1006-E1012.
-
Nawa N, Numasawa M, Nakagawa M, Sunaga M, Fujiwara T, Tanaka Y, Kinoshita A*. Differential effects of individual and school factors on the academic trajectories of Japanese dental students. J Dent Educ. 2020 Jul;84(7):792-798.
日本語アブストラクト
「日本の歯学部学生の学業成績の軌跡に対する個人要因と学校要因の影響の検討」
【目的】
歯学部学生は,学年を経るにつれて増加する学習するべき内容の増加に対して、個人要因と学校要因によって異なる学力軌跡をたどる。
group-based trajectory modelingは,学生の学業成績の軌跡がとる一定のパターンとその決定因子を明らかにするのに有用である。
我々の知る限り、group-based trajectory modelingを用いて、歯学部学生の学業成績の軌跡に対する個人要因および学校要因の影響を検討した研究はない。本研究の目的は、group-based trajectory modelingを用いて、日本の歯学部学生の学業成績の軌跡に対する、個人要因と学校要因の影響を検討することである。
【方法】
2013年と2014年に東京医科歯科大学に入学した歯学部学生103名のデータを解析した。学生の学業成績は年2回のGPAスコアで評価され、本研究では2年生から4年生のGPAが用いられた。まず、group-based trajectory modelingを用いて、生徒のGPAの軌跡を異なるグループに分類した。次に、多項ロジスティック回帰モデルを用いて生徒の個人および学校要因と、特定のGPAグループに割り当てられる確率との関連を検討した。
【結果】
歯学部学生のGPAは4つのグループに分類された。高校時代の学業成績は、より低いGPA軌道を辿るグループに属する確率や退学・留年の確率と関連していた。男性であることは、過去の学業成績で調整した後でも、より低いGPA軌道を辿るグループに属する確率や退学・留年の確率と有意に関連していた。
【結論】
解析の結果、高校時代の学業成績そして男性であることが、歯学部学生においてより低いGPA軌道を辿るグループに属する確率や退学・留年の確率と関連していた。 -
Matsuyama Y, Isumi A, Doi S, Fujiwara T*. Longitudinal analysis of child resilience link to dental caries. Pediatr Dent. 2020 Jul 15;42(4):308-315.
日本語アブストラクト
「子どものレジリエンスとう蝕との関連についての縦断的分析」
【目的】
小学校1年生における親子の関わり、小学校2年生における子どものレジリエンスと小学校4年生におけるう蝕罹患率との関連を検討する。
【方法】
足立区子どもの健康・生活実態調査(A-CHILD)の3,168人の子どもの縦断的データを分析した。2015年、東京都足立区の公立小学校1年生全児童の養育者から子育て行動に関する回答を得た。小学2年生では、子どものレジリエンスと口腔保健行動を測定した。小学4年生におけるう蝕罹患率は、学校での歯科健診時に評価した。構造方程式モデリングを適用した。
【結果】
小学1年生における親子の関わりは、小学2年生における児童の高いレジリエンスと関連し(標準化係数[β]は0.402、95%信頼区間[95%CI]は0.357~0.446)、これは同年の良好な口腔保健行動と関連した(βは0.236、95%CIは0.159~0.313)。良好な口腔保健行動は、小学4年生におけるう蝕罹患率と逆相関していた(βは-0.108、95%CIは-0.170~-0.045)。
【結論】
親子の関わりは、子どものレジリエンスの向上およびう蝕罹患率の低下と関連していた。 -
Doi S*, Fujiwara T, Isumi A. Association between maternal adverse childhood experiences and child’s self-rated academic performance: Results from the K-CHILD study. Child Abuse Negl. 2020 Jun;104:104478.
日本語アブストラクト
「母親の子ども期の逆境体験と子どもの学業成績との関連:高知県子どもの生活実態調査」
【背景】母親の子ども期の逆境体験(Adverse Childhood Experiences: ACEs)は、その子どもの身体的・精神的健康や発達に悪影響を及ぼすことがわかっている。一方で、母親のACEsが思春期児童の学業成績と関連するかは明らかになっていない。
【目的】母親のACEsが、子どもの学業成績と関係するかを明らかにする。
【方法】本研究では、2016年に実施された高知県子どもの生活実態調査のデータの一部を用いて、高知県の小学校5年、中学校2年、高校2年の全児童・生徒およびその保護者10,810組を対象とした。母親のACEs(両親の離婚、虐待やネグレクトなど7項目)、年齢など基本属性、幼少期の経済状況、現在のメンタルヘルスおよび虐待傾向について、母親に回答を求めた。子どもの基本属性、学校の成績に関する自己評価(1項目5件法)、自己肯定感について、子どもに回答を求めた。保護者回答が母親以外である、ACEsと学業成績に欠損がある、自己肯定感が低いことで学業成績の自己評価が低くなるというバイアスを回避するために、自己肯定感の得点が下位10%以下であった児童を除外し、7,964名を解析の対象とした。母親のACEs(0個、1個、2個、3個以上)を説明変数、子どもの自己評価による学業成績を目的変数とした順序ロジスティック回帰分析を行なった。
【結果】母親の年齢を交絡変数として調整した場合、母親のACEsと子どもの学業成績の関連は用量反応関係にあった(p trend < 0.001)。母親のACEsの中でも、親の不在(両親の離婚または親の死)が子どもの低い学業成績と関係していた(オッズ比:1.31、95%信頼区間:1.16-1.47)。一方、幼少期の被虐歴と子どもの学業成績との関連は有意ではなかった(オッズ比:1.10、95%信頼区間:0.99-1.22)。
【結論】本研究から、母親のACEsの経験個数が多いほど、その子どもの学業成績は低くなることが明らかとなった。また、母親のACEsの中でも親の不在が子どもの成績に影響している可能性が示唆された。今後は、母親のACEsが子どもの学業成績に与えるメカニズムを解明する必要がある。
-
Tani Y*, Fujiwara T, Kondo K. Cooking skills related to potential benefits for dietary behaviors and weight status among older Japanese men and women: a cross-sectional study from the JAGES. Int J Behav Nutr Phys Act. 2020 Jun 26;17(1):82.
日本語アブストラクト
「高齢者の調理技術と食行動及び体格との関連について」
■背景:家庭で調理をすることが、食事の質向上や適切な体重維持に重要であることが報告されています。家庭での調理を促すには、食事を準備する人の調理技術が重要であると考えられますが、調理技術が家庭での調理頻度や健康に及ぼす影響についてはほとんど明らかにされていません。また、調理技術には性差があり、食事を作ってくれる人がいない男性の場合、調理技術の低さが大きな健康リスクにつながる可能性があります。そこで、本研究では日本人向け調理技術尺度を作成し、高齢者の調理技術と食行動及び体格との関係性について男女別に解析を行い、さらに食事を作ってくれる人がいない男性についてもそれらの関係性を調べました。
■対象と方法:2016年に実施したJAGES調査に参加した全国39市町在住の要介護認定を受けていない65歳以上の高齢男性9,143名、女性10,595名。調理技術は、参加者に7項目(1, あなたの調理技術はどのくらいですか 2, 野菜や果物の皮をむくことができますか 3, 野菜や卵をゆでることができますか 4, 焼き魚を作ることができますか 5, 野菜や肉の炒め物を作ることができますか 6, 味噌汁を作ることができますか 7, 煮物を作ることができますか)について全くできないからよくできるまで、6段階で評価(1〜6点)してもらい、全項目の平均点を調理技術スコアとし、スコア>4.0を高調理技術群, 2.1–4.0を中調理技術群, ≤2.0を低調理技術群と定義しました。女性は低調理技術群の割合が1%と少なかったため、中調理技術群と合わせたものを中/低調理技術群(≤4.0)としました。「あなたの日頃の食事は、主にどのように準備されますか」の問いに「家族が調理」以外を選択した男性を「食事を作ってくれる人がいない男性」と定義しました。食行動は低調理頻度(男:0回、女:≤2回/週)、高外食頻度(≥3回/週)、低野菜果物摂取(<1回/日)と定義しました。体格はやせをBMI < 18.5 kg/m2、肥満を≥ 27.5 kg/m2と定義しました。低調理頻度リスク、高外食頻度リスク、低野菜果物摂取リスク、やせリスク、肥満リスクは、年齢、教育歴、収入、婚姻状況、治療中または後遺症のある病気(がん、心臓病、脳卒中、糖尿病、高血圧、高脂血症)の影響を調整して統計学的な評価を行いました。
■結果:調理技術スコアの平均点は男性より女性の方が高く、男4.1点、女5.6点でした。男性では、高調理群が4751人、中調理群が3269人、低調理群が1123人、女性では、高調理群が9968人、低調理群が627人でした。調理頻度は、男性では54%(n=4917)が調理をしていないのに対し、女性では83%(n=8762)が週に5回以上調理しており、週2回以下の割合は9%(n=931)でした。男性は週3回以上外食していた人が8%(n=704)、女性では3.5%(n=371)でした。年齢、教育歴、収入、婚姻状況、治療中または後遺症のある病気の影響を取り除いて解析した結果、高調理群に比べ、調理技術が低いと、低調理頻度リスクが男女とも約3倍、食事を作ってくれる人がいない男性では8倍、高外食頻度リスクは男性で1.3倍、食事を作ってくれる人がいない男性では2.3倍、低野菜・果物摂取リスクは女性で1.6倍、やせリスクは男性で1.4倍、食事を作ってくれる人がいない男性では3倍でした。
■結論:調理技術が低いと不適切な食行動とやせのリスクとなる可能性が示唆されました。さらに、食事を作ってくれる人がいない男性ではそのリスクが高いことがわかりました。
■本研究の意義:高齢期になると、生活環境の変化や配偶者が調理困難になる等により家庭内で食事を準備する人が変化する可能性があります。調理技術を高める介入が健康維持に効果的かもしれません。
-
Kizuki M*, Fujiwara T. Quality of supervisor behaviour, workplace social capital and psychological well-being. Occup Med (Lond). 2020 Jun 20;70(4):243-250.
日本語アブストラクト
「上司の行動の質、職場のソーシャルキャピタル、心理的幸福の関連」
【背景】
職場のソーシャルキャピタル(職場の人間関係、信頼、互恵性)が高い従業員ほど、メンタルヘルスの問題を有するリスクが低い。上司の行動は職場ソーシャルキャピタルの予測因子である可能性がある。
【目的】
上司の行動、職場のソーシャルキャピタル、心理的幸福との関連を検討すること。
【方法】
第6回欧州労働条件調査の二次分析を行った。調査サンプルは、直属のラインマネージャーを持つ欧州35カ国の従業員28 900人である。うつ病はWHO-5幸福度指数で評価した。上司の行動の質と職場のソーシャルキャピタルは、それぞれ6項目の質問で測定された。上司の行動の質と職場のソーシャルキャピタルとの関連は、階層的線形モデリングを用いて分析した。職場のソーシャルキャピタル指数がある場合とない場合のうつ病について、階層ロジスティック・モデルを用いて媒介分析を行った。
【結果】
上司の行動質指数が高いほど、職場のソーシャルキャピタル指数が高かった(β、0.55;95%信頼区間[CI]、0.51-0.59)。職場のソーシャルキャピタル指数が高いほど、うつ病のオッズが低かった(オッズ比[OR]、0.89;95%CI、0.87-0.90)。より高い上司の行動質指数は、より低いうつ病のオッズと関連していた(OR、0.90;95%CI、0.89-0.92)。その効果の58%は、職場のソーシャルキャピタルによって媒介された。
【結論】
我々の知見は、上司の行動の質の向上が職場のソーシャルキャピタルを増加させ、従業員の心理的幸福に寄与するという仮説を支持するものであった。このことは、労働者のメンタルヘルスを高めるための組織的介入を計画する上で有用であろう。 -
Yamada A, Isumi A, Fujiwara T*. Association between Lack of Social Support from Partner or Others and Postpartum Depression Among Japanese Mothers: A Population-Based Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 15;17(12):4270.
日本語アブストラクト
「夫や他の人からのソーシャルサポートの欠如と母親の産後うつとの関連:人口ベース横断研究」
【背景・目的】ソーシャルサポートの欠如は産後うつのリスク因子として知られている。しかし、夫や他の人からのソーシャルサポートの欠如と産後うつの関連は十分解明されていない。そこで本研究ではこれらの関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】2012年10~11月に愛知県で3~4ヶ月健診に参加した母親9707名に質問紙を配布し6590名(回答率:68%)から回答を得た。夫や他の人からのソーシャルサポートは、夫および他の人(両親、親戚、友人)に育児について相談できるかに基づいて評価した。産後うつはエジンバラ産後うつ病質問票を用いて評価した。母親を4つのカテゴリーすなわち、夫および他の人のいずれのサポートもなし、夫のサポートのみあり、他の人のサポートのみあり、夫および他の人の両方のサポートあり、に分類し多重ロジスティック回帰分析を行った。
【結果】夫および他の人の両方のサポートのある母親と比べ、夫および他の人のいずれのサポートもない母親では産後うつが7.22倍(オッズ比:7.22, 95%信頼区間:1.76–29.6)、夫のみのサポートがある母親では2.34倍(オッズ比:2.34, 95%信頼区間:1.37–3.98)、他の人のみのサポートがある母親では3.13倍(オッズ比:3.13, 95%信頼区間:2.11–4.63)、多かった。
【結論】他の人からのソーシャルサポートがある母親においても、夫からのソーシャルサポートの欠如は産後うつのリスクとなることが明らかとなった。夫からのサポートのない母親に着目した産後うつ予防の取り組みが必要であると考えられる。
-
Yang J, Tani Y, Tobias DK, Ochi M, Fujiwara T*. Eating Vegetables First at Start of Meal and Food Intake among Preschool Children in Japan. Nutrients. 2020 Jun 12;12(6):1762.
日本語アブストラクト
「保育園児における野菜から食べることと食物摂取量との関連」
【背景】食行動は、食事の質や長期的な健康にとって重要です。本研究では、就学前の子どもたちが、食事の際に「最初に野菜を食べる」という食行動と食物摂取量との関連を調べました。
【方法】東京都足立区にある7つの保育園の幼児135人を対象とした横断データを用いました。保護者は、子どもの食行動と食事に関する調査に記入しました。食事の調査は幼児用簡易型自記式食事歴法質問票(BDHQ3y)を用いました。最初に野菜を食べる頻度とそれぞれの食品群の食物摂取量を頻度線形回帰分析にて解析し、パーセント差と対応する95%信頼区間(95%CI)を算出しました。
【結果】子ども達が食事の際に最初に野菜を食べる頻度は、「毎回」が25.2%、「時々」が52.6%、「ほとんどまたはまったくない」が22.2%でした。多変量解析の結果、他の共変量を調整した後でも、最初に野菜を食べる行動と野菜摂取量については有意な関連があり、最初に野菜を食べる頻度が「ほとんどまたはまったくない」群と比較して、「時々」群では27%(95%CI:0〜63%)、「毎回」群では93%(95%CI:43–159%)でした。果物、肉、魚、穀類、お菓子など、他の食品群では、最初に野菜を食べる頻度による摂取量に有意差は見られませんでした。
【結論】日本の就学前児童では、食事の際に最初に野菜を食べる頻度が多い子どもは、最初に野菜を食べる頻度が少ない子どもと比較して、野菜の総摂取量が多いことがわかりました。
-
Nawa N, Nakamura K, Fujiwara T*. Oxytocin response following playful mother-child interaction in survivors of the Great East Japan Earthquake. Frontiers in Psychiatry. 2020 Jun 3;11:477.
日本語アブストラクト
「東日本大震災被災者における親子間のふれあいのセッションに伴うオキシトシン濃度の変化、及びその後の子どもの問題行動への影響」
【背景】
自然災害を経験した子どもはメンタルヘルスの問題や問題行動を発症するリスクが高い。メンタルヘルスの問題や問題行動の予防のためには、災害前からの良好な親子の関わり合いが重要であることが示唆されており、その予防効果のメカニズムとしては、親子の関わり合いによるオキシトシンの上昇の影響が示唆されている。実際、Feldmanらは、親と乳児が相互に関わり合いを行った後、親と乳児のオキシトシンレベルが上昇することを報告している。しかし、トラウマ体験後にはそのようなオキシトシンレベルの上昇が鈍化することも知られており、自然災害を経験した子どもにおいて、親子の関わり合い後のオキシトシン濃度の変化やその後の子どもの問題行動への影響を評価することは重要である。本研究では、東日本大震災を経験した34組の親子を対象に、親子間のふれあいが親子のオキシトシン濃度に及ぼす影響、母親のオキシトシン濃度の変化がその後の子どもの問題行動に及ぼす影響について検討した。
【方法】
東日本大震災後の2012年より開始し、2017年まで毎年調査を実施したコホート調査のデータを解析した。2015年に親子間のふれあいのセッションを行い、セッションの前後に唾液オキシトシン濃度を測定した。問題行動は、2017年にChild Behavior Checklistを用いて評価した。固定効果回帰分析を行い、親子間のふれあいのセッションがオキシトシン濃度に及ぼす影響を、セッション後 10 分間の変化とセッション前10 分間の変化を比較することで測定した。また、親子間のふれあいのセッション前後の母親のオキシトシン濃度の変化が、2017年度の子どもの問題行動の程度に及ぼす影響を検討した。
【結果】
親子間のふれあいのセッションにより母親のオキシトシン濃度の有意な増加が検出され、特に第一子の男子の母親で顕著であった(2.63 pg/mg protein. 95%CI:0.45、4.81)。心理的苦痛やトラウマ体験の程度が強い母親では、オキシトシンレベルの増加は低かった。最後に、母親のオキシトシン増加の程度が強いと、有意に2年後の子どもの外的問題行動(非行的行動と攻撃的行動)の程度が低いことがわかった。
【結語】
本研究の結果から、自然災害後のリソースが限られた状態でも、点鼻投与などの方法ではなく、母子のふれあいを介したオキシトシン濃度の上昇により、子どもの問題行動への予防的介入が有効である可能性が示唆された。 -
Doi S, Fujiwara T*, Isumi A, Mitsuda N. Preventing postpartum depressive symptoms using an educational video on infant crying: A cluster randomized controlled trial. Depress Anxiety. 2020 May;37(5):449-457.
日本語アブストラクト
「乳児の泣きに関する教育ビデオによる産後うつ症状の予防効果:クラスターランダム化比較試験」
【背景・目的】母親の産後の抑うつ症状のリスク要因の中でも、乳児の泣きに対する認識と対処行動は変容可能なリスク要因である。乳児の泣きは虐待(乳児の揺さぶりや口塞ぎ)につながることから、乳児の泣きに関する教育ビデオが複数開発され、虐待の予防効果が示されている。一方、乳児の泣きに関する教育ビデオによる産後の抑うつ症状の予防効果は明らかにされていない。そこで本研究では、産科での入院中(産後1週間)に、乳児の泣きに関する教育ビデオを視聴することによって、産後1ヶ月時点で抑うつ症状を呈する母親の割合が減少するか検討することを目的とした。また、乳児の泣きに対する認識と対処行動は母親の年齢によって異なるため、母親の年齢によって予防効果が異なるかも検討した。
【方法】大阪府の150の産科医療機関のうち47施設が研究参加に同意した。地域別および病院の機能別に層別化し、参加施設を介入群と対照群に無作為に割り付けた。介入群の母親は、産後1週間の入院中に約11分の乳児の泣きに関する教育ビデオを視聴した。44施設(介入群22施設、対照群22施設)が実施し、産後1ヶ月時点の質問紙への回答が得られた介入群1,040名、対照群1,561名を解析対象とした(回答率:介入群=47.2%、対照群=69.3%)。産後の抑うつ症状の評価には、Edinburg Postnatal Depression Scale(EPDS)を使用し、9点以上を「抑うつ症状あり」とした。
【結果】産後1ヶ月に抑うつ症状を呈していた母親は、対照群で250名(16.0%)、介入群で142名(13.7%)であった。Intention-to-treat analysisの結果、介入群と対照群で産後の抑うつ症状の割合に差はなかった(OR=0.85; 95%CI=0.64-1.12)。一方、25歳未満の母親を対象とした場合、対照群と比べて介入群の抑うつ症状を呈する母親が67%減少していた(OR=0.33; 95%CI=0.15-0.72)。25歳以上の母親を対象とした場合には、予防効果は認められなかった(OR=0.94; 95%CI=0.70-1.26)。
【結論】産後1週間の入院中における乳児の泣きに関する教育ビデオの視聴によって、産後1ヶ月の抑うつ症状を予防する効果は認められなかった。しかし、若年の母親(25歳未満)に限った場合は、乳児の泣きに関する教育ビデオ視聴によって産後の抑うつ症状が予防されることが明らかとなった。産後1週間の入院という既存の枠組みに加えられること、専門的スタッフが必要ないことなど、低いコストで実施可能な予防的介入の一つとなるだろう。今後は、若年以外の母親に対する予防的介入について検討する必要がある。
-
Nawa N, Numasawa M, Nakagawa M, Sunaga M, Fujiwara T, Tanaka Y, Kinoshita A*. Associations between demographic factors and the academic trajectories of medical students in Japan. PLOS ONE. 2020 May 18;15(5): e0233371.
日本語アブストラクト
「日本の医学部学生における人口統計学的因子と学業成績の軌跡との関連性」
【背景】
Group-based trajectory modelingは、学生の学業成績の軌跡とその決定要因を分類するのに有用なツールである。分析から得られた知見を用いることで、学業成績が低下するリスクのある学生を特定し、彼らをフォローして支援を提供することができる。現在までのところ、医学部学生における人口統計学的要因と学業成績の軌跡との関連を調査した研究は少ない。本研究の目的は、Group-based trajectory modelingを用いて、医学部学生における人口統計学的要因と学業成績の軌跡との関連を検討することである。
【方法】
2013年と2014年に東京医科歯科大学に入学した医学部学生(n = 202)のデータを解析した。学業成績は、前臨床の学年の年2回のGPAスコアで評価した。Group-based trajectory modelingを用いて、学生のGPAの軌跡を分類した。多項ロジスティック回帰を用いて、あるGPA軌跡グループに属する確率と、高校の種類、高校の地域、入学試験の種類、高校卒業年度、生物学専攻かどうか、性別などの人口統計学的要因との関連を検討した。
【結果】
医学部学生のGPAの軌跡は、4つの軌跡グループと、退学または留年をした生徒からなる別のグループに分類された。解析の結果、高校の地域が首都圏以外の生徒は、首都圏の生徒に比べて、退学や留年をする可能性が7.2倍高いことがわかった(OR: 7.21, 95% CI: 1.87, 27.76)。さらに、入学試験の種類、高校卒業年度、性別がGPAの推移と関連していた。
【結論】
高校の地域、入学試験の種類、高校卒業年度、性別はGPAの軌跡と関連していた。これらの知見は、学業成績が低下するリスクのある生徒を特定し、適切かつタイムリーな支援を提供するために学生をフォローするための重要な知見を提供するものである。 -
Shinsugi C, Tani Y, Kurotani K,Takimoto H, Ochi M, Fujiwara T*. Changein growth and diet quality among preschool children in Tokyo, Japan. Nutrients. 2020 May 1;12(5):1290.
日本語アブストラクト
「就学前児童の食事の質と発育の変化の関連」
背景:幼少期における健やかな発育には、質・量ともに適切な食事摂取が重要である。本研究は、就学前児童の食事の質と1年後の発育状況との関連を検討することを目的とした。
方法:東京都足立区保育園の幼児110名(男児54名及び女児56名、ベースライン時4-5歳)を解析対象とした。体格は、WHOの成長曲線を基に、年齢に対する身長のZスコア(height-for-age z-score, HAZ)及び年齢に対するBMIのZスコア(BMI-for-age z-score, BAZ)を算出し、身体発育状況を評価した。食事の質スコアは、日本人幼児用簡易型自記式食事歴訪質問票(BDHQ3y)を用いて収集した食事摂取量より、食事バランスガイドを基に、主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物、総エネルギー、菓子・嗜好飲料由来のエネルギーの各摂取量を10点満点として評価し、70点満点の食事バランスガイド遵守得点を算出した。
結果:ベースライン時の痩せ(BAZ<-1SD)及び発育阻害(HAZ+1SD)の割合は14.6%であった。回帰分析の結果、食事の質と1年後の発育には統計的に有意な関連はみられなかった(低スコアと比べて、BAZ:中スコアβ= 0.16(95%信頼区間: -0.29-0.60)、高スコアβ= −0.14(95%信頼区間: −0.61-0.33)、HAZ:中スコア β= −0.15(95%信頼区間: −0.50-0.21)、高スコアβ= −0.06(95%信頼区間: −0.43-0.30)。
結論:幼児の健やかな発育に資する適切な食事摂取に関して、さらなる研究が必要である。
-
Morishita S, Yoshii T*, Okawa A, Fushimi K, Fujiwara T. Comparison of perioperative complications between anterior decompression with fusion and laminoplasty for cervical spondylotic myelopathy: Propensity score-matching analysis using Japanese diagnosis procedure combination database. Clin Spine Surg. 2020 Apr;33(3):E101-E107.
-
Michihata N, Fujiwara T*, Okuyama M. Impact of a govermnmental intervention to improve access to child psychiatric services in Japan. Ann Clin Epidemiol. 2020 Apr 28;2(2):51-60.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ace/2/2/2_No.20-07/_article/-char/ja/
-
井上裕子、松山祐輔、伊角彩、土井理美、越智真奈美、藤原武男*.「子どものう蝕に対する保護者の消極的受診態度に関する要因の探索的研究」日本公衆衛生雑誌. 2020;67(4):283-294.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jph/67/4/67_19-026/_article/-char/ja/
-
Morita A*, Fujiwara T*. Association between childhood suicidal ideation and geriatric depression in Japan: A population-based cross-sectional study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Mar 27;17(7):2257.
日本語アブストラクト
「日本における子ども期の自殺念慮と老年期うつ病との関連: 住民ベースの横断研究」
子ども期の逆境体験(ACE)は、メンタルヘルスの悪化を介して、晩年のうつ病のリスクを高めると想定されているが、子ども期の精神的苦痛と老年期のうつ病との関連は直接的に検討されていない。本研究では、涌谷市の地域在住で機能的に自立した高齢者1140人の住民ベースの横断調査データを用いて、子ども期の自殺念慮と老年期のうつ病との関連を検討した。子ども期の自殺念慮については、18歳以前に自殺未遂を真剣に考えたことがあるかどうかを尋ねることで評価し、老年期うつ病については、15項目の老年期うつ病尺度の日本語版を用いて評価した。潜在的な交絡因子と媒介因子を調整するためにポアソン回帰を適用した。合計で、参加者の6.1%が小児期の自殺念慮を報告した。性別、年齢、性格属性、ACEで調整した上で、子ども期の自殺念慮は老年期うつ病有病比[PR]と正の相関を示した(PR: 1.40、95%信頼区間(95%CI):1.04-1.88)。老年期うつ病のPRの増加は、成人期の社会経済的状態、最近の生活上のストレス要因、現在の健康状態についてさらに調整した後でも有意なままであった(PR:1.38、95%CI:1.02-1.88)。さらなる前向き研究が必要であるが、自殺念慮のある子どもに精神保健サービスを提供する努力は、蔓延している老年期うつ病を減少させる可能性がある。 -
Fujiwara T*, Isumi A, Sampei M, Yamada F, Miyazaki Y. Effectiveness of using an educational video simulating the anatomical mechanism of shaking and smothering in a home-visit program to prevent self-reported infant abuse: A population-based quasi-experimental study in Japan. Child Abuse Negl. 2020 Mar;101:104359.
日本語アブストラクト
「揺さぶりに関する解剖学的メカニズムと口塞ぎに関する教育的ビデオを家庭訪問で使用した場合の自己申告乳児虐待の予防効果:日本における人口ベースの擬似実験的研究」
背景:より視聴者にとってインパクトのある、乳児の頭が揺さぶられることによってどうなるかをコンピューターグラフックスによる解剖学的なメカニズムに基づいて示したビデオの効果検証を行ったものはない。また、泣きに対して口塞ぎを行なってはいけないことを明示したビデオの効果検証もこれまでにない。
目的:本研究は、乳児の泣きおよび揺さぶり、口塞ぎの危険性に関する教育的ビデオを産後2ヶ月における家庭訪問で視聴させた時に、4ヶ月健診における自己申告の揺さぶりおよび口塞ぎがどの程度予防できるのかを検証することである。
方法:日本のA市における擬似実験的研究として、助産師、保健師、トレーニングされたボランティアによる産後2ヶ月時の家庭訪問において教育的ビデオの介入を行った。4ヶ月健診時において、対象となった産婦にビデオの視聴状況、自己申告による揺さぶり、口塞ぎ行動および他の共変量について質問紙で調査した。ビデオ視聴と自己申告の揺さぶり、口塞ぎへ関係について多変量ロジスティック解析を行った。
結果:合計で5961名の産婦が質問紙に有効回答をした(有効回答率:73.8%)。調整したモデルにおいて、ビデオを見た産婦は、乳児を揺さぶる割合が74%(オッズ比:0.36, 95%信頼区間:0.21-0.64)、口塞ぎの割合が43%(オッズ比:0.57, 95%信頼区間:0.37-0.89)、どちらかの乳児虐待は52%(オッズ比:0.48, 95%信頼区間:0.33-0.69)、低かった。
結論:乳児の泣きおよび解剖学的なメカニズムに基づく揺さぶりおよび口塞ぎの危険性に関する教育的ビデオは産後4ヶ月時における自己申告の揺さぶりおよび口塞ぎを半減させる可能性が示唆された。
-
Miura R, Tani Y, Fujiwara T*, Kawachi I, Hanazato M, Kim Y. Multilevel analysis of the impact of neighborhood environment on postpartum depressive symptoms. J Affect Disord. 2020 Feb 15;263:593-597.
日本語アブストラクト
「近所の環境が産後うつ症状に与える影響に関するマルチレベル分析」
【背景】日本では10人に1人の母親が産後うつを経験します。うつの個人的、社会的なリスクファクターについては報告されてきましたが、近所の環境に関する研究は少ないのが現状です。そこで本研究では、日本人女性における近所の環境と産後うつの関連について調べました。
【方法】2012年に名古屋市で3,4か月健診の際に実施した母親を対象とした質問紙調査のデータを用いました。産後うつ症状は、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)で評価しました。近所の環境は、地理情報システムに基づき、産後の母親が日常的に訪れるスーパー、コミュニティセンター、遊び場の小学校区ごとの数で評価しました。データの階層構造を考慮して、有効回答の得られた2298名を338の小学校区にネストし、マルチレベル分析を行いました。
【結果】母親の年齢などの個別要因で調整し、遊び場の多い小学校区に住んでいる母親の方が、EPDSが低い、つまり産後うつになりにくいという関連がみられました(回帰係数: -0.12、95%信頼区間: -0.24, -0.01)。遊び場以外の環境要因で調整した後も同様の関連がみられました(回帰係数: -0.14、95%信頼区間: -0.27, -0.02)。
【結論】これらの結果は、近所に遊び場があることが産後うつに予防的な効果があることを示唆しました。
-
Tani Y*, Fujiwara T, Kondo K. Association between adverse childhood experiences and dementia in older Japanese adults. JAMA Netw Open. 2020 Feb 5;3(2):e1920740.
日本語アブストラクト
「日本人高齢者における子ども期の逆境体験と認知症との関連」
【重要性】
日本における認知症の有病率は増加傾向にある。子ども期の貧困は認知障害のリスク上昇と関連しており、おそらく個人の教育歴が介在している。しかし、貧困や教育以外の子ども期の逆境体験と認知症との関連は十分に報告されていない。
【目的】
第二次世界大戦中および戦後に育った1948年以前に生まれた日本人において、子ども期の逆境体験(ACE)と認知症発症との関連を検討すること。
【デザイン、セッティング、参加者】
参加者 65歳以上の成人を対象とした集団ベースのコホート研究である日本老年学的評価研究の参加者17 412人を対象に、3年間(2013~2016年)の追跡調査を実施した。データは2019年12月に解析した。
【主なアウトカムと測定方法】
認知症発症は公的介護保険制度を通じて評価した。18歳以前のACEはベースライン時の調査により評価した。親の死亡、親の離婚、親の精神疾患、家庭内暴力、身体的虐待、心理的ネグレクト、心理的虐待の7つのACEを評価した。参加者は、ACEが0、1、2、3以上のいずれであったかによって分類された。Cox回帰モデルを用いて認知症リスクのハザード比を推定した。
【結果】
参加者17412人(女性9281人[53.3%];平均[SD]年齢、73.5[6.0]歳)のうち、平均追跡期間3.2年(範囲、2.4~3.3年)の間に703人(男性312人、女性391人)に認知症が発生した。全参加者のうち、6804人(39.1%)が75歳以上であった。10968人(63.0%)がACEを0回、5129人(29.5%)がACEを1回、964人(5.5%)がACEを2回、351人(2.0%)がACEを3回以上報告した。年齢、性別、子ども期の経済的困難、栄養環境、教育を調整した結果、ACEが3回以上ある参加者は、そうでない参加者に比べて認知症発症リスクが高かった(ハザード比、2.18;95%CI、1.42-3.35)。高齢期現在の社会人口統計学的特性、社会的関係、健康行動、健康状態について調整した後も、このハザード比は減少したが、統計的に有意であった(1.78;95%CI、1.15-2.75;P = 0.009)。
【結論と関連性】
本研究は、日本人高齢者において、3つ以上のACEが認知症リスクの増加と関連していることを明らかにした。 -
Yamaoka Y, Fujiwara T*, Fujino Y, Matsuda S, Fushimi K. Incidence and age distribution of hospitalized presumptive and possible abusive head trauma of children under 12 months old in Japan. J Epidemiol. 2020 Feb 5;30(2):91-97.
日本語アブストラクト
「日本における虐待による頭部外傷(AHT)の入院発生率と月齢分布」
【背景】乳幼児の致死的な虐待の多くは虐待による頭部外傷(AHT)である。しかし、日本におけるAHTの入院症例の発生率は報告されていない。本研究では12ヶ月未満乳児の頭蓋内損傷による入院症例の発生率と月齢分布について調べることを目的とした。
【方法】包括医療費支払い制度(DPC)のデータを用いて、2010〜2013年に36ヶ月未満の頭蓋内損傷にて入院した症例を調べた。米疾病管理センター(CDC)が推奨する疾病分類コード(ICD10)におけるコードの組み合わせにより、「確定的なAHT」と「AHTの可能性あり」を定義した。
【結果】2010〜2013年におけるAHTの発生率は、年間10万人乳児あたり「確定的なAHT」 が7.2人(95% 信頼区間: 7.18-7.26)、「AHTの可能性あり」が41.7人(95%信頼区間: 41.7-41.8) であった。月齢分布は、「確定的なAHT」と「AHTの可能性あり」のどちらでも、2ヶ月と8ヶ月にピークを認めた。
【結論】本研究は、国内におけるDPCデータを用いて、「確定的なAHT」と「AHTの可能性あり」の入院症例における発生率を報告した初めての研究である。特にリスクの高い月齢における予防的介入の効果評価を行うために、このデータを用いたさらなる研究が必要である。
-
Kizuki M*, Fujiwara T, Shinozaki T. Adverse childhood experiences and bullying behaviours at work among workers in Japan. Occup Environ Med. 2020 Jan;77(1):9-14.
日本語アブストラクト
「日本の労働者における子ども期の逆境体験と職場でのいじめ行動」
【目的】
日本人労働者における、子ども期の逆境体験(ACE)と職場でのいじめ被害および部下に対するいじめ行動との関係を検討すること。
【方法】
過去3年間に部下に向けられたいじめ行為が0、1、2種類以上であった労働者を対象に、インターネットを利用した横断調査を実施した(各群309名、合計N=927)。部下へのいじめ行為数に対するACEの全体効果および統制された直接効果は、それぞれベースライン調整およびmarginal structural model (MSM)から推定した。
【結果】
性別、年齢、幼少期の社会経済的地位で調整した結果、ACEのレベルと職場でのいじめ被害の頻度、職場で行われたいじめ行為の数との間には正の用量反応関係が認められた(いずれもp<0.001)。ACEの3分位が最も高い労働者は、最も低い労働者と比較して、職場でより多くのいじめ行為を行うリスクが3.15倍(95%信頼区間2.20~4.50倍)高かった。その影響の大きさは、直接効果のMSMにおいて、職場でのいじめ被害によって媒介されない経路を介して2.57(95%CI 1.70~3.90)であった。
【結論】
ACEを有する人は、後年、職場でいじめ行為を行うリスクが高かった。今回の知見は、職場でのいじめ行動を予防するために有用であろう。 -
Isumi A*, Fujiwara T, Kato H, Tsuji T, Takagi D, Kondo N, Kondo K. Assessment of additional medical costs among older adults in Japan with a history of childhood maltreatment. JAMA Netw Open. 2020 Jan 3;3(1):e1918681.
日本語アブストラクト
「子ども期の虐待歴のある高齢者は医療費がより高くかかるか?」
【背景」
子ども期の虐待は生涯を通じて健康に重大な影響を及ぼす可能性があるが、その後の人生における医療費との関連はあまり知られていない。
【目的】
日本の高齢者において、子ども期の虐待歴が追加の医療費と関連するかどうかを評価すること。
【方法】
この集団ベースの横断研究は、日本老年学的評価研究(Japan Gerontological Evaluation Study, 2013)に参加した1市町村の2012年4月から2014年3月までの国民健康保険請求データとリンクしたデータを用いた。この自治体には150万人以上の住民がおり、65~75歳の自立した978人が解析の対象となった。データは2017年10月から2019年2月までに解析された。
曝露: 身体的虐待、心理的ネグレクト、心理的虐待、親密なパートナーからの暴力の目撃を含む子ども期のマルトリートメント。
主なアウトカムと指標: 2012年4月~2013年3月および2013年4月~2014年3月の年間平均医療費。
【結果】
978人の自立した高齢者(平均[SD]年齢、70.6[2.9]歳;426人[43.6%]男性)のうち、44人(4.5%)が子ども期に親密なパートナーからの暴力を目撃し、19人(1.9%)が身体的虐待を受け、104人(10.6%)が精神的にネグレクトされ、56人(5.7%)が心理的虐待を受けていた。合計176人の高齢者(18.0%)が少なくとも1種類の子ども期の虐待を経験していた。子ども期に何らかの虐待を経験した人の平均年間医療費は、そうでない人に比べて有意に高かった(差:136 456円[1255米ドル];95%CI、38 155円-234 757円[351-2160米ドル];P = 0.007)。心理的ネグレクトを経験した人は、そうでない人よりも平均医療費が高かった(差:161 400円[1484米ドル];95%CI、42 779-280 021円[394-2576米ドル];P = 0.008)。子ども期の虐待と医療費との関連は、年齢と性別でコントロールした後も有意であった(平均限界効果:116 098円[1068米ドル];SE、53 620円[493米ドル];95%CI、11 004円-221 192円[101-2034米ドル];P = 0.03)。子ども期の虐待に関連する追加的な費用は、全国で年間3,330億円(310万米ドル)以上になると推定された。
【結論】
本研究において、日本在住の高齢者において、子ども期の虐待は医療費がより高くかかることと関連していた。この所見は、子ども期の虐待の一次予防および二次予防の重要性を強調するものである。




