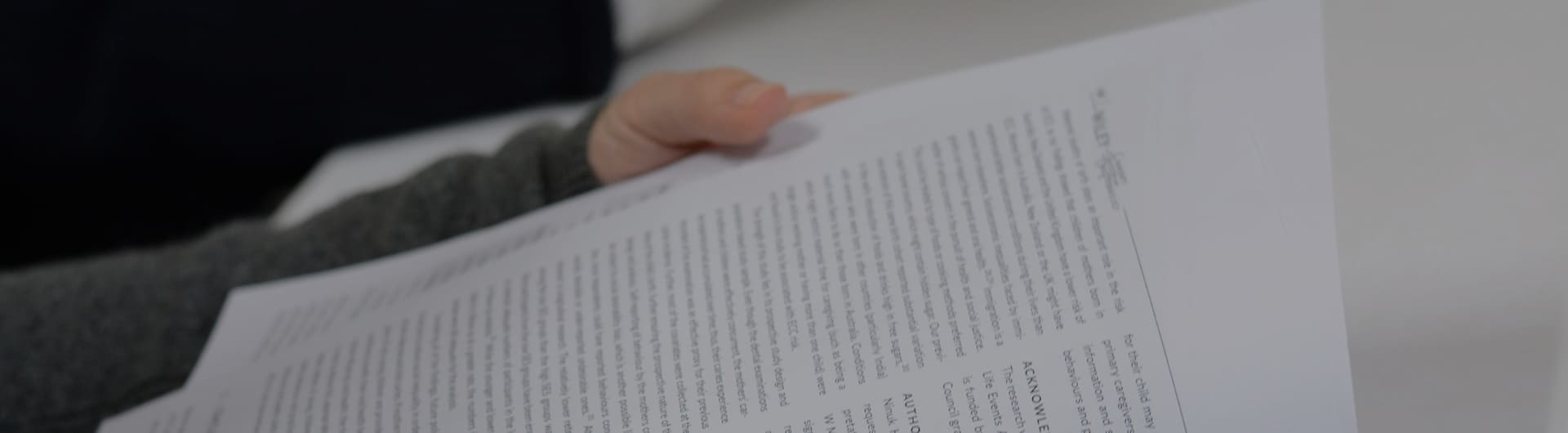
研究業績Publication
in press
-
Maeda Y, Morita A, Nawa N, Yamaoka Y, Fujiwara T. The Risk of Self-stigma and Discrimination for Healthcare Workers in Developing Countries during COVID-19 pandemic: International multisite study. Stigma and Health. (in press)
日本語アブストラクト
「COVID-19パンデミック中における途上国の医療従事者のセルフスティグマと差別に関する国際比較:国際多施設共同研究」
【目的】
本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック中に、発展途上国と先進国の医療従事者とその家族に対するセルフスティグマと差別の有病率を比較することである。
【方法】
2020年8月から10月にかけて、ブラジル(n=55)、ガーナ(n=61)、インド(n=99)、メキシコ(n=27)、ミャンマー(n=35)、日本(n=55)の医療従事者を対象とし、スノーボール・サンプリングを用いて参加者を募った。
医療従事者とその家族におけるセルフスティグマと差別経験を測定するために、3項目の質問を含むオンライン質問票を用いた横断研究を行った。多変量ポアソン回帰モデルを適用し、年齢、性別、職業、都道府県のCOVID-19患者数、心理的苦痛(Kessler-6スコア≧13と定義)を調整した上で、日本を対照群として6カ国間のセルフスティグマ、及び医療従事者とその家族に対する差別の頻度を比較した。
【結果】
6カ国より合計336件の回答が得られた。全体では、セルフスティグマを経験した医療従事者の割合は69.9%(235/336人)、差別を経験した医療従事者の割合は38.7%(130/336人)、差別を経験した医療従事者の家族の割合は14.3%(48/336人)であった。日本と比較して、インドとミャンマーは医療従事者とその家族に対するセルフスティグマと差別の有病率が有意に高かった。また、ブラジルとガーナは医療従事者に対する差別の有病率が有意に高く、メキシコはセルフスティグマの有病率が有意に高かった。
【結論】
医療従事者とその家族に対するセルフスティグマと差別の有病率は、COVID-19パンデミック期間中、日本よりも発展途上国で高かった。パンデミック時の医療従事者の健康と安全を確保するためには、医療従事者に対するスティグマと差別を防止するための対策を実施する必要がある。



