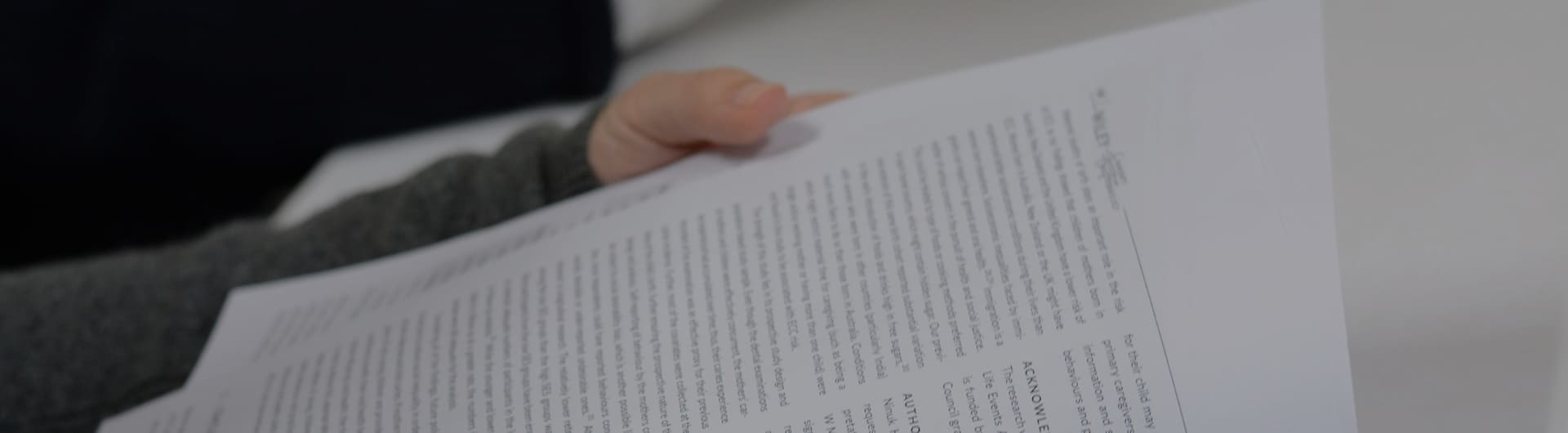
研究業績Publication
2025
-
Maeda Y, Tabuchi T, Fujiwara T*. Menstruation-Related Diseases, Work Performance, and Oral Contraceptive: Nationwide Online survey. J Occup Environ Med. 2025 Dec 1;67(12):1014-1019.
日本語アブストラクト
「月経関連疾患と経口避妊薬がワークパフォーマンスに与える影響:全国オンライン調査」
【目的】
本研究の目的は、月経前症候群(PMS)、月経前不快気分障害(PMDD)、および月経困難症などの月経関連疾患がワークパフォーマンスに与える影響を比較検討することである。あわせて、一般人口において経口避妊薬がこれらの悪影響を軽減するかどうかを調査した。
【方法】
日本で実施された全国規模のオンライン調査のデータ(n = 4,818)を分析した。回帰分析を用いて、月経関連疾患とプレゼンティーイズム(出勤時の生産性低下)またはアブセンティーイズム(欠勤)との関連、および経口避妊薬による軽減効果を検討しました。また、重度の労働機能障害に対する人口寄与危険割合(PAF)をモデルに基づいて算出した。
【結果】
PMDD(月経前不快気分障害)が、プレゼンティーイズムおよびアブセンティーイズムのリスクを最も顕著に高めることが示された。PMSとPMDDによる重度の労働機能障害に対するPAF(PMSやPMDDがなければ防げたであろう障害の割合)は有意であり、合計で約15%に達した。また、経口避妊薬は、PMDDを抱える女性においてのみ、プレゼンティーイズムを有意に軽減することが明らかになった。
【結論】
PMSおよびPMDDは、月経困難症よりも深刻にワークパフォーマンスを阻害する。経口避妊薬は、PMDDを持つ女性のワークパフォーマンスに対する悪影響を緩和する効果があることが示された。 -
Khin YP*, Kimura S, Shibata S, Nawa N, Fujiwara T. Association between the frequency of treating foreign patients and the cultural competency of Japanese healthcare professionals: a mixed-method study. Trop Med Health. 2025 Nov 24;53(1):171.
日本語アブストラクト
「外国人患者の診療頻度と、日本の医療従事者の文化的適応能力との関係:混合研究法による研究」
【背景】
これまでの研究では、外国人患者とのか関わりが、日本の医療従事者(J-HCPs)の高い文化的コンピテンス(文化への理解や対応力)と関係があるとされてきました。しかし、文化的コンピテンスをつくる個別要素に焦点を当てた研究はほとんどありませんでした。この研究では、外国人患者を診療する頻度が、文化的コンピテンスの構成要素とどのように関係しているかを、量的調査と質的調査を合わせた方法で調べました。
【方法】
量的調査では、インターネット調査で日本の医療従事者1089人からデータを集めました。文化的コンピテンスは「医療者のための異文化対応能力評価尺度(J-CCCHP)」を用い、「動機・好奇心」「感情・共感」「態度」「技能」の下位尺度で評価しました。また、外国人患者への対応研修への参加の有無で層別化しました。
質的調査では、スノーボールサンプリングにより16人にインタビューを行いました。
【結果】
週に数回外国人患者を診療する医療従事者(203人、18.6%)は、ほとんど診療していない医療従事者と比べて、「態度」の得点が低く(係数 −0.67、95%CI −1.28 ~ −0.06)、逆に「技能」の得点は高い(係数 1.36、95%CI 0.43 ~ 2.29)ことがわかりました。
また、年に数回程度外国人患者を診療する医療従事者はは「動機・好奇心」の得点も高い傾向がありました。
質的調査では、外国人患者の対応で得られる達成感や知識の向上が、「動機・好奇心」や「技能」を高めることが示されました。一方で、追加の業務負担、言語や文化の違い、リソース不足、組織的な支援不足などが、「態度」の得点をを低下させる可能性があります。
【結論】
外国人患者の診療は、日本の医療従事者にとって「動機」や「技能」を高める一方で、制度的な問題により「態度」には悪い影響が出る可能性があります。
信頼性の高い通訳サービスの提供、実践的な文化的コンピテンス研修、組織的な支援体制のの強化が、これらの課題の軽減に寄与する可能性があります。 -
Nomura T, Tani Y, Tabuchi T, Fujiwara T*. Associations between adverse childhood experiences and cosmetic surgery: effect modification by sexual orientation. Aesthetic Plast Surg. 2025 Oct 31. doi: 10.1007/s00266-025-05355-0. Online ahead of print.
日本語アブストラクト
「 子ども期の逆境体験と美容外科手術との関連:性的指向による修飾効果」
【背景】
子ども期の逆境体験(Adverse Childhood Experiences:ACEs)が美容外科手術の受療に及ぼす影響を検討した研究はほとんどない。また、その関連は性的指向によって異なる可能性がある。本研究の目的は、ACEsと美容外科手術との関連を明らかにし、さらに性的指向による修飾効果を検討することであった。
【方法】
本研究では、2023年に実施された「Japan COVID-19 and Society Internet Survey(JACSIS)」の18~79歳の参加者27,824人を対象とした。参加者は、ACEs、美容外科手術の経験、および社会人口学的特徴について回答した。多変量ロジスティック回帰分析を用いて、ACEsと美容外科手術との関連を検討し、さらに性的指向との交互作用を含めて解析を行った。
【結果】
社会人口学的特徴を調整した後、4つ以上のACEsを有する者は美容外科手術を受ける可能性が2.97倍高かった(95%信頼区間[CI]:2.51–3.51)。この関連は非異性愛者男性においてより強く認められた(オッズ比[OR]:14.60、95%CI:8.49–25.11)。また、4つ以上のACEsを有する参加者は、美容外科手術の結果に不満を抱く可能性も高かった(OR:1.92、95%CI:1.36–2.71)。
【結論】
4つ以上のACEsを有する者は、美容外科手術を受ける可能性が高く、特に非異性愛者男性でその傾向が顕著であった。さらに、4つ以上のACEsを有する参加者は、手術結果に不満を抱きやすい傾向がみられた。これらの知見は、美容外科における患者評価およびケアに際して、ACEsを含む心理社会的背景を考慮することの重要性を示唆している。 -
Suzuki T*, Fukui S, Yoneoka D, Aoki J, Fujiwara T. Blood Pressure After Changes in Light-to-Moderate Alcohol Consumption in Women and Men: Longitudinal Japanese Annual Check-up Analysis. JACC. 2025 Oct 22; doi:10.1016/j.jacc.2025.09.018
日本語アブストラクト
「女性と男性における軽度から中等度の飲酒量変化後の血圧変化:日本人年次健診縦断解析」
【背景】
飲酒は血圧上昇の既知の要因であるが、軽度から中等度の飲酒(女性で1日1杯以下、男性で1日2杯以下)の変化、特に飲酒中止と血圧との関連は不明である。本研究では、飲酒の中止・開始と血圧変化の関連を、性別、軽度から中等度の摂取量、アルコール飲料の種類に焦点を当てて評価することを目的とした。
【方法】
2012年10月から2024年3月に日本の予防医学センターで年次健診を受けた成人のデータを解析した。連続する受診間の収縮期および拡張期血圧(SBP/DBP)の変化を評価した。アルコール摂取量は標準ドリンク(1ドリンク=エタノール10g)として自己申告された。飲酒中止・開始と血圧変化の関連は、人口統計学的要因、臨床歴、生活習慣行動で調整した一般化推定方程式を用いて評価した。
【結果】
58,943名の参加者から359,717回の受診データを解析した。飲酒中止コホート(53,156回受診、25,621名、女性52.1%、年齢中央値50.5歳)では、飲酒中止は用量依存的な血圧低下と関連していた。女性では、0.5-1.0杯/日の中止でSBPは有意な変化なし(-0.44 mmHg、95%CI: -0.93~0.06)、DBPは-0.41(-0.77~-0.05)mmHg低下、1.0-2.0杯/日の中止でSBPは-0.78(-1.53~-0.04)mmHg、DBPは-1.14(-1.68~-0.61)mmHg低下した。男性では、0.5-1.0杯/日の中止でSBP(-0.27 mmHg、-0.81~0.27)およびDBP(-0.39 mmHg、-0.77~0.01)は有意な変化なし、1.0-2.0杯/日の中止でSBPは-1.03(-1.70~-0.35)mmHg、DBPは-1.62(-2.11~-1.12)mmHg低下した。飲酒開始コホート(128,552回受診、31,532名、女性70.4%、年齢中央値50.0歳)では、飲酒開始後に用量依存的な血圧上昇が認められ、その効果は男女で一貫していた。飲料別の解析では、両コホートでアルコールの種類に関わらず同様の血圧への効果が示された。
【結論】
少量飲酒でも血圧上昇と関連し、飲酒中止は男女ともに血圧低下と関連していた。これらの知見は、軽度から中等度の飲酒者においても、血圧管理のための広く適用可能な戦略として飲酒中止が有効であることを示唆している。 -
Ivanich E, Nawa N, Goto A, Fujiwara T*, Surkan PJ. Bonding Impairment as an Explanatory Link between Unplanned Pregnancy and Maternal Infant Abuse: Results of a Causal Mediation Analysis. JMA J. 2025 Oct 15; 8(4):1124-1131.
-
Yokoyama I*, Takaku R, Tabuchi T, and Fujiwara T. The Unexpected Side Effects of Lockdowns on Those “Barely” Inside and Outside of Lockdown Areas. the Oxford Bulletin of Economics & Statistics. 2025 Sep 15; doi:10.1111/obes.70016
-
Katagiri A, Iijima Y, Tanaka Y, Ohyama H, Nakazawa T, Hakariya H. Japan’s emerging role in bridging immunisation gap and supporting global health. BMJ Glob Health. 2025 Sep 14;10(9):e020316.
日本語アブストラクト
「予防接種格差の解消とグローバルヘルス支援における日本の果たすべき役割」
アメリカが2025年に米国際開発庁(USAID)およびGaviワクチンアライアンスへの資金凍結を突如発表したことは、低中所得国、特にグローバル・サウスにおける定期予防接種や小児保健プログラムを脅かしている。 過去のデータは、アメリカのグローバルヘルス支援が5歳未満児死亡率を大幅に減少させたことを示していて、資金凍結がもたらす潜在的な悪影響を浮き彫りにしている。イギリス、フランス、ドイツを含む他の主要ドナー国も、防衛や財政制約といった国内優先事項を理由に援助を縮小している。 日本は、ナショナリズムの高まりや対外援助への国内懐疑論がある一方で、Gaviワクチンアライアンスのアフリカにおけるワクチン製造アクセラレータ(AVMA)への多額の拠出を含む新たな公約を通じ、グローバルヘルス分野におけるリーダーシップを改めて示している。日本が長年培ってきた母子保健分野の専門性、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)推進活動、UHCナレッジハブなどの最近の取り組みは、現代の予測不可能な国際情勢下において、資金不足を補い、低中所得国の持続可能な保健システムを支援しうる。 -
Terada S, Maeda Y, Surkan PJ, Fujiwara T*. Associations between low birth weight, childhood adversity, and natural disaster with delay discounting among children. J Dev Orig Health Dis. 2025 Sep 2;16:e32.
日本語アブストラクト
「低出生体重、小児期逆境体験、および自然災害と子どもの遅延割引との関連」
【背景】
DOHaD仮説によると、2500g未満で生まれた子ども(低出生体重児)は、胎内での栄養不足を補うために追加の資源を求めるようにプログラムされていると考えられています。しかし、この考え方が「delay discounting(遅延割引)」と呼ばれる行動特性と関連しているかは、これまで研究されてきませんでした。遅延割引とは、「多いけれど時間を待たないと得られない報酬」に比べて「少しだけど今すぐに得られる報酬」選ぶ傾向を指します。さらに、出生後の要因として、小児期逆境体験(ACEs)や自然災害の体験も遅延割引に影響する可能性があります。
【目的】
本研究では、低出生体重、ACEs、そして自然災害の体験と遅延割引の関連を明らかにすることを目的としました。
【方法】
本研究は、2011年の東日本大震災の被災地域から167人の子どもを対象とした前向きコホート研究です。出生体重および震災前後のACEsは、2012年に実施した保護者への質問票で把握しました。震災中のトラウマ体験については、小児精神科医または心理士による半構造化面接で評価しました。2014年には、子ども(平均年齢8.3歳)を対象に、コインを使った実験で遅延割引を測定しました。子どもたちは最初に5枚のコインを持ち、「すぐにもらえるお菓子(コイン1枚あたり1個)」と「1か月後にもらえるお菓子(コイン1枚当たり2個)」のどちらに振り分けるかを選びました。従属変数は、今すぐに使うコインの数で、Poisson回帰を用いて各要因との関連を推定しました。
【結果】
低出生体重の子どもは、今すぐの報酬にコインを振り分ける数が0.68倍(95%信頼区間: 0.46–1.00)低い傾向がみられました。また、震災前に3つ以上のACEsを経験していた子どもも、即時報酬を選ぶ割合が低く(IRR: 0.58, 95% CI: 0.37–0.91)、より遅延報酬を選ぶ傾向がありました。一方で、震災後のACEsや震災中のトラウマ体験とは関連がみられませんでした。
【結論】
低出生体重や震災前に複数のACEsを経験した子どもは、遅延割引が低い(=待つことができる)傾向を示しました。これは、より多くの資源を得るための適応的な戦略が発達している可能性を示唆しています。 -
Maeda Y, Morita A, Nawa N, Yamaoka Y, Fujiwara T*. The Risk of Self-stigma and Discrimination for Healthcare Workers in Developing Countries during COVID-19 pandemic: International multisite study. Stigma and Health. 2025 Aug;10(3):369-375.
日本語アブストラクト
「COVID-19パンデミック中における途上国の医療従事者のセルフスティグマと差別に関する国際比較:国際多施設共同研究」
【目的】
本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック中に、発展途上国と先進国の医療従事者とその家族に対するセルフスティグマと差別の有病率を比較することである。
【方法】
2020年8月から10月にかけて、ブラジル(n=55)、ガーナ(n=61)、インド(n=99)、メキシコ(n=27)、ミャンマー(n=35)、日本(n=55)の医療従事者を対象とし、スノーボール・サンプリングを用いて参加者を募った。
医療従事者とその家族におけるセルフスティグマと差別経験を測定するために、3項目の質問を含むオンライン質問票を用いた横断研究を行った。多変量ポアソン回帰モデルを適用し、年齢、性別、職業、都道府県のCOVID-19患者数、心理的苦痛(Kessler-6スコア≧13と定義)を調整した上で、日本を対照群として6カ国間のセルフスティグマ、及び医療従事者とその家族に対する差別の頻度を比較した。
【結果】
6カ国より合計336件の回答が得られた。全体では、セルフスティグマを経験した医療従事者の割合は69.9%(235/336人)、差別を経験した医療従事者の割合は38.7%(130/336人)、差別を経験した医療従事者の家族の割合は14.3%(48/336人)であった。日本と比較して、インドとミャンマーは医療従事者とその家族に対するセルフスティグマと差別の有病率が有意に高かった。また、ブラジルとガーナは医療従事者に対する差別の有病率が有意に高く、メキシコはセルフスティグマの有病率が有意に高かった。
【結論】
医療従事者とその家族に対するセルフスティグマと差別の有病率は、COVID-19パンデミック期間中、日本よりも発展途上国で高かった。パンデミック時の医療従事者の健康と安全を確保するためには、医療従事者に対するスティグマと差別を防止するための対策を実施する必要がある。 -
Katagiri A, Tokuda Y*, Barnett P.B., Tanigchi K, Shibuya K, Tabuchi T. A Cross-Sectional Study on Mental Health and Quality of Life Among LGBTQ+ individuals in Japan. Journal of Gay & Lesbian Mental Health. 2025 Aug 26; doi.org/10.1080/19359705.2025.2494008
日本語アブストラクト
「日本におけるLGBTQ+当事者のメンタルヘルスと生活の質に関する横断研究」
【背景】
欧米諸国の研究では、LGBTQ+当事者がメンタルヘルス上の課題に直面していることが報告されている。しかし、日本における大規模な報告はまだされていない。
【目的】
本研究は、LGBTQ+当事者のメンタルヘルス上の課題を検討することを目的とした。
【方法】
JACSIS2022年調査を用いて、参加者31,301人の性自認・性的指向をシスジェンダー・ヘテロセクシュアル、ゲイ自認、レズビアン自認、バイセクシュアル自認、クエスチョニング、トランスジェンダー・ノンバイナリーに分類した。LGBTQ+当事者は、全体の9.8%を占めた。LGBTQ+当事者の抑うつ、孤独感、社会的孤立、および生活の質との関連性を、シスジェンダー・ヘテロセクシュアル当事者と比較し、多変量調整回帰モデルを用いて分析した。
【結果】
すべてのLGBTQ+サブグループ当事者は抑うつと、生活の質の低下を認めた。ゲイ自認当事者とクエスチョニング当事者は、社会的孤立を経験した一方、レズビアン自認当事者はむしろシスジェンダー・ヘテロセクシャル当事者よりも社会的つながりがみられた。バイセクシュアル自認当事者、クエスチョニング当事者、トランスジェンダー・ノンバイナリー当事者は孤独感を経験した一方、ゲイ自認当事者はシスジェンダー・ヘテロセクシャル当事者よりも孤独感が少なかった。
【結論】
LGBTQ+サブグループ当事者間では、社会的孤立と孤独感が異なり、それぞれのサブグループに特化した研究と健康介入が必要である。 -
Yamaoka Y*, Ochi M, Kondo K, Kimura H, Fujiwara T. A pilot study of implementing of a home-visiting parent training program: SafeCare in Japan. Child Abuse Negl. 2025 Aug 22;169(Pt 1):107644
日本語アブストラクト
「家庭訪問型ペアトレプログラム「セーフケア」の日本における実装に関するパイロット研究」
【背景】
セーフケア(SafeCare®)は家庭内で実施するペアトレプログラムであり、親子ののより良い相互作用と家庭内の安全を促進するプログラムである。本研究はパイロット研究として、セーフケアを日本のコミュニティで実施することの実行可能性、受容性、および有効性について検討した。
【方法】
2023年3月から2024年5月にかけて、福岡市で21家族をリクルートした。対象家族は子どもとの関わりや家庭内の安全性の向上が必要である家族や、虐待やネグレクトのリスクがある家族を対象とした。
【結果】
14世帯が「親と子ども/親と乳幼児の相互交流(Parent-Child Interaction or Parent-Infant Interaction [PCI/PII])」の科目と「室内の安全」の科目を含む全プログラムを修了した。これらの世帯の平均訪問回数は13.9回(SD=2.3, range= 10-18)であった。プログラムを完了しなかった世帯では、6世帯はPCI/PII科目で平均2.8回、1世帯は安全の科目で8回の訪問を受けたが中断した。修正した短縮版家庭環境觀察評価尺度(Home Observation for Measurement of Environment Inventory)において改善が認められた(平均スコア:pre=7.9、post=10.1、p<0.001)。育児ストレスも減少した(平均スコア:pre=5.4、post=3.9、p=0.020)。
【結論】
本パイロット研究ではセーフケアが実行可能なプログラムであり、日本の地域社会で受け入れられたことを示した。また、虐待・ネグレクトのリスクがある家族に対する潜在的な効果も実証した。より大規模なサンプルを用いた実験的デザインによるセーフケアの実装と有効性を確認するために、さらなる研究が必要である。 -
Katagiri A, Li Z, Wang G, Surkan PJ, Wang X, Fujiwara T*. Maternal pre-pregnancy overweight/obesity, in-utero exposure to toxic heavy metals, and offspring age at peak height velocity: A prospective birth cohort study. Environ Res. 2025 Aug 15;279(Pt 2):121829.
日本語アブストラクト
「母親の妊娠前の過体重・肥満、子宮内における有害重金属への曝露、および児の身長発育ピーク年齢:前向き出生コホート研究」
【背景】
胎児期の重金属への曝露と子どもの思春期開始時期に関する研究は、一貫性のない結果が示されている。
【目的】
本研究ではこの関連を明らかにするとともに、重金属への曝露と既知のリスク因子との相乗的な関連性を調査した。
【方法】
アメリカ・ボストンの956組の母子を対象とした。重金属濃度(鉛、水銀、カドミウム)は、分娩後24~72時間以内に母体から採取した血液から測定した。子どもの成長スパート年齢は、経時的な身長測定データに基づく混合効果成長曲線モデルを用いて算出した。まず、母体の重金属濃度と子どもの成長スパート年齢の関連を多変量線形回帰モデルで検討した。次に、交絡因子を調整後、母体の妊娠前過体重/肥満(および人種/民族)と重金属濃度が子どもの成長スパート年齢に及ぼす相乗的な効果を推定した。
【結果】
胎児期の重金属への曝露は、子どもの成長スパート年齢の早期化とわずかに関連を示した。小児期の過体重/肥満や母体の妊娠前の過体重/肥満は子どもの成長スパート年齢の早期化と関連していた。非ヒスパニック系黒人の男児は、他の人種/民族の男児よりも成長スパート年齢が早かった。さらに、高濃度の鉛およびカドミウム曝露と母体の妊娠前過体重/肥満は、それぞれ男児のみ、女児のみにおいて成長スパート年齢と関連を示した。母体の妊娠前過体重/肥満と高濃度の鉛およびカドミウム曝露はそれぞれ男児のみ、女児のみにおいて成長スパート年齢の早期化と関連した。非ヒスパニック系黒人種/民族と高濃度の鉛や水銀曝露は男児のみにおいて成長スパート年齢の早期化と関連した。
【結論】
母体の妊娠前の過体重/肥満予防と環境有害化学物質の管理が、特に非ヒスパニック系黒人において、長期的な思春期早期化を緩和するのに役立つ可能性を示唆している。 -
Kawahara T, Nawa N, Oze I, Ikezaki H, Hara M, Kubo Y, Nagayoshi M, Ito H, Michihata N, Ibusuki R, Suzuki S, Ozaki E, Kuriki K, Takashima N, Katsuura-Kamano S, Nakatochi M, Momozawa Y, Tamura T, Fujiwara T, Matsuo K; J-MICC Study Group. Inverse association between fruit juice consumption and type 2 diabetes among individuals with high genetic risk on type 2 diabetes: the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort (J-MICC) study. Br J Nutr. 2025 Jul 28;134(2):89-96.
-
Sakakibara K, Kawahara T, Nawa N, Murakami K, Ohseto H, Takahashi I, Narita A, Obara T, Ishikuro M, Orui M, Noda A, Shinoda G, Nagaie S, Ogishima S, Sugawara J, Kure S, Kinoshita K, Hozawa A, Fuse N, Tamiya G, Bennett WL, Kuriyama S, Fujiwara T, Surkan PJ. Household income modifies the association between social capital and gestational diabetes mellitus in Japan: Results from TMM BirThree Cohort Study. J Diabetes Investig. 2025 Oct;16(10):1900-1909.
-
Adewunmi OA*, Fujiwara T, Nawa N, Khin YP, Adewunmi MC, Lawal EA. Addressing Disparities in Psychological First Aid Awareness, Training, and Practice Among First Repsonders in Nigeria. Disaster Med Public Health Prep. 2025 Jun 26;19:e165.
日本語アブストラクト
「ナイジェリアの救急隊員における心理的応急処置の認識、トレーニング、実践の格差」
【背景】
本研究は、ナイジェリアの救急隊員が緊急時の被災者に心理的応急処置(PFA)を提供しているかどうか、またどのように提供しているかを調査した。主な目的は、救急隊員の心理的応急処置に関する認識を評価し、PFAのトレーニング状況および救急治療におけるPFAの活用の程度を評価することである。
【方法】
混合研究法を用いた記述的横断調査を実施した。本研究は、ナイジェリアのラゴス州に居住する救急隊員を対象に実施された。定量的調査では386名の回答者が参加した。一方、定性的調査では、救急対応における多様な役割と経験に基づき、様々な階層の救急隊員からスノーボールサンプリング法を用いて17名の参加者を抽出した。
【結果】
本研究の結果、回答者の59.6%がPFAを認知しており、27.2%がトレーニングを受けており、38.3%がPFAを実践していることが判明した。しかし、調査結果では、教育水準によって認知度に有意な差が見られ、高等教育を受けた人は、そうでない人に比べて認知度が4.21倍高かった(オッズ比1.73~10.23)。質的調査の結果、学習環境および実践現場における手順が整備されていないため、回答者がPFAを実践する機会を得られていないことが明らかになった。
【結論】
本調査は、回答者間で心理的応急処置(PFA)の認知度とトレーニングレベルにばらつきがあることを示しており、緊急対応への備えにおける機会と課題を示している。高齢者層におけるPFAの認知度向上策を策定するとともに、新任者の応急処置者もPFAのトレーニングを受けるべきである。 -
Tani Y, Isumi A, Yamaoka Y, Fujiwara T. Reading Books Helps Children in Poverty Become More Resilient: Results from a Population-based Longitudinal Study in Japan. J Epidemiol. 2025 Jun 21. doi: 10.2188/jea.JE20240329. Online ahead of print.
日本語アブストラクト
「 読書は貧困にある子どものレジリエンスを育てる: 日本の縦断研究の結果」
【背景】
レジリエンスは、貧困による健康リスクを軽減する上で重要な力です。本研究は、小学4年生時の読書が小学6年生時のレジリエンスを高めるかどうか、さらに、貧困状態にある場合に読書による効果が異なるかどうかを検証しました。
【方法】
2018年から2020年にかけて実施された「子どもの健康・生活実態調査(A-CHILD)」における縦断データを用いました。分析には、小学4年生とその保護者を2年後まで追跡したデータ(n= 3,136、9~10歳、男子49.6%、追跡率 = 87%)を使用しました。貧困状況と小学4年生時の子どもの読書状況をベースライン時に評価しました。小学4年生時と6年生時の子どものレジリエンスは、保護者が評価しました。
【結果】
小学4年生時には、20%の子どもが全く読書をしておらず、15%の子どもが週に4冊以上の読書をしていました。小学4年生時により多くの本を読んだ子どもは、4年生のレジリエンスを調整した後でも、6年生時のレジリエンスが高くなっていました。4年生時の貧困状況は、4年生時と6年生時の両方でレジリエンスの低さと関連していましたが、貧困状況で層別化すると、貧困層の子どもにおいてのみ、読書冊数とレジリエンスの上昇との有意な関連が見られました(読書をしていなかった子どもに比べて、週に4冊以上読んでいた子どもでは6年生時のレジリエンスが5.13点高かった(95%信頼区間:1.20~9.06))。
【結論】
日本の小学生にとって、読書はレジリエンスを高め、特に貧困層の子どもにおいてその効果が顕著でした。小学生における読書に関する教育政策は、子どもの貧困対策において重要である可能性があります。 -
Goto Y, Nawa N, Nakayama T, Sato M, Satoh I, Nitta H, Okada S, Wakabayashi K, Fujiwara T*. Loneliness, but not social isolation, is a risk factor for COVID-19 vaccine hesitancy in university students in Tokyo, Japan. Sci Rep. 2025 May 21;15(1):17562.
日本語アブストラクト
「社会的孤立ではなく孤独感が、東京の大学生の COVID-19 ワクチン接種忌避のリスク要因である」
【背景】
COVID-19パンデミック下では、特に大学生において、キャンパス訪問の制限により社会的孤立が深刻な問題となった。このような社会環境は、正確な情報の不足や孤独に起因する新たな行動への不安によって、ワクチン忌避に影響を及ぼす可能性がある。
【目的】
本研究は、東京都内の大学生を対象に、社会的孤立および孤独感とCOVID-19ワクチン忌避との関連を検討することを目的とした。
【方法】
2022年3月、四大学連合(東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学、一橋大学)に所属する全学生を対象にオンライン質問票調査を実施した。質問内容には、ワクチン接種回数、社会的孤立、孤独感、メンタルヘルスなどの共変量が含まれた。ワクチン忌避者は、第3回目の接種期間中に一度も接種を受けていない者、または1回のみ接種した者と定義した。分析にはロジスティック回帰分析を用いた。
【結果】
2,907人の学生のうち、1,080人(37.2%)が社会的に孤立しており、480人(16.5%)が孤独を感じていた。また、113人(3.9%)がワクチン忌避者であった。孤独感を抱く学生は、そうでない学生と比較してワクチンを忌避する傾向が2.08倍高く(95%信頼区間: 1.25–3.44)、一方で社会的孤立はワクチン忌避との有意な関連を示さなかった(オッズ比: 1.07、95%信頼区間: 0.69–1.65)。
【結論】
東京都内の大学生において、孤独感はCOVID-19ワクチン忌避と有意に関連していたが、社会的孤立との関連は認められなかった。これらの知見は、将来のパンデミックに備えた若年層向けのワクチン接種プログラムの設計において、孤独感への配慮の重要性を示唆している。 -
Mizuno T, Nawa N, Isumi A, Doi S, Morio T, Fujiwara T*. Association between COVID-19 pandemic and school refusal among elementary school children in Japan: difference-in-differences analysis. Front Public Health. 2025 May 21;13:1466209.
日本語アブストラクト
「COVID-19パンデミックと日本の小学生における登校しぶりとの関連:差分の差分分析」
【背景】
COVID-19パンデミックが子どものメンタルヘルスに影響を及ぼしたことが報告されているが、パンデミックが登校しぶりに与えた影響については明らかになっていない。本研究では、縦断データを用いて、COVID-19流行初期と日本の小学生における登校しぶりの関連について検討した。
【方法】
「足立区の子どもの健康・生活実態調査(Adachi Child Health Impact of Living Difficulty
study, A-CHILD)」のデータを用いた。コントロール群は、COVID-19パンデミックを経験していない、2016年に小学4年生、2018年に6年生の子ども(n=449人)、COVID-19群はパンデミックを経験した、2018年に小学4年生、2020年に6年生の子ども(n=3733人)を対象として、各々のグループを追跡調査した。
【結果】
小学6年時点で登校しぶりがあった子どもの割合は、コントロール群で
3.8%、COVID-19群で 4.0% だった。小学4年から6年にかけての登校しぶりの有病率の変化は、コントロール群で2.4%、COVID-19群で 2.0%だった。差分の差分分析の結果、COVID-19パンデミックの経験は登校しぶりのリスクを高めないことが示された。この結果は傾向スコアマッチングを行っても同様だった。
【結論】
初期のCOVID-19パンデミックは、日本の小学生における登校しぶりのリスクとは関連がない可能性がある。パンデミックが登校しぶりに及ぼす影響をより明らかにするためには、長期的かつ包括的な分析が必要である。 -
山岡祐衣,井土優,森尾真由美,小江充大,福井充,近藤強,木村一絵,越智真奈美. 虐待ネグレクト予防のための家庭訪問プログラム「セーフケア(SafeCare®)」―エビデンスに基づく家庭訪問を導入・実装するには. 子どもの虐待とネグレクト (2025) 第27巻第1号 p.114-123.
日本語アブストラクト
概要:
家庭訪問プログラム「セーフケア(SafeCare®)」は、虐待ネグレクト予防を目的としたエビデンスに基づいた家庭訪問プログラムである。主に未就学児とその養育者を対象とし、子どもへの声の掛け方や関わり方に関するペアトレを行う「相互交流の科目」と室内の事故予防について学ぶ「安全の科目」があり、養育者は訪問員と一緒にペアレンティング・スキルを練習し身につけていくことを目指している。本稿では、家庭訪問プログラム「セーフケア」を自治体にて導入・実装するための段階的なプロセスとして、①プログラムの翻訳と文化的適応、②自治体との実装会議・コーディネーターの設置、③訪問員への研修と支援体制の構築をいう段階が必要であったことを報告した。今後さまざまな地域での導入・普及に向けて、対象家族への実践を増やしていきながら、ペアレンティング・スキルの向上や虐待・ネグレクトリスクの低下などプログラムそのものの効果検証に加えて、エビデンスに基づくプログラムをどのように導入・実践すると期待される効果が出るのかという、実装の仕方による効果の違いについても検証していくことが求められる。 -
Nawa N, Nishimura H, Fushimi K, Fujiwara T. Heat exposure and pediatric immune thrombocytopenia in Japan from 2011 to 2022: a nationwide space-time- stratified case-crossover study. Haematologica. 2025 May 1;110(5):1217-1220.
日本語アブストラクト
「2011年から2022年の日本における暑熱と子どもの免疫性血小板減少性紫斑病の関連:全国データを用いた時間層別化ケースクロスオーバーデザインによる検討」
【背景・目的】
子どもの免疫性血小板減少性紫斑病は、年間10万人あたり2~7人の割合で発症する血液疾患で、ウイルス感染などが発症の誘因となる可能性が示唆されていますが、環境要因についてはほとんど解明されていません。
【方法】
本研究では、2011年から2022年までの12年間において、1年で最も熱い5か月間(5月から9月)の日本全国の入院データと気象庁の気温のデータを用い、時間層別化ケースクロスオーバーデザインにより、暑熱と子どもの免疫性血小板減少性紫斑病の関連を検討しました。、また、気温曝露から影響が現れるまでの時間差(ラグ効果)を解析に考慮しました。
【結果】
高温曝露が子どもの免疫性血小板減少性紫斑病のリスクを高める可能性が示されました。特に、極端な暑熱(1日の平均気温が上位1%に該当する30.7度)にさらされた場合、入院リスクが67%増加することが分かりました(95%信頼区間: 33%~109%)。
【結論】
本研究により、高温曝露が子どもの免疫性血小板減少性紫斑病のリスクを高める可能性が示されました。本研究の結果は、気候変動が人間の健康に及ぼす悪影響をさらに裏付けるものであり、公衆衛生の観点からも気候変動への対応が求められることを示しています。 -
Tokumoto A, Jindai K, Nakaya T, Saito M, Sabel CE, Oshitani H*. Changes in the spatiotemporal patterns of COVID-19 in Japan from 2020 through 2023. J Infect Public Health. 2025 May;18(5):102704.
日本語アブストラクト
「日本におけるCOVID-19の時間的・空間的パターンの推移(2020–2023年)」
【背景】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大状況は国によって異なった。
【目的】
日本の都道府県におけるCOVID-19の感染者数・死亡者数の時間的・空間的推移を詳細に調査し、大都市圏と地方圏におけるCOVID-19の流行パターンの変化を分析することを目的とした
【方法】
全国の公開データ(2020年1月〜2023年5月)を用いて、COVID-19の地域別流行動向を分析した。都市部と非都市部の都道府県で人口当たりの罹患率・死亡率を比較した。
【結果】
流行初期はCOVID-19は都市部に集中しており、非都市部では2022年半ばまで感染・死亡ともに比較的抑制されていた。その後、非都市部でも流行が拡大し、2022年後半の第8波では非都市部での人口当たりの感染・死亡率がともに都市部を上回った。
【結論】
日本ではパンデミック初期の約2年間、特に非都市部でCOVID-19の拡大が抑制されていたが、2022年後半以降は傾向が変化した。地域差を考慮した対策の重要性や、非都市部での流行を遅らせることが、将来の感染症対策に有用であることが示唆された。 -
Kawahara T, Nawa N*, Murakami K, Tanaka T, Ohseto H, Takahashi I, Narita A, Obara T, Ishikuro M, Orui M, Noda A, Shinoda G, Nagata Y, Nagaie S, Ogishima S, Sugawara J, Kure S, Kinoshita K, Hozawa A, Fuse N, Tamiya G, Bennett WL, Taub MA, Surkan PJ, Kuriyama S, Fujiwara T. Genetic effects on gestational diabetes mellitus and their interactions with environmental factors among Japanese women. J Hum Genet. 2025 May;70(5):265-273.
-
Terada S, Nishimura H, Miyasaka N, Fujiwara T. Drops in atmospheric pressure and subsequent fluctuations in daily delivery volume: A case-crossover study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2025 May;39(4):325-333.
日本語アブストラクト
「大気圧の低下とその後の分娩数の変動: ケースクロスオーバー研究」
【背景】
分娩数の変動は、産科医の負担やバーンアウトにつながりうる。台風やハリケーンなどによる大気圧の急激な低下は、その後数日間の分娩数の増加と関連している可能性があるが、遅延効果を考慮した研究はほとんどなかった。
【目的】
大気圧の低下が、自然陣痛発来による分娩数の変動と関連しているかを明らかにすることを目的とした。
【方法】
ケースクロスオーバー研究を行った。2011年から2020年までの47都道府県の自然陣痛発来による分娩数のデータを、日本周産期登録ネットワークのデータベースから取得しました。Distributed lag non-linear modelを用いた疑似ポアソン回帰モデルで、大気圧の低下(-13.8 hPa、1パーセンタイルに相当)と一日当たりの分娩数の関連を、分娩前最大14日間の期間にわたって検討した。都道府県ごとの推定値をランダム効果メタアナリシスで統合した。また、妊娠週ごとの層別解析を行った。
【結果】
1,074,380件の自然陣痛による分娩を対象に解析した。自然陣痛発来による分娩のラグ累積相対リスクは、分娩前4日間の遅延効果を考慮した時に最も大きかった。特に、妊娠38週から40週において、気圧低下と分娩数の関連が強く見られた。具体的には、-13.8 hPaの気圧低下による0〜4日間のラグ累積相対リスクは、気圧変化がなかった場合と比較して、妊娠38週で1.07(95%信頼区間1.00, 1.14)、妊娠39週で1.08(95%信頼区間1.02, 1.14)、妊娠40週で1.10(95%信頼区間1.03, 1.19)だった。
【結論】
大気圧の低下は、特に妊娠38~40週において、その後数日間における自然陣痛発来による分娩数のわずかな増加と関連していた。 -
Asanbek Kyzy A*, Sulaimanova G, Kalmatov R, Mamyrova K, Abdyrasulov K, Fonken P, Bardella IJ. The Evolution and Challenges of Family Medicine in Kyrgyzstan: A Health System Analysis. Fam Med. 2025 May;57(5):349-354.
日本語アブストラクト
「キルギスにおける家庭医療の進化と課題:医療システム分析」
1991年にソビエト連邦から独立した後、キルギスは家庭医療を導入する大規模な医療改革を実施し、中央アジアにおける先駆者となった。1990年代後半から始まったこれらの改革は、家庭医療を専門分野として、また医療システムの重要な構成要素として導入することで、一次医療を強化した。このアプローチは医療の質を向上させつつ医療費を削減し、医療教育や農村医療従事者問題への取り組みを含む広範な医療制度改革へと徐々に拡大した。しかし、家庭医療をキルギスの医療教育・医療制度に完全に定着させるには、依然として課題が残されている。本稿は初期改革以降の進展を分析し、近年の動向を評価するとともに、キルギスの医療環境における家庭医療の制度化における継続的課題を探求することを目的とする。 -
Tani Y*, FujiwaraT, Yamakita M & Kondo K. Childhood sports club experiences mitigate the association between childhood socioeconomic disadvantage and functional disability in older Japanese men. Scientific Reports. 2025 Apr 24; 15:14371.
日本語アブストラクト
「子ども期のスポーツクラブ参加経験は社会経済的不利による高齢期の機能障害を緩和する」
【背景】
家事や金銭の管理、交通機関の利用といった日常生活を送る上で必要な生活機能の低下(生活機能障害)は、本人のQOLの低下や健康リスクとなるだけでなく、介護者の負担につながります。子ども期の生活環境が悪いと、その後の機能障害につながることがわかっていますが、このリスクを軽減できる要因については不明でした。我が国には部活動という課外活動があり、子どもの運動面だけでなく、心理的発達や社会的つながりを育むことに寄与している可能性がある。そこで、本研究では、子ども期にスポーツクラブに参加した経験が、子ども期の社会経済的不利による高齢期の生活機能障害リスクを緩和するかどうかを検証しました。
【方法】
2016年に実施したJAGES(Japan Gerontological Evaluation Study,日本老年学的評価研究)調査に参加した65歳以上高齢者16,095名を解析対象者としました。生活機能は、高次の生活機能評価指標である13項目からなる老研式活動能力指標で評価し、10パーセンタイル未満のスコアを生活機能障害と定義しました。子ども期の生活環境は「あなたが15歳当時の生活程度は、世間一般からみて次のどれに入ると思いますか。」という質問を用いて、上・中・下の3群に分けました。子ども期のスポーツクラブ経験は、6-12歳、13-15歳、16-18歳の3つの期間のうち、スポーツクラブに参加していた期間の合計数を算出しました。
【結果】
男性では、子ども期のスポーツ経験が0(無し)だった59.2%、1期間だった人が27.5%、2期間以上だった人が13.3%だった。女性では、子ども期のスポーツ経験が0(無し)だった75.5%、1期間だった人が17.8%、2期間以上だった人が6.6%だった。男女ともに、子ども期スポーツクラブ参加経験期間が長いほどリスクが低かった。男性では、子ども期の生活環境が低いほど、スポーツクラブ参加経験による機能障害リスク減が大きく、緩和効果が認められた。男性では子ども期の生活環境が「下」群では、スポーツクラブ参加期間が0の場合は機能障害割合が20%であったが、スポーツクラブ参加経験が2期間以上の場合は機能障害割合が6%だった。女性では、子ども期の生活環境のレベルに関わらず、2期間以上スポーツクラブに参加した経験があると機能障害リスクが40%低かった。
【結論】
子ども期のスポーツクラブ参加経験は、男女ともに高齢期における機能障害リスクの低さと関係していました。男性では、子ども期のスポーツクラブ参加経験が、子ども期の経済的不利による高齢期の機能障害リスクを緩和しました。社会経済的に恵まれない子どもたちが利用できるスポーツ環境を整えることが、その後の生活機能の向上に寄与するかもしれません。 -
Terada S, Nakayama SF, Fujiwara T. Household income, maternal allostatic load during pregnancy, and offspring with autism spectrum disorders. Autism Res. 2025 Apr;18(4):881-890.
日本語アブストラクト
「妊娠中の世帯年収と児の自閉スペクトラム症の関連、およびアロスタティック負荷の媒介効果」
【目的】
本研究は、妊娠中の世帯年収と子どもの自閉スペクトラム症(ASD)との関連を明らかにするとともに、妊娠中の慢性的な生理的ストレス負荷を示すアロスタティック負荷が、この関連にどのように関わっているかを検証することを目的とした。
【方法】
本研究はエコチル調査(子どもの健康と環境に関する全国調査)のデータを利用した。59,998組の母子を対象とし、世帯年収を3群(400万円未満、400–600万円、600万円超)に分類した。ASDの診断は4歳時点の保護者回答に基づいた。母親の自閉症特性における広域表現型(BAP)を含む交絡因子を調整し、ベイジアン・ロジスティック回帰モデルを用いて分析を行った。また、妊娠中のアロスタティック負荷が媒介するか媒介分析で検討した。
【結果】
世帯年収低群では、高群と比較して子どものASDリスクが58%(95%信用区間: 28–98%)、中群では37%(95%信用区間: 12–70%)高かった。一方、アロスタティック負荷とASDの関連は認められず、媒介効果もなかった。これらの結果は、母親のBAPやその他の交絡因子を調整した後も一貫していた。
【結論】
本研究は、妊娠中の世帯年収低群および中群が子どものASDリスク上昇と関連することを明らかにした。これらの結果は、低所得層におけるASDリスクの要因を理解し、社会的支援等の公衆衛生的介入を検討する上で重要な知見を提供する。 -
Terada S, Nishimura H, Miyasaka N, Fujiwara T. Heat Stress and Placental Abruption: A Space–Time Stratified Case‐Crossover Study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2025 Apr 10. doi: 10.1111/1471-0528.18163. Online ahead of print.
日本語アブストラクト
「暑さ指数と常位胎盤早期剝離の関連」
【背景】
近年の気候変動により、暑さが妊婦や胎児の健康に与える影響が注目されている。「常位胎盤早期剝離」という、胎盤が出産前にはがれてしまう重篤な合併症について、暑さとの関係はこれまで不明だった。
【目的】
妊娠中に強い暑さにさらされると、1週間以内に常位胎盤早期剝離が起こりやすくなるかどうかを調べることを目的とした。
【方法】
2011年から2020年の夏季(6月〜9月)に、日本全国11地域で出産した6,947件の常位胎盤早期剝離のデータを使用した。WBGT(湿球黒球温度)という、気温・湿度・日射を総合した熱ストレス指標(いわゆる暑さ指数)を用いて、その日の暑さが発症に与える影響を、最大7日間の遅延効果を考慮して解析した。分析には、ケースクロスオーバー法という統計手法を使った。
【結果】
強い暑さ(暑さ指数95パーセンタイル以上)の翌日には、常位胎盤早期剝離のリスクが23%高まることが確認された。一方で、その2日後にはリスクがやや下がる傾向も見られ、1週間全体で見るとリスクの増減が打ち消し合うような形となっていた。妊娠週数による違いは大きくなかったが、妊娠高血圧症候群や胎児発育不全がある妊婦では、暑さの翌日にさらに大きくリスクが上昇していた。
【結論】
妊娠中に強い暑さにさらされると、その翌日に常位胎盤早期剝離が起こるリスクが高まり、もともと起こるはずだった胎盤早期剥離の発症時期が暑さにより1日程度早まってしまう可能性が示唆された。とくに妊娠高血圧症や胎児発育不全がある妊婦では、暑さへの注意がより重要と考えられる。 -
Adewunmi OA*, Fujiwara T, Nawa N, Khin YP, Lawal EA. Factors Related to Current Level of Knowledge and Skills of Psychological First Aid Among Health Care Providers for Africa and the Global South: A Systematic Review. Disaster Med Public Health Prep. 2025 Apr 7;19:e85.
日本語アブストラクト
「アフリカおよびグローバル・サウスにおける医療従事者の心理的応急処置に関する現状の知識・技能水準に関連する要因:システマティック・レビュー」
【背景】
心理的応急処置(PFA)は、個人の急性危機における心理的影響を軽減するために設計された重要な介入法である。PFAは、医療従事者に即時的な心理社会的支援を提供する上で必要な技能と知識を身につけさせ、それによって長期的なメンタルヘルス問題の可能性を低減することを目的としている。本研究は、医療従事者のPFAに関する既存の知識と技能を評価するものである。
【方法】
2023年4月1日から2023年8月7日までに、PubMed、Psych INFO、Web of Science、CINAHL、Google Scholarデータベースを検索し、過去10年間に発表された医療従事者のPFAに関する知識と技能を報告した研究を抽出した。選定された研究に対して質的統合分析を実施した。
【結果】
626件の検索結果から12件が適格と判定された。心理的応急処置トレーニングの有効性は自己効力感を用いて評価された。時間の経過は、医療従事者の適切な心理社会的対応に関する理解に有意な影響を及ぼした。PFAトレーニングは医療従事者への心理的支援提供に有効である。PFAトレーニングプログラムの長期的な効果は不明である。
【結論】
本研究結果は、PFAトレーニングが医療提供者の知識と技能向上に有効であることを示しており、課題への継続的な取り組み、トレーニング手法の適応、急性危機における心理社会的支援の持続的改善の確保が求められる。 -
Morita A, Nawa N, Storey D, Underwood CR, Surkan PJ, Fujiwara T*. Associations between individual-level social capital, homophilous and heterophilous social network diversities, and climate stewardship in Japan. J Environ Manage. 2025 Mar;376:124337.
日本語アブストラクト
「日本における個人レベルの社会関係資本、同質的・異質的社会ネットワーク多様性と気候保全行動の関連」
【背景】
気候変動緩和政策に対する国民的支持を構築することは、2050年までのネットゼロという世界的目標を達成するうえで不可欠である。これまで、社会的つながりが環境保全行動と関連することは知られていたが、どのような人々とのつながりが政府の温室効果ガス削減政策の受容に影響するのかについては、十分に検討されていなかった。
【方法】
オンライン調査(n = 12,147)を実施し、社会関係資本および同質的/異質的な社会ネットワーク多様性(SND)が、政府の推奨と一致した気候保全行動とどのように関連するかを分析した。
【結果】
社会関係資本は気候保全行動全般と有意に正の関連を示した。さらに、同質的SNDは異質的SNDに比べ、全体的な気候保全行動との関連がより強かった。一方で、同質的SNDおよび異質的SNDと気候保全行動の各領域との関連は、必ずしも一貫していなかった。
【結論】
脱炭素社会に向けて気候保全行動を促進するためには、多くの共通点を持つ人々が相互に情報を共有し、協力しやすい社会的環境を整えることが重要であることが示唆された。 -
Owusu FM, Nawa N, Nishimura H, Khin YP, Doi S, Shakagori S, Isumi A, Fujiwara T*. Association of communication methods and frequency with BMI among adolescents during the COVID-19 pandemic: Findings from A-CHILD Study. Front Public Health. 2025 Feb 28:13:1433523. doi: 10.3389/fpubh.2025.1433523. eCollection 2025.
日本語アブストラクト
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック下におけるコミュニケーションスタイル・頻度とBMIの関連:足立区子どもの健康・生活実態調査(A-CHILD Study)から」
【背景・目的】
これまで、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック下におけるコミュニケーション方法とBMIの関連についての研究が不足していました。そのため、本研究では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック下において、対面およびオンラインといったコミュニケーションスタイルの違いとBMIの関連を検討することを目的としました。
【方法】
本研究は、足立区子どもの健康・生活実態調査(N=3,178)の2022年のデータを用いた横断研究です。 コミュニケーション方法を評価するために質問票を用いました。 BMIは、WHOの基準に基づき、過体重および肥満(+1SD)、正常体重(-1SD~<+1SD)、低体重(<-1SD)に分類しました。多項ロジスティック回帰分析を用いて、コミュニケーション方法とBMIの関連を検討しました。
【結果】
対面式コミュニケーションの頻度が減少すると、過体重および肥満のリスクが94%上昇していました(RRR=1.94、95%CI;1.38、2.72)。一方、オンラインコミュニケーションの頻度が増加すると、リスクが46%上昇していました(RRR=1.46、95%CI;1.10、1.95)。オンラインと対面でのコミュニケーションを同時にモデルに投入すると、対面でのコミュニケーション頻度の減少のみが、過体重および肥満のリスクの上昇と関連していました(RRR=1.56、95%CI;1.09, 2.25)。性別で層別化すると、女子では対面でのコミュニケーションの頻度の低下が過体重および肥満のリスクの上昇と関連していましたが、(RRR=2.12、95%CI;1.20, 3.73)、男子では関連は認めませんでした。
【結論】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック下において、対面でのコミュニケーションの頻度の低下は、特に女子において、過体重および肥満のリスクの上昇と関連していました。 -
Nawa N, Nishimura H, Fushimi K, Fujiwara T. Association between heat exposure and intussusception in children in Japan from 2011 to 2022. Pediatric Research. 2025 Feb 19. doi: 10.1038/s41390-025-03930-4. Online ahead of print.
日本語アブストラクト
「暑熱と子どもの腸重積症の関連」
【背景・目的】
暑熱への暴露は、食事内容や腸管蠕動の変化を含むさまざまなメカニズムにより、子どもの腸重積症のリスクを高める可能性があります。しかし、日ごとの暑熱への暴露と子どもの腸重積症の入院リスクとの関連を調査した全国的な研究はこれまで行われていませんでした。本研究は、高い気温と子どもの腸重積症との関連を検討することを目的としました。
【方法】
2011年から2022年までの5歳以下の子どもの腸重積症による入院患者数を、DPCデータベースから抽出しました。1日の平均気温は気象庁のデータを活用しました。本研究では、暑熱への曝露に焦点を当てるため、分析では最も気温の高い5か月間(5月~9月)に発生した入院について検討しました。熱への曝露による腸重積症の相対リスクを、時間層別化ケースクロスオーバー法により推定しました。
【結果】
研究期間中の腸重積症による子どもの入院患者は13,083人でした。日平均気温が高いと、腸重積症による入院リスクが高くなることが分かりました。特に、99パーセンタイルの極めて高い日平均気温にさらされると、入院リスクが39%増加することが分かりました(95%信頼区間: 5%〜83%)。
【結論】
この研究では、日平均気温が高いと子どもの腸重積症による入院リスクが増加することがわかりました。今後の研究では、高い日平均気温と子ども腸重積症による入院リスクとの関連のメカニズムを解明する必要があります。 -
Suzuki E, Nawa N, Okada E*, Akaishi Y, Kashimada A, Numasawa M, Yamaguchi K, Takada K, Yamawaki M. An action research study on the needs and perspectives of medical students and junior residents on peer physical examination guidelines to respect medical students’ autonomy and privacy in Japan. BMC Med Educ. 2025 Feb 3;25(1):174.
-
Nawa N, Nishimura H, Fushimi K, Fujiwara T. Association Between Heat Exposure and Anaphylaxis in Japan: A Time-Stratified Case-Crossover Study. Allergy. 2025 Feb 1. doi: 10.1111/all.16488. Online ahead of print.
日本語アブストラクト
「暑熱とアナフィラキシーの関連」
【背景・目的】
暑熱への曝露は、間接的(例えば、食事内容の変化、花粉レベルの上昇、または虫刺されの頻度の上昇など)または直接的(例えば、免疫反応の増強など)にアナフィラキシーのリスクを高める可能性があります。しかし、全国規模の日ごとの入院データと気象データを連結して暑熱への暴露とアナフィラキシーの関連性を検討した研究は不足していました。
【方法】
2011年から2022年までのアナフィラキシーによる入院患者数を、DPCデータベースから抽出しました。日平均気温は気象庁のデータを活用しました。
本研究では暑熱への曝露に焦点を当てているため、最も気温の高い5か月間(5月から9月)に発生した入院患者について分析を行いました。時間層別化ケースクロスオーバーデザインを用いて、暑熱への暴露とアナフィラキシーの関連性を検討しました。
【結果】
研究期間中のアナフィラキシーによる入院患者数は55,298人にのぼりました。1日の平均気温が高くなると、アナフィラキシーによる入院リスクが上昇することが確認されました。特に、99パーセンタイルに該当する極めて高い気温(30.7度)にさらされた場合、入院リスクが49%増加することが明らかになりました(95%信頼区間: 19%〜85%)。さらに、アナフィラキシーのタイプ別に解析を行った結果、高気温への曝露と入院リスクの関連性は、医療処置や治療に関連するタイプのアナフィラキシーでは認められませんでした。一方で、医療処置や治療とは無関係な食物性などのアナフィラキシーのタイプでは、この関連性が特に顕著であることが分かりました。
【結論】
気温が高いほどアナフィラキシーによる入院リスクが増加することが示されました。この関連は、食物性などのアナフィラキシーのタイプに特に顕著でした。本研究の結果は、気候変動が健康に与える悪影響の新たな証拠であり、公衆衛生の観点からも気候変動対策を急ぐ必要性を示しています。 -
Tazawa M, Nawa N, Yamauchi S, Tokunaga M, Fushimi K, Kinugasa Y, Fujiwara T*. Impact of the coronavirus disease 2019 pandemic on the number of colorectal cancer surgeries performed based on a nationwide inpatient database in Japan. Surgery Today. 2025 Feb;55(2):247-256.
日本語アブストラクト
「全国入院患者データベース(DPCデータベース)を用いて解析したCOVID-19のパンデミックが大腸がん手術件数に与えた影響」
【背景・目的】
本研究では、COVID-19の流行が日本における大腸がん手術件数に及ぼす影響を検討した。
【方法】
Diagnosis Procedure Combination(DPC)データベースより、2017年1月から2020年12月の間に大腸がん手術を受けた患者を抽出した。COVID-19発生初期の流行を3つの波に分けた。COVID-19パンデミックの各波における大腸がんの手術件数の変化をがんの病期別に層別化し、ロバスト標準誤差を用いたポアソン回帰を用いて評価した。
【結果】
結腸がん手術は、第1波では、Stage IIIの手術が6%有意に減少(RR, 0.94)し、第2-3波ではStage 0-IIの手術は4%有意に減少(RR, 0.96)し、Stage IVの手術は9%有意に増加(RR, 1.09)した。直腸がん手術は、第1波でStage 0-IIの手術は9%有意に増加(RR、1.09)し、Stage IVの手術は16%有意に減少(RR、0.84)した。
【結論】
COVID-19のパンデミック時には大腸がんの診断と治療が遅れ、通常よりも進行した段階で治療が行われたことが示唆された。さらに、流行の初期には手術件数の減少を認めた。しかし、流行が続くにつれて、恐らく医療資源が適切に配分されたためと思われるが、手術件数は徐々に通常通りに回復した。 -
Doi SK, Isumi A, Sugawara J, Maeda K, Satoh S, Mitsuda N, Fujiwara T. Social life impact for mother scale at first trimester predicts postpartum suicide risk: A prospective study. Suicide Life Threat Behav. 2025 Feb;55(1):e13157.
日本語アブストラクト
「妊娠初期のSocial life impact for mother scale(SLIM尺度)による産後の自殺リスクの予測:前向き研究」
【背景・目的】
妊産婦の死因第一は自殺であり、自殺リスクを早期に把握し、早期支援に繋げることは重要である。産科医療機関の初診時(妊娠初期)に「Social life impact for mother scale(SLIM尺度)」を実施することで、産後の自殺リスクを予測することができるかを検討した。
【方法】
日本の4つの都府県の産婦人科クリニックおよび病院で実施された病院ベースの前向き研究の一部データを使用した(N=7,462)。研究対象者は、妊娠初期に9項目のリスク要因で構成されたSLIM尺度に回答し、産後1か月時点にエジンバラ産後うつ病自己質問票(EPDS)に回答した。EPDSの項目10(自傷行為念慮)を用いて産後の自殺リスクを評価した(N=5,697)。
【結果】
産後の自殺リスクをアウトカムとしたオッズ比の結果から重み付けされたSLIM尺度合計得点は、産後の自殺リスクを中程度の精度で予測した。SLIM合計得点で6点以上を記録した妊婦は、産後の自殺リスクが4.26倍(95%CI=3.12–5.01)高いことが示された。原版のSLIM尺度得点(社会的ハイリスクをアウトカムとしたオッズ比の結果から重み付け)も、産後の自殺リスクを予測したが、本研究の新しいSLIM尺度得点は原版よりも高い精度を示した。
【結論】
妊娠初期の産科医療機関での健診でSLIM尺度を実施することで、産科医療機関が産後の自殺リスクを予測し、妊婦に対するサポートを開始するための有用なツールとなる可能性がある。産科医療機関でSLIM尺度を実施する際には、目的に応じて本研究で得られた重み付け得点または原版の重み付け得点を活用することができるだろう。 -
Mita N, Khin YP, Nawa N, Yamaoka Y, Fujiwara T. Fathers’ perceptions of factors associated with the attainment of paternity leave: A qualitative study. Frontiers in Global Women’s Health.2025 Jan 28. doi: 10.3389/fgwh.2024.1466227
日本語アブストラクト
「父親の育児休業取得に関連する要因に対する父親の認識: 質的研究」
【背景・目的】
システマティック・レビューによると、父親の関与は子どもの社会的、行動的、心理的問題の軽減に有益であると報告されている。しかし、父親の育児休業取得に関する要因を調査した研究は限られている。本研究の目的は、父親の育児休業取得に関する要因についての父親の認識を探ることである。
【方法】
父親の育児休業についての認識に関する情報を得るため、全体で21人の父親にインデプスインタビューを行った。また、父親の育児休業に対する意見を把握し、本研究の示唆が職場において適切であることを確認するため、企業の上司4名にもキーインフォーマントインタビューを実施した。データは主題分析により分析した。育児休業に関する先行研究をもとに演繹的コーディングを行い、その後、帰納的コーディングを行った。最終的なコードはエコロジカルモデルに基づき整理した。
【結果】
父親のキャリアへの関心、乳幼児や母親のサポートに対する父親のコミットメント、母親や乳幼児における父親の関与の重要性、父親の育児休業に対する同僚の見解、父親の仕事のスケジュールや責任、親族からのサポート、育児休業に関する政策やガイドライン、父親の関与にまつわる社会の動向などが、育児休業の取得に関するテーマとして挙げられた。企業の上司は、長期的な効果や組織への影響など、より広い観点から育児休業に関するテーマを挙げていた。
【結論】
本研究は、父親の育児休業取得に関する要因についての父親の認識を明らかにした。この結果は、父親が育児休業を取得しやすい環境を作るために有用な情報を提供すると考えられる。 -
Nawa N, Okada E, Akashi Y, Kashimada A, Okada H, Okuhara T, Kiuchi T, Takahashi M, Ohde S, Fukui T, Tanaka Y, Yamawaki M. Analysis of the Growth Trajectories of Junior Residents in Japan: A Longitudinal Cohort Study Utilizing Data from a Nationwide E-Portfolio System (EPOC2). BMJ Open. 2025 Jan 15;15(1):e087625.
-
Khin YP, Owusu FM, Nawa N*, Surkan PJ, Fujiwara T. Barriers and facilitators for healthcare access among immigrants in Japan: A mixed method systematic review and meta-synthesis. The Lancet Regional Health – Western Pacific. 2025 Jan 10:54:101276.
日本語アブストラクト
「日本における在留外国人の医療アクセスに関する障壁と促進要因:混合研究法を用いた系統的レビューとメタ統合」
【背景・目的】
日本では国民皆保険制度が整備されているが、在留外国人の医療アクセスには障壁がある可能性がある。さらに、在留外国人の医療アクセスに関する体系的な研究は十分ではない。本システマティックレビューでは、日本における在留外国人の医療アクセスに関する障壁と促進要因を検討することを目的としている。
【方法】
2024年1月9日までに発表された英語および日本語の文献を検索した。Levesqueのフレームワークに基づき、在留外国人の医療アクセスの各ステージに影響を及ぼす要因を評価した研究を対象とした。さらに、主題分析を行い、結果の分類を行った。
【結果】
2,791件の論文を精査した結果、量的研究40件、質的研究23件、混合研究4件の合計67件の研究が特定された。限られた医療情報により、在留外国人は代替の情報源を求めるようになり、移民の医療ニーズの認識に影響を与えた。また、滞在期間が長くなるほど、医療情報へのアクセスが改善された。文化や医療制度の違いが医療の受診に影響を与えた。過重労働、無登録の滞在、経済的困難、保険の制約により医療へのアクセスや利用が妨げられたが、家族や友人の支援はこれを促進する要因となった。医療制度は、在留外国人の言語や文化的なニーズをサポートするには不十分であることが多く、その結果、満足度やコンプライアンスの低下につながることが明らかになった。
【結論】
本研究の結果は、医療情報へのアクセス改善から在留外国人に配慮した医療制度づくりに至るまで、日本の在留外国人を支援するための多角的なアプローチの重要性を浮き彫りにしている。また、無登録の滞在者や低技能労働者としての在留外国人、子どもなど、特に脆弱な立場にある在留外国人の医療アクセスに関しては、さらなる研究が求められる。 -
Khin YP, Nawa N, Namboonsri N, Owusu FM, Miyanishi A, Shrestha S, Tshering U, Shimizu K, Sugawara J, Kaewboonchoo O, Fujiwara T. Experiences of Myanmar migrants working in healthcare-related sectors in Thailand and Japan during COVID-19: A qualitative study. Asia Pac J Public Health. 2025 Jan;37(1):170-172.
日本語アブストラクト
「COVID-19下におけるタイと日本で医療関連分野に従事するミャンマー移民の経験:質的研究」
【背景】
東アジアで最も貧しい国の一つであるミャンマーでは、特に2021年のクーデター以降、多くの市民が経済的苦境を緩和するため労働移民を選択している。ミャンマーからの低技能労働者は主にタイへ移住するが、近年では日本も人気の目的地の一つとなっている。COVID-19パンデミックは、特に医療関連分野で働く労働者たちの脆弱性をさらに悪化させた。本研究の目的は、COVID-19パンデミック下におけるタイと日本で医療関連分野に従事するミャンマー移民の経験を比較することである。
【方法】
2022年6月から2023年8月にかけて、日本在住のミャンマー人介護職員10名とタイの病院で勤務したミャンマー人通訳者13名に対し、詳細なインタビューを実施した。これらのインタビューは、テーマ分析を行う前にビルマ語およびタイ語から英語へ翻訳された。本研究はマヒドン大学および東京医科歯科大学の研究倫理委員会により承認されている。
【結果】
テーマを「以前から存在していた課題」「COVID-19によって増幅された課題」「ウェルビーイングへの影響」「支援と希望によるレジリエンス」の4つに分類した。
【結論】
COVID-19パンデミック下におけるタイと日本で医療関連分野に従事するミャンマー人移民の経験を比較した結果、彼らの経験は異なるものの、共通の対処法も存在することが明らかになった。移民に関する今後の研究では、移住プロセスの各段階を網羅することが推奨される。 -
Hanafusa M, Nawa N, Owusu F, Kondo T, Khin YP, Yamoka Y, Abe A, Fujiwara T. Do the norms of tolerance for child physical abuse modify the intergenerational transmission of physical abuse? Child Abuse Negl. 2025 Jan:159:107156.
日本語アブストラクト
「子どもへの身体的虐待を容認する地域の規範は、身体的虐待の世代間連鎖を修飾するか?」
【背景】
身体的虐待の世代間連鎖については昔からよく取り上げられていますが、それに対する地域の文脈的な修飾効果については知見が不足しています。
【目的】
子どもへの身体的虐待を容認する地域の規範が、身体的虐待の世代間連鎖を修飾するかどうかを検証しました。
【方法】
日本の3県で2016年から2018年にかけて実施された「子どもの生活実態調査」(小学5年生と8年生)のデータを分析しました。33地域(43,534人)ごとの、養育者が子どもに身体的虐待を行う割合を、子どもへの身体的虐待を容認する地域の規範の近似値として利用しました。養育者の小児期の身体的虐待(被害)と、子どもへの身体的虐待(加害)については、質問紙で評価しました。父親(4,334人)と母親(38,290人)は層別化し、子どもへの身体的虐待における、養育者が小児期に身体的虐待を受けた経験と、子どもの身体的虐待を容認する地域の規範との交互作用を調べるために、マルチレベル分析を行いました。
【結果】
地域別では、身体的虐待を行った養育者の割合は平均14.4%でした。父親、母親ともに、身体的虐待の世代間連鎖が確認されました。また、子どもへの身体的虐待を報告した割合が高い地域(つまり、子どもへの身体的虐待に寛容と思われる地域)に住む父親では、身体的虐待の世代間連鎖の確率が高まりましたが、母親では同じような傾向は見られませんでした (交互作用項 p値: 父親0.06, 母親0.29)。
【結論】
子どもへの身体的虐待を容認する地域の規範は、父親において、身体的虐待の世代間連鎖の確率を高めていました。身体的虐待の世代間連鎖を断ち切るためには、地域全体で身体的虐待に対する意識を高め、容認規範を厳しく否定するような取り組みが有用である可能性が示唆されました。 -
Okamoto T, Hanafusa M, Abe T, Shimamura T, Ito M, Wakai Y, Jinta T, Higa K, Kondoh Y, Okouchi Y, Okuda R, Bando M, Suda T, Tomioka H, Fujiwara T, Takase M, Yoshihara S, Odajima H, Miyazaki Y*. Estimated prevalence and incidence of hypersensitivity pneumonitis in Japan. Allergol Int. 2025 Jan;74(1):66-71.
-
Khin YP, Nawa N, Yamaoka Y, Owusu F, Abe, A, Fujiwara T. Association between elementary and middle school children with mixed/foreign roots and influenza vaccination in Japan. Pediatr Int. 2025 Jan-Dec;67(1):e15851.
日本語アブストラクト
「日本における小中学生の外国籍・混合世帯/とインフルエンザワクチン接種との関連」
【背景・目的】
日本では外国籍の親を持つ子どもの数が増加しているが、毎年任意で自己負担により接種することが推奨されているインフルエンザワクチンの接種率が低い可能性がある。さらに、社会経済的地位は任意接種の効果修飾因子の一つである可能性がある。本研究では、日本における混合(両親のどちらかが外国籍)/外国ルーツ(両親が外国籍)の小中学生とインフルエンザワクチン接種との関連を、世帯収入と母親の学歴で層別化して調査を行った。
【方法】
2016年から2019年の首都圏8都市のデータを統合し、小中学生とその保護者16,368人を対象とした。 保護者は、昨年度に子どもがインフルエンザワクチン接種を受けたかどうか、および外国籍であるかどうかについて回答した。 マルチレベルポアソン回帰分析を適用し、さらに所得状況と母親の学歴によって層別化して解析を行った。
【結果】
391人(2.4%)の子どもが混合世帯、91人(0.6%)が外国籍であった。日本人の子どもと比較すると、混合世帯の子どもおよび外国籍の子どもはインフルエンザワクチンの接種率が低いことが分かった。層別化後、外国籍・混合世帯の子どもは、高所得および母親が高学歴の家庭においてのみ、日本人の子どもよりもインフルエンザワクチンの接種率が低いことが分かった。
【結論】
特に高所得および母親が高学歴の家庭において、日本人の子どもよりも混合世帯の子どもおよび外国籍の子どもはインフルエンザワクチンの接種率が低いことが分かった。




