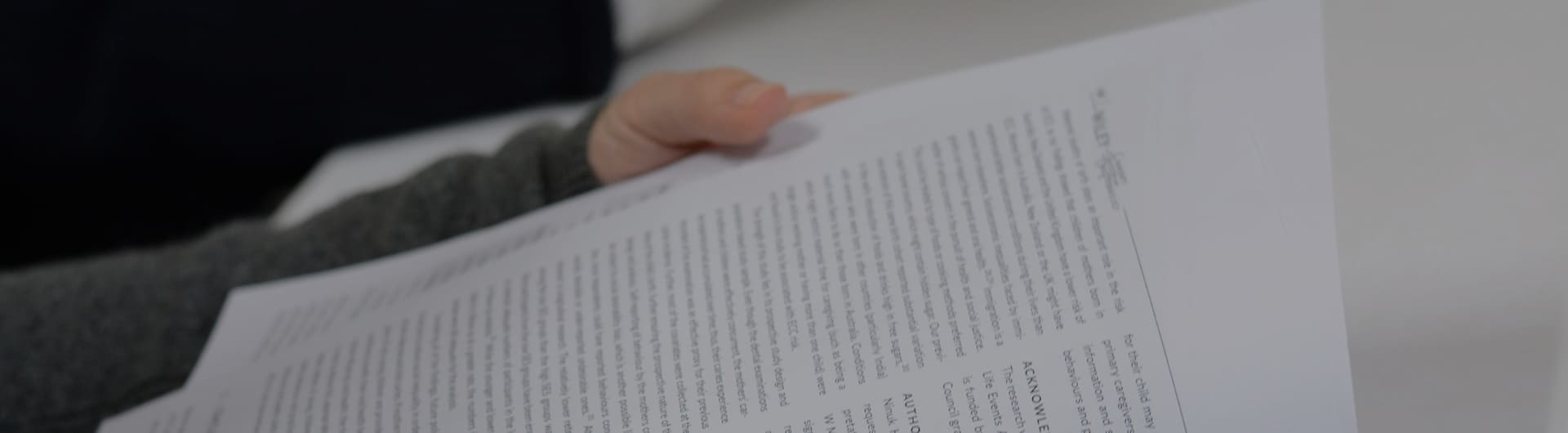
研究業績Publication
2021
-
Mikami R, Mizutani K, Matsuyama Y, Matsuura T, Kido D, Takeda K, Takemura S, Nakagawa K, Mukaiyama Y, Suda T, Yasuda T, Ohta S, Takaya N, Fujiwara T, Izumi Y, Iwata T. Association between periodontal inflammation and serum lipid profile in a healthy population: A cross-sectional study. J Periodontal Res. 2021 Dec;56(6):1037-1045.
-
Katz I, Priolo-Filho S, Katz C*, Andresen S, Bérubé A, Cohen N, Connell CM, Collin-Vézina D, Fallon B, Fouche A, Fujiwara T, Haffejee S, Korbin JE, Maguire-Jack K, Massarweh N, Munoz P, Tarabulsy GM, Tiwari A, Truter E, Varela N, Wekerle C, Yamaoka Y. One year into COVID-19: What have we learned about child maltreatment reports and child protective service responses? Child Abuse Negl. 2021 Dec 31;105473.
-
Katagiri A, Nawa N, Fujiwara T*. Association Between Paternal Separation During Early Childhood and Pubertal Timing Among Girls Using Longitudinal Birth Cohort in Japan. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Dec 21;12:766728.
日本語アブストラクト
「日本における出生コホートを用いた女児における幼児期の父親との別居と思春期開始の時期の関連性」
【背景と目的】
これまでの研究で、高所得国の女児において、父親の不在が思春期開始の早期化につながることが示されている。日本では離婚率が低いにもかかわらず、社員が配偶者や子どもと一緒に転勤する単身赴任と呼ばれる独特の会社制度により、父子分離がよく見られる。我々は、離婚や死亡による父の不在、および父の単身赴任を含む、幼児期における父の分離を、ピーク身長速度(PHV)年齢で評価される女児の思春期発達の開始を予測するか検討した。
【方法】
本研究は、厚生労働省が2001年から2016年にかけて日本で実施した21世紀出生児縦断調査の15, 214人の女児のデータを解析した。父子分離は、0.5歳から4.5歳まで毎年実施された調査から評価した。アウトカムは、6歳から15歳の間のPHV時の年齢と定義した。潜在的な交絡因子やその他の共変量を調整した線形回帰を実施した。
【結果】
父親の同居は88.7%の世帯で継続的に見られたが、父親分離はそれぞれ7.4%、2.8%、1.1%の世帯で1-2回、3-4回、5回(つまり常に父親と分離)、経験された。父親との分離が5回続いた女児は、常に父親と同居している女児と比較して、PHV時の年齢が0.42歳(95%信頼区間(CI):-0.75、-0.10)早かった。
【結論】
0.5~4.5歳を通じて父親との分離を経験した女児は、PHVを早期に経験した。 -
Yamaoka Y, Isumi A, Doi S, Fujiwara T*. Association between Children’s Engagement in Community Cultural Activities and Their Mental Health during the COVID-19 Pandemic: Results from A-CHILD Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Dec 20;18(24):13404.
日本語アブストラクト
「新型コロナ感染症パンデミック時の子どもの地域文化活動への参加と精神的健康との関連性: A-CHILD Studyの結果」
地域の文化活動に参加することで培われる社会的学習体験は、子どもの発達に影響を与えると考えられるが、地域活動への参加が子どもの精神的健康にどのように関係しているかを調べた研究はほとんどない。本研究では、子どもの地域文化活動への参加と精神的健康との関連性を検討することを目的とした。東京都足立区の全69小学校の6年生児童を対象に、足立区子どもの健康・生活実態調査(A-CHILD)を用いて行った(n = 4391)。保護者は、子どもの精神的健康(日本語版強さ・困難さ質問票(SDQ)で評価)、子どもの地域文化活動への参加度について回答した。子どもが最も頻繁に参加した地域活動は、地域のお祭りであった。地域の祭りに参加することは、人口統計学的変数、家族のソーシャルキャピタル、親子の相互作用を調整した後、より低い行動困難(β = -0.49, SE = 0.17, p = 0.005) およびより高い向社会的行動(β = 0.25, SE = 0.07, p < 0.001 )と有意に関連していた。これらの結果は、新型コロナ感染症パンデミック時に、子どもたちが地域の文化活動に参加することが、子どもたちの心の健康に重要であることを強調している。 -
Tani Y, Isumi A, Doi S, Fujiwara T*. Associations of Caregiver Cooking Skills with Child Dietary Behaviors and Weight Status: Results from the A-CHILD Study. Nutrients. 2021 Dec 18;13(12):4549.
日本語アブストラクト
「養育者の調理スキルと子どもの食行動および体格との関連性: A-CHILD Studyの結果」
日本における養育者の調理スキルが、家庭料理の頻度、子どもの食事行動、子どもの体格と関連するかどうかを検討した。東京都足立区の9~14歳の小中学生を対象とした「2018年 足立区子ども健康・生活実態調査」の横断データを用いた(n = 5257)。養育者の調理スキルは、良好な妥当性と信頼性を有する尺度を日本で使用するために修正して用いた。学校の健康診断データから得られた子どもの身長と体重は、WHO標準肥満度Zスコアの算出に使用された。潜在的な交絡因子を調整した結果、調理スキルの低い養育者は、調理スキルの高い養育者に比べて家庭での調理頻度が低い可能性が4.31倍(95%信頼区間(CI): 2.68-6.94 )であった。養育者の調理スキルが低い子どもは、野菜の摂取頻度が低い可能性が2.81(95%信頼区間:2.06-3.84)倍、肥満の可能性が1.74(95%信頼区間:1.08-2.82)倍であった。養育者の調理スキルが低いことは、家庭での調理頻度の低さ、子どもの不健康な食事行動、子どもの肥満と関連していた。 -
Morishita S, Yoshii T*, Inose H, Hirai T, Yuasa M, Matsukura Y, Ogawa T, Fushimi K, Katayanagi J, Jinno T, Okawa A, Fujiwara T. Perioperative Complications of Laminoplasty in Degenerative Cervical Myelopathy -A Comparative Study Between Ossification of Posterior Longitudinal Ligament and Cervical Spondylotic Myelopathy Using a Nationwide Inpatient Database. Global Spine J. 2021 Dec 17;21925682211063867.
-
Hanafusa M, Kuramochi J, Ishihara K, Honda M, Nawa N, Fujiwara T*. Clinical Characteristics of Patients with SARS-CoV-2 N501Y Variants in General Practitioner Clinic in Japan. J Clin Med. 2021 Des 14;10(24):5865.
日本語アブストラクト
「本の開業医におけるSARS-CoV-2 N501Y変異体の患者の臨床的特徴について」
SARS-CoV-2亜種のN501Y変異(N501YV)を有する患者の臨床特性は、特に一般診療所という環境において十分に理解されていない。この後方視的コホート研究では、2021年3月26日から5月26日の間に1つの一般開業医の診療所に入院したCOVID-19患者を後方視的に分析した。治療前の特徴、臨床症状、X線所見をN501YVと野生型501Nの間で比較した。28名の患者が野生型501N、24名がN501YVと分類された。平均(±標準偏差)年齢は37.4(±16.1)歳であり、有意差はなかった。臨床症状のうち、38℃以上の発熱の有病率は、N501YV群が野生型501N群より有意に高かった(p=0.001)。多変量解析では、38℃以上の発熱は引き続きN501YVと有意に関連していた(調整オッズ比[aOR]:6.07、95%信頼区間[CI]:1.68~21.94)。CT所見では、肺病変面積はN501YVに感染した患者で有意に大きかった(p = 0.013)。以上のことから、N501YV群では、野生型501N群に比べ、38℃以上の発熱や広範囲の肺炎が高頻度に観察された。その他の人口統計学や臨床症状については、有意差はなかった。 -
Khin YP, Nawa N, Fujiwara T, Surkan PJ. Access to contraceptive services among Myanmar women living in Japan: A qualitative study. Contraception. 2021 Nov;104(5):538-546.
日本語アブストラクト
「日本在住のミャンマー人女性における避妊サービスへのアクセス: 質的研究」
【目的】
日本における移住者の健康状態は比較的悪いにもかかわらず、彼らの生殖医療へのアクセスについてはほとんど知られていない。我々は、在日ミャンマー人移住者における、避妊サービスに特化したアクセスへの認識された障壁とその結果を探るために、質的調査を実施した。
【方法】
2020年1月から4月にかけて、東京都、埼玉県、千葉県の医療機関で働くミャンマー人移住女性への17回の詳細インタビューと、ミャンマー人通訳への4回のキーインフォーマントインタビューを実施した。インタビューを書き起こし、ATLAS.tiで主にLevesqueらの医療アクセスの概念フレームワークの5つの要素に基づく演繹的アプローチでコーディングした。また、概念フレームワーク以外のテーマが浮かび上がるように、帰納的なコーディングも行った。
【結果】
17名の女性のうち、半数近くが、推定受胎可能期間に基づく定期的な禁欲、または休薬法を用いていると回答した。さらに、半数強の女性が意図しない妊娠の既往歴があった。ミャンマー人移住女性の避妊具へのアクセスには、言葉の壁、限られた健康情報源、文化的・健康的信念、経済的要因が重要な役割を担っていた。女性たちは、これらの障壁が、家族計画や意図しない妊娠に対するコントロールの欠如を感じさせる結果となっていることを説明した。
【結論】
日本におけるミャンマー人移住者は、避妊具へのアクセスに制限があることが示唆された。言語の壁、限られた情報源、健康信念、文化的・経済的要因がアクセスに影響を及ぼしていた。
【示唆】
この結果は、日本におけるミャンマー人女性の社会的認識と避妊へのアクセスを向上させるために、非営利の支援プログラムが、ミャンマー人移民の既存の社会的ネットワーク、通訳、日本のリプロダクティブヘルス分野の医師や研究者の助けを借りることが有益であることを示唆した。 -
Mizuki R, Fujiwara T*. Association Between Accumulation of Child Maltreatment and Salivary Oxytocin Level Among Japanese Adolescents. Front Psychiatry. 2021 Nov 29;9:710718.
日本語アブストラクト
「思春期の日本人における不適切養育の蓄積と唾液中オキシトシン濃度の関連」
【背景】
子ども期の不適切養育(虐待とネグレクト)は、社会的機能に関連するオキシトシンとの関連が報告されている。有害な状況を回避するためにオキシトシンレベルを下げていると考えられるが、思いやり・絆反応というストレス対応戦略を用いて状況に適応するためにオキシトシンレベルを増加させている可能性がある。
【目的】
本研究は、思春期の日本人における中・重度の不適切養育の蓄積と唾液中のオキシトシンレベルの関連性を検討することを目的とする。参加者は児童養護施設で暮らす人(n = 31)と親と暮らす人(n = 46)の協力を得て実施した。
【方法】
子ども期の不適切養育は、Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)を用いて測定した。唾液OT濃度は酵素結合免疫吸着法で評価した。多変量回帰分析を行い、共変量(年齢、性別、施設入所期間など)で調整した子どもの不適切養育の蓄積と唾液中のオキシトシンレベルの関連性を検討した。
【結果】
身体的虐待はオキシトシンレベルの上昇と関連し、感情的ネグレクトはオキシトシンレベルと逆相関を示した。オキシトシンレベルは、不適切養育が1つのグループで最も低く、非不適切養育経験群と比較して有意に低い値であった。不適切養育が1種類から2~3種類、4~5種類と増加するにつれて、オキシトシンレベルも増加した。この不適切養育の数とオキシトシンレベルのU字型関連は、モデルにおける不適切養育数の二乗項の有意な結果によって確認された(p = 0.012)。
【結論】
子どもの不適切養育の蓄積と唾液中のオキシトシンの値の間にU字型の関連性があることを見出した。また、不適切養育の種類によって、唾液中のオキシトシンレベルに与える影響は様々であった。不適切養育とオキシトシンレベルの非線形な関連を解明するためには、さらなる研究が必要である。 -
Yamaoka Y, Isumi A, Doi S, Ochi M, Fujiwara T*.Differential Effects of Multiple Dimensions of Poverty on Child Behavioral Problems: Results from the A-CHILD Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Nov 11;18(22):11821.
日本語アブストラクト
「貧困の子どもの行動問題へ影響は貧困の内容で異なる: A-CHILD研究からの結果」
【背景と目的】
低所得と物質的困窮、特に子どもの教育的ニーズに関連する困窮の子どもの発達への影響は、これまであまり検討されてこなかった。本研究は、低所得、生活に関連した剥奪、子どもに関連した剥奪が子どもの行動問題に及ぼす影響を検討することを目的とした。
【方法】
本研究では、日本の2015年、2017年、2019年に足立区子ども健康影響調査(A-CHILD)に参加した小学1年生のデータ(N = 12,367)を用いた。物質的剥奪は生活関連剥奪(生活に必要なものがないなど)と子ども関連剥奪(子どもの本がないなど)に分け、低所得は世帯の年間収入で評価した。
【結果】
子どもの行動問題や向社会的行動については、Strengths and Difficulties Questionnaireを使用して評価した。10人に1人の子どもが低所得家庭に属し、15.4%の子どもが生活に関連した剥奪を経験し、5.4%の子どもが子どもに関連した剥奪を経験した。生活上の困窮と子どもに関する困窮は、行動上の問題に大きな悪影響を及ぼすが、向社会的行動との関連はなかった。低所得の影響は,親の心理的苦痛(45.0%)と相談先の数(20.8%)によって行動問題への媒介がなされた.生活関連および子ども関連の剥奪の効果は、親の心理的苦痛(29.2-35.0%)および相談先の数(6.4-6.9%)によって、行動問題に対して媒介されることがわかった。
【結論】
低所得ではなく、生活関連と子ども関連の剥奪が子どものメンタルヘルスに重要である。 -
Yamaoka Y, Hosozawa M, Sampei M, Sawada N, Okubo Y, Tanaka K, Yamaguchi A, Hangai M, Morisaki N. Abusive and positive parenting behavior in Japan during the COVID-19 pandemic under the state of emergency. Child Abuse and Neglect. 2021 Oct;120:105212.
日本語アブストラクト
「COVID-19パンデミックによる緊急事態宣言下における日本での虐待的およびポジティブな親の関わりの実態調査」
【背景】
コロナウイルス感染症2019(COVID-19)のパンデミックは、子どもや親の生活を変え、子どものマルトリートメントに対する懸念を高めている。
【目的】
COVID-19のパンデミックにおける虐待的な養育行動の有病率と、身体的、心理的、社会的要因およびポジティブな養育行動との関係を調べた。日本におけるCOVID-19の緊急事態宣言中にオンライン調査を実施した。参加者は、0~17歳の子どもを持つ親5344名である。
【方法】
子ども関連団体のウェブサイトやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)など、複数のプラットフォームを利用して、無記名のオンライン調査を実施した。虐待行為に関連する要因を特定するために、多重ロジスティック回帰分析を実施した。
【結果】
5分の1の親が虐待行為を報告したのに対し、8割以上の親がポジティブな養育行動(子どもに共感する等)を報告した。虐待的な養育行動は、スクリーンタイムの長さ(1日6時間以上:OR, 1.44; 95%CI, 1.05-1.98 )、母親のメンタルヘルス不良(K6 = 13+:OR, 2.23; 95%CI, 1.71-2.89 )、DVの発生( OR, 4.54; 95%CI, 3.47-5.95 )と関連していた。ポジティブな養育行動、特に共感を示すことは、虐待行動のリスクの低下と関連していた(OR, 0.51: 95%CI, 0.39-0.66)
【結論】
COVID-19パンデミック時の児童虐待の予防には、ポジティブな養育行動が必要かもしれない。 -
Park S, Greene MC, Melby MK, Fujiwara T, Surkan PJ. Postpartum depressive symptoms as a mediator between intimate partner violence during pregnancy and maternal-infant bonding in Japan. J Interpers Violence. 2021 Oct;36(19-20):NP10545-NP10571.
日本語アブストラクト
「日本における妊娠中の親密なパートナーからの暴力と母子の絆との媒介要因としての産後抑うつ症状」
妊娠中に親密なパートナーからの暴力(IPV)を経験することは、母子の絆の悪化に関係することが研究で示されている。しかし、この関係の根底にあるメカニズムは不明である。本稿の目的は、妊娠中のIPVと母子の絆の関連を、母親の産後抑うつ(PPD)症状が媒介するかどうか、また母子の絆の下位尺度(愛情不足、怒り/拒絶)によって関係が異なるかどうかを検討することである。2012年に愛知県の4ヶ月健診に参加した女性(N = 6,590)を対象に調査を実施した。感情的・身体的IPVの経験が母子のボンディングに関連するかどうか、またPPD症状がこの関係を媒介するかどうかを検討した。パス解析の結果、感情的・身体的IPVはPPD症状と関連し、PPD症状はボンディング不良を予測した。情緒的IPVのボンディング不良への影響は合計で有意であり、わずかに有意な直接効果と統計的に有意な間接効果を示した。身体的IPVのボンディング不良に対する総効果は統計的に有意ではなかった。感情的IPVは、愛情不足と怒り/拒絶の絆下位尺度の両方と有意に関連しており、これらは同様にPPD症状によって媒介された。調査結果は、IPV、特に感情的IPVとボンディング不良との間に緩やかな間接的関連があることを明らかにし、それはPPD症状によって媒介されていた。IPVの予防は究極の目標であるが、妊娠中にIPVを経験した女性のPPD症状の治療は、母子のボンディングを改善し、IPVの世代を超えた影響を緩和する可能性がある。IPVとPPD症状を発見する機会を特定し、予防と早期介入を行うことで、母子ボンディングを改善できる可能性がある。 -
Mastuyama Y, Isumi A, Doi S, Fujiwara T*. Being left alone at home and dental caries of children aged 6-7 years. J Epidemiol. 2021 Oct 30. doi: 10.2188/jea.JE20210321. [Epub ahead of print]
日本語アブストラクト
「小学校1年生を対象とした留守番と虫歯の関係」
【背景・目的】
子どもを一人で留守番させることは、国によってはネグレクトとみなされるが、日本では禁止されてはいない。我々は、日本における小学校1年生(6~7歳児)の留守番と虫歯の関連について調査した。
【方法】
2015年、2017年、2019年に実施された横断調査で得られた、東京都足立区の全69校の公立小学校の1年生のデータを分析した。保育者が質問票に回答し,そのデータは学校歯科健診で評価された子どもの虫歯に関する情報(N = 12,029)とリンクした。交絡因子を考慮するために、傾向スコアマッチング(PSM)を用いたポアソン回帰分析を適用した。
【結果】
平日に1時間以上子どもを自宅で一人にする留守番は、46.4%の養育者が報告しており、これは年によって異なるものではなかった。PSM分析の結果、留守番経験のない子どもと比較して、週に1回以上留守番をする子どもは虫歯が多く(平均比[MR]1.11;95%信頼区間(CI)、1.02-1.21;P=0.016)、週に1回未満の留守番は関連がなかった(MR 0.97;95%CI,0.92-1.03;P=0.345).また、週1回未満の留守番と週1回以上の留守番の差は、ボンフェローニ補正を適用すると有意ではなかった(MR 1.12; 95% CI, 1.00-1.26; P = 0.041)
【結論】
毎週1時間以上の留守番は、6~7歳児のう蝕のリスクファクターとなる可能性がある。 -
Nawa N*, Trude ACB, Black MM, Richiardi L, Surkan PJ. Associations between Paternal Anxiety and Infant Weight Gain. Children(Basel). 2021 Oct 28;8(11):977.
日本語アブストラクト
「父親の不安と乳幼児の体重増加の関連性」
【背景と目的】
本研究の目的は、親の不安症状と乳児の体重変化との関係を検討することである。
【方法】
生後4、8、12カ月に体重測定を前向きに収集した出生コホートであるAvon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC)の子ども551人を対象に、二次データ解析を行った。父親と母親の不安症状は、Crown-Crisp Experiential Indexの8項目の不安に関する下位尺度に基づいた。
産後8週間の時点で上位15%のスコアを持つ参加者を、不安症状が高いグループと分類した。一般化推定方程式を用いて、親の不安症状と子どもの年齢に対する体重のZスコアの変化との間の関係を推定した。
【結果】
母親は不安症状が高くないが、父親が不安症状が高い子どもは、両親ともに不安症状が高くない子どもに比べて、年齢別体重のZスコアの増加が0.15(95%CI:0.01、0.29)大きいことが示された。
【結論】
この結果は、母親の不安症状ではなく父親の不安症状が、子どもの体重のZスコアのより大きな増加と関連していることを示唆している。
産後うつ症状のスクリーニングに加えて、産後に母親と父親の両方の不安症状のスクリーニングを検討する重要性が示唆された。
ただし、研究の限界を考慮すると、本研究の結果は予備的なものであり、あくまでも仮説の創出と考えるべきである。 -
Matsuyama Y*, Fujiwara T. Role of Libraries in Human Flourishing: Adolescents’ Motivational Orientation for Occupation. Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 21;18(21):11209.
日本語アブストラクト
「人間のフラーリッシングにおける図書館の役割:青年に職業に対する動機付けをもたらすか」
【背景と目的】
青年期は人間のフラーリッシングにとって重要であり、人生の意味を持つことに強く影響する。本研究では、日本の青年期における共有資源としての地域公共図書館の密度と職業への動機づけ志向の関連について検討した。
【方法】
日本全国の出生コホート調査(n = 12,184)のデータを用いて、縦断的研究を行った。7歳の時点で、その養育者は、読んだ本の数を含む子どもに関するアンケートに回答した。各自治体の図書館密度(低、中、高)は、国の統計から入手した。15歳のとき、参加者は職業を決めたかどうかを答え、動機づけの方向性を内発的(自分の能力や興味)、外発的(高収入、社会階級、仕事の安定)、利他的(社会貢献)の中から選択した。世帯の社会経済状況や都市の規模などの交絡因子を調整した上で、マルチレベル線形モデルを当てはめた。
【結果】
希望する職業に対する動機は、内発的動機が40.7%、外発的動機が31.9%、利他的動機が41.8%であった。7歳時に図書館密度の高い自治体に住んでいることは、15歳時に内発的動機を持つことと、低い密度よりも3.1ポイント関連した(95%信頼区間(CI): 0.35, 5.85).この関連は、所得の低い人ほど顕著であった(交互作用のP値 = 0.026)。外発的動機も利他的動機も図書館の密度とは関連しなかった(係数:-0.13、95%CI:-2.81、2.56、係数:0.08、95%CI:-2.72、2.88)。
【結論】
地域社会に図書館を整備することで、特に低所得世帯の青少年の内発的動機付けを促すことができる。 -
Doi S*, Koyama Y, Tani Y, Murayama H, Inoue S, Fujiwara T, Shobugawa Y. Do Social Ties Moderate the Association between Childhood Maltreatment and Gratitude in Older Adults? Results from the NEIGE Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 21;18(21):11082.
日本語アブストラクト
「高齢者における社会的つながりは子ども期の虐待経験と感謝の関連を修飾するか?:NEIGE Study」
【背景】
子ども期の虐待経験があると、感謝する傾向が低いことが示されているが、高齢者においても同様の結果が得られるのか、その関連における保護要因はわかっていない。本研究では、1)高齢者における子ども期の虐待経験と感謝との関連について検討する、2)社会的つながりが子ども期の虐待経験と感謝の関連を修飾するかを検討することを目的とした。
【方法】
2017年に実施されたNeuron to Environmental Impact across Generations (NEIGE)の横断データを用いて、新潟県十日町市の機能的障害がない65歳から84歳までの地域高齢者524名を対象とした。質問紙を用いて、18歳までの3種類の虐待経験(身体的虐待、情緒的ネグレクト、心理的虐待)、感謝の度合い(人生で感謝することがたくさんある、いろいろな人に感謝する)、社会的つながり(ご近所付き合い、友人に会う頻度)について回答を求めた。
【結果】
情緒的ネグレクト(親から愛されていると感じなかった経験)は感謝の度合いの低さと関連していることが示された。さらに情緒的ネグレクトと感謝における負の関連は、社会的つながりが低い高齢者においてのみ見られた。
【結論】
社会的つながりを高めることで、情緒的ネグレクトが感謝の度合いに与える悪影響を軽減できる可能性が示唆された。 -
Doi S, Isumi A, Fujiwara T*. Impact of school closure due to COVID-19 on the social-emotional skills of Japanese preschool children. Front Psychiatry. 2021 Oct 21;12:739985.
日本語アブストラクト
「COVID-19による保育所閉鎖が日本の未就学児における非認知スキル(社会情動的スキル)に与える影響」
【目的】
本研究では、2020年における新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)の第1波による自主的な保育所閉鎖に伴う、園行事の縮小が日本の未就学児の社会情動的スキルに与える影響を検討することを目的とした。
【方法】
本研究では、厳しい園封鎖は行われておらず、自主的な園封鎖が推奨されていた東京都内の3つの保育所に通園する4〜5歳の32名の子どもを対象とした。子どもの社会情動的スキルは、Devereux Student Strengths Assessment mini (DESSA-mini)を用いて、2019年11月、2020年1月(COVID-19拡大前)、および2020年3月(COVID-19第1波中)の3回にわたり、担任保育士によって評価された。すべての保育所が2020年3月2日から自主的な園封鎖を実施し、2園(A園、B園)が園行事である発表会を中止し、1園(C園)のみが3月4日に発表会を開催した。COVID-19拡大前と第1波中のDESSA-miniのT得点の違いを検討するために、反復測定分散分析を実施した。
【結果】
C園の子どもは、安定したDESSA-miniのT得点を示したものの、A園とB園の子どもは、COVID-19前と比べて第1波中のT得点は低くなっていた。また、時間と園の交互作用が示された(F=7.05, p<0.001)。
【考察】本研究の結果から、保育所での発表会が、COVID-19のパンデミック下でも子どもの社会情動的スキルを維持するために重要であった可能性が示唆された。 -
Nawa N, Tebi D, Kuramochi J, Fujiwara T. Estimation of the total number of SARS-CoV-2-infected individuals and the necessary tests and cost during the first wave of the COVID-19 pandemic in Japan. J Epidemiol. 2021 Oct 5;31(10):554-555.
日本語アブストラクト
「日本におけるCOVID-19パンデミック第1波におけるSARS-CoV-2感染者の総数、必要な検査とコストの推定」
【研究の背景】
日本における新型コロナウイルス感染症患者の報告数は、欧米に比べて少ないことが知られている(WHO, 2020)。新型コロナウイルス感染症は、集団により半数以上が無症候性であることが知られており(Arons et al, NEJM, 2020)、無症候性感染者は未診断のことも多いため、有症状の感染者や濃厚接触者だけを対象とした従来の調査では、地域の感染者数を正確に把握することは困難である。そのため、決めた地域における無作為抽出した集団に対して血清学的疫学調査を行い、無症候性感染者および非感染者も対象に含めた、地域の人口ベースでの感染状況を明らかにすることが重要である。本研究の目的は、宇都宮市の無作為抽出世帯において、新型コロナウイルス感染症の有病率を調査することである。
【研究の方法】
宇都宮市で住民基本台帳から無作為抽出した1000世帯2290名のうち、742名を対象に新型コロナウイルスの抗体検査を実施した。
【研究成果の概要】
742名の参加者(参加率:32%)のうち、86.8%が18歳以上、52.6%が女性、71.1%が診療所から10km以内に居住、89.2%が家族と同居をしていた。年齢および性別の分布や診療所からの距離は参加者と非参加者で違いはなかったが、単身世帯数は参加者のほうが少なかった(参加者が10.8%、非参加者が16.2%)。定量検査で 既往の感染を示すIgG抗体が陽性だったのは3名で、感染率は0.40%(95%信頼区間:0.08-1.18%)だった。調査参加者の傾向を多重代入法によって補正すると、感染率は1.23%(95%信頼区間:0.17-2.28%)だった。陽性と判定された人と同じ世帯に住んでいる人の中には陽性例はいなかった。
【研究成果の意義】
本結果より、人口518,610人(2020年6月1日時点)の宇都宮市の感染者数は2074-6378名と推定され、第1波の期間における感染者報告数23人の90-277倍の感染者がいる可能性があることがわかった。ほとんどの人口は感染していないが、把握している感染者数はかなり少なく、より広範囲に、病院以外の場所も含めてPCR検査または抗原検査を実施し、感染者の隔離等を行っていく必要があると考えられた。 -
Doi S, Isumi A, Fujiwara T*. Association between Adverse Childhood Experiences and Time Spent Playing Video Games in Adolescents: Results from A-CHILD Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 2;18(19):10377.
日本語アブストラクト
「思春期児童における逆境体験とテレビゲーム時間の関連:A-CHILD Study」
【背景】
過度なテレビゲーム時間は、思春期児童の健康に悪影響があることがわかっている。親子関係の問題や友人関係の問題は、ゲーム時間の長さを予測するとされているが、子ども期の逆境体験(ACE)がテレビゲーム時間と関連するかは明らかになっていない。本研究では日本の思春期児童を対象にACEとテレビゲーム時間との関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】
2016年、2018年に実施された足立区子どもの健康・生活実態調査(Adachi Child Health Impact of Living Difficulty (A-CHILD) study)の小学4年生、小学6年生、中学2年生合計6799名の横断データを用いた。思春期児童は、平日1日におけるテレビゲーム時間(1時間未満、1時間以上3時間未満、3時間以上)、ACE(8タイプ)について質問紙で回答した。
【結果】
順序ロジスティック回帰分析の結果、共変量を調整後もACE得点の高い(ACEの数が多い)ほど、テレビゲーム時間が長いことが示された(1 ACE: OR = 1.28, 95%信頼区間 = 1.10–1.48; 2 ACEs: OR = 1.25, 95%信頼区間 = 1.06–1.48; 3 + ACEs: OR = 1.44, 95%信頼区間 = 1.14–1.82, p for trend < 0.001)。ACEの8つのタイプそれぞれについて検討した結果、ひとり親家庭であること、保護者に精神疾患の既往歴があること、友人から孤立していることが、独立してテレビゲーム時間の長さと関係していた。
【結論】
子ども期の逆境体験の問題に取り組む健康政策が、思春期児童のテレビゲーム時間の短縮に重要である可能性がある。 -
Okada S, Doi S, Isumi A, Fujiwara T. The association between mobile devices use and behavior problems among fourth grade children in Japan. Psychiatry Clin Neurosci. 2021 Sep;75(9):286-293.
日本語アブストラクト
「日本の小学4年生におけるモバイル機器の使用と行動問題の関連性」
【背景と目的】
これまでの研究では、子どもにおけるモバイル機器の使用期間と行動問題の関連性については、さまざまなエビデンスが示されていた。我々は、男女別に層別化した小学4年生(=9~10歳)の大規模な地域ベースのサンプルを用いて、この関連性を検証することを目的とした。
【方法】
東京都足立区の全公立学校の小学4年生(9~10歳)を対象に質問票を配布した(n = 4,105)。モバイル機器の使用期間は自己申告、行動問題は養育者による「強さと困難の質問票(SDQ)」で評価した。社会経済的地位、家族のソーシャルキャピタル、友人の数などの潜在的交絡因子を調整した上で、重回帰分析を行った。
【結果】
男児では,モバイル機器の使用時間と行動問題の間にU字型の関連が認められ,使用時間が1時間未満の男児は,モバイル機器を使用していない男児と比較して,総困難度が0.88[95%信頼区間(CI)-1.50~-0.27]ポイント低く,使用時間が1時間以上の男児の総困難度は非使用者と差がなかった.女子では、モバイル機器の使用時間と総合的な問題行動スコアの間に用量反応的な正の関連が認められた(傾向のP:<0.001)。
【結論】
9~10歳の子どもにおいて、男児ではモバイル機器の使用時間が1時間未満は行動問題の保護因子であり、女児では使用時間が1時間以上は危険因子であった。この結果を確認するためには、さらなる縦断的研究が必要である。 -
Morita T, Fujiwara T. Association between Childhood Parental Involvement and Late-Life Cognitive Function: A Population-based Cross-Sectional Study among Cognitively Intact Community-dwelling Older Adults in Japan. Geriatr Gerontol Int. 2021 Sep;21(9):794-801.
日本語アブストラクト
「子ども期における親の関わりと高齢期の認知機能:日本人地域在住高齢者を対象にした横断研究」
【背景】
劣悪な養育環境下で育った子どもは、そうでない子どもと比べて、高齢期の認知機能が低いことが知られています。しかし、ポジティブな育児行動が、劣悪な養育環境とは独立して高齢期の認知機能に与える影響についてのエビデンスは少なく、本研究は、子ども期の親の関わりと高齢期における認知機能との関連を検討しました。
【方法】
認知障害の兆候がない宮城県涌谷市在住の高齢者266名(65~88歳)を対象に調査を実施しました。子ども期の親の関わりは質問票で評価し、高齢期の認知機能は日本語版のQuick Mild Cognitive Impairment(QMCI)スクリーンテスト(得点範囲:0-100)で測定した。重回帰分析を行い、交絡因子と媒介因子の影響を考慮した解析を行いました。
【結果】
年齢・性別・子ども期の虐待経験・貧困・栄養状態・小学6年時の学業成績を調整した結果、子ども期に親の関わりが高い高齢者は、そうでない高齢者に比べて総合得点が6.00(95%CI:2.39、9.61)ポイント高くありました。子ども期における親の関わりは、総合得点(p<0.001)、時計描画テスト得点(p<0.05)、言語的流暢性得点(p<0.001)と有意な用量反応的な正の関連を示しました。6種類のポジティブな親の関わり方のうち、本の読み聞かせは総合得点(p < 0.01)および論理的記憶スコア(p < 0.01)と有意な独立した正の相関を示しました。上記の関連は、成人期以降の社会的環境や生活習慣の影響を調整後も有意でありました。
【考察】
子ども期の親の積極的な関わりが高齢期の高い認知機能と関連することが示されました。今回検討した親の関わりの中では、本の読み聞かせが、高い論理的記憶能力と関連することが示されました。
-
Tani Y, Doi S, Isumi A, Fujiwara T. Association of home cooking with caregiver–child interaction and child mental health: Results from the A-CHILD study. Public Health Nutr. 2021 Sep;24(13):4257-4267.
日本語アブストラクト
「家庭料理と養育者の子どもの関わりおよび子どものメンタルヘルスとの関連:足立区子どもの健康・生活実態調査(A-CHILD)の結果」
【目的】
日本における家庭料理と養育者の子どもとの関わりおよび子どものメンタルヘルスとの関連性を検討する。
【方法】
2018年に収集された横断的データを用いた。家庭料理の頻度は、4126人の養育者を対象に質問紙で評価し、高(ほぼ毎日)、中(4~5日/週)、低(≦3日/週)に分類された。養育者の子どもとの関わりは、一緒に話したり遊んだりする頻度(1週間あたり)で評価した。行動問題と向社会的行動はStrengths and Difficulties Questionnaire(SDQ)で評価し、レジリエンスはChildren's Resilient Coping Scaleで評価した。参加者は東京都足立区に住む9~10歳の子どもたちとその養育者である。
【結果】
家庭料理の頻度が低い、または中程度の子どもは、学校生活について話す頻度、子どもとニュースについて話す頻度、子どもとテレビ番組について話す頻度、子どもの宿題を手伝う頻度が低いことと関連していた。家庭料理の頻度が低い、あるいは中程度の子どもは、行動上の問題が多く(低頻度:β=3-95、95%CI 1-30、6-59、中頻度:β=3-38、95%CI 2-07、4-70)、向社会性の低さ(低頻度.社会経済的地位などの共変数を調整した後、家庭料理の頻度が高い子どもと比較して、β = -5-85, 95 % CI -10-04, -1-66)、レジリエンス(低頻度:β = -6-56, 95 % CI -9-77, -3-35、中頻度:β = -4-11, 95 % CI -5-71, -2-51) は低かった。これらの関連は、子どもの食行動および養育者の子どもとの関わりによって媒介された。
【結論】
養育者が家庭で料理をすることを奨励する環境を作ることは、子どものメンタルヘルスにとって重要であると考えられる。 -
Doi R, Kobayashi M*, Ogawa K, Morisaki N, Jwa CS, Fujiwara T. Validity of dietary patterns extracted from the food intake frequency questionnaires of Japanese pregnant women. Journal of Human Nutrition & Food Science. 2021 Sep 18;9(1):1140.
-
Ochi M*, Fujiwara T. Paternal childcare in early childhood and problematic behavior in children: A population-based prospective study in Japan. BMC Pediatrics. 2021 Sep 10;21(1):397.
日本語アブストラクト
「幼児期における父親の育児と子どもの問題行動: 日本における集団ベースの前向き研究」
【背景】
父親の育児が子どもの行動発達に及ぼす影響については、これまでにも多くの報告がある。しかし、長時間労働により父親が育児に十分な時間を割けない日本などのアジア諸国では、これらの効果についてほとんど知られていない。本研究では、5.5歳児を対象に、幼児期における父親の育児と育児行動の種類、その後の行動問題との関連を、性別で層別して調査した。
【方法】
日本の人口ベースのコホート調査である21世紀新生児縦断調査(2001-2006)のデータを分析した(N = 27,870)。父親の育児は、18ヶ月時点で、平日または週末の父親の育児時間と、各タイプの育児(食事、おむつ交換、入浴、寝かしつけ、家での遊び、外への連れ出し)の頻度という観点から評価した。父親の関与の頻度や欠如に基づき、子どもが5歳半のときに子どもの行動問題の6つのカテゴリーを評価した。既知の交絡変数を考慮するため、ロジスティック回帰分析を適用した。
【結果】
平日・週末を問わず、幼児期の父親の育児時間が長いと、5.5歳時の行動問題に対して保護効果があった。また,父親が子どもを外に連れ出す頻度と男児の行動問題,父親が家庭で子どもと遊ぶ頻度と男児・女児ともに行動問題の間に,量反応関係が見られた。
【結論】
幼児期における父親の育児は、その後の子どもの行動問題を予防する可能性がある。子どもを外に連れ出す、家で一緒に遊ぶなど、いくつかの特定の父親の育児行動が、その後の行動問題の予防に重要な役割を果たすと考えられる。 -
Yanagimachi M, Fukuda S, Tanaka F, Iwamoto M, Takao C, Oba K, Suzuki N, Kiyohara K, Kuranobu D, Tada N, Nagashima A, Ishii T, Ino Y, Kimura Y, Nawa N, Fujiwara T, Naruto T, Morio T, Doi S, Mori M*. Leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1 and angiotensinogen as diagnostic biomarkers for Kawasaki disease. PLoS One. 2021 Sep 9;16(9):e0257138.
-
Khin YP, Matsuyama Y, Tabuchi T, Fujiwara T*. Association of Visual Display Terminal Usage with Self-Rated Health and Psychological Distress among Japanese Office Workers during the COVID-19 Pandemic. Int J nviron Res Public Health. 2021 Sep 6;18(17):9406.
日本語アブストラクト
「COVID-19パンデミックにおけるVisual Display Terminalの使用状況と自己評価による健康状態および心理的苦痛との関連性」
【背景と目的】
日本におけるCOVID-19パンデミック時のオフィスワーカーにおいて、仕事と仕事以外の活動におけるビジュアルディスプレイターミナル(VDT)の使用期間と自己評価健康度(SRH)および心理的苦痛との関連性を検討する。
【方法】
2020年8月25日から2020年9月30日にかけて実施したWebベースの自記式調査によるオフィスワーカー7088名の横断データを用いた。多重ロジスティック回帰分析を適用した。
【結果】
仕事のために4~9時間VDTを使用した人と比較して、仕事のために10時間以上VDTを使用したオフィスワーカーは、SRH不良(オッズ比(OR):1.65、95%信頼区間(CI):1.13、2.41)および重度の心理的苦痛(OR:2.23、95% CI:1.52,3.28) が見られた。また、仕事のための1時間未満(OR:1.37、95%CI:1.12、1.67)および1~3時間(OR:1.42、95%CI:1.12、1.80)のVDT使用は、重度の心理的苦痛と関連していた。年齢による層別分析では、30~64歳では仕事のためのVDT使用とSRH不良との間に有意な関連が見られ、若い年齢層(15~29歳)では仕事のためのVDT使用と心理的苦痛との間にU字型の関連が見出された。
【結論】
日本におけるCOVID-19のパンデミック時、業務用VDTの長期使用は一般的な健康状態と心理的な健康状態を悪化させるが、業務用VDTの適度な使用は心理的苦痛を軽減する可能性がある。 -
Tani Y, Fujiwara T, Kondo K. Adverse childhood experiences and dementia: Interactions with social capital in JAGES cohort study. Am J Prev Med. 2021 Aug;61(2):225-234.
日本語アブストラクト
「子ども期の逆境体験と認知症:JAGESコホート研究におけるソーシャルキャピタルとの相互作用効果」
【背景と目的】
本研究では、個人レベルのソーシャルキャピタルが、子ども期の逆境体験と認知症発症の関連を修飾するかどうかを検討した。
【方法】
日本老年学的評価研究(JAGES)において身体的・認知的に自立している参加者を対象に3年間の追跡調査(2013~2016年)を実施した。16,821人の参加者の認知症発症は、公的介護保険制度を通じて評価した。18歳以前の子ども期の逆境体験とソーシャルキャピタルは、2013年のベースライン時に自己報告式の質問票を用いて評価した。親の死、親の離婚、親の精神疾患、家庭内暴力、身体的虐待、心理的ネグレクト、心理的虐待の計7つの子ども期の逆境体験が評価された。ソーシャルキャピタルの媒介効果を評価するため、個人のソーシャルキャピタル3項目(コミュニティ信頼、互恵性、愛着)を測定した。ソーシャルキャピタル全体のスコアは、低(<10パーセンタイル)、中(10~90パーセンタイル)、高(>90パーセンタイル)に分類された。データは2020年に分析した。
【結果】
3年間の追跡調査で、652件の認知症が発生した。子ども期の逆境体験が多い人は認知症のリスクが高かった。ソーシャルキャピタルスコアによる層別化では、3つ以上の子ども期の逆境体験のハザード比は、ソーシャルキャピタルが低い人では3.25(95% CI=1.73, 6.10)、ソーシャルキャピタルが中程度の人では1.19(95% CI=0.58, 2.43) であった。子ども期の逆境体験が3つ以上あり、ソーシャルキャピタルが高い人では、認知症の症例は観察されなかった。
【結論】
日本の高齢者において、子ども期の逆境体験が認知症発症率の上昇に関連したのは、ソーシャルキャピタルが低い人に限られていた。 -
Doi S, Fujiwara T, Isumi A. Association between maternal adverse childhood experiences and mental health problems in offspring: An intergenerational study. Dev Psychopathol. 2021 Aug;33(3):1041-1058.
日本語アブストラクト
「母親の幼少期の逆境体験と子どものメンタルヘルスとの関連」
【目的】
幼少期の逆境体験は成人期のメンタルヘルスの問題につながることがわかっている。さらに、その幼少期の逆境体験による悪影響は世代を超えて、次の世代の子どもにおける発達および身体的健康とも関連していることが明らかとなっている。一方で、母親の幼少期の逆境体験と、その子どものメンタルヘルスとの関係を検証した研究はない。そこで本研究では、母親の幼少期の逆境体験と、思春期児童におけるメンタルヘルスの問題との関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】
2016年に実施された「高知県子どもの生活実態調査」に参加した高知県の小学5年生(3,144組)、中学2年生(3,497組)、高校2年生(4,169組)の児童・生徒10,810名を対象とした。児童・生徒の母親に、幼少期の逆境体験、子どもの頃の社会経済的状況、現在のメンタルヘルス、現在の社会経済的状況、ポジティブな養育行動、不適切な養育行動、Strength and Difficulty Questionnaireを用いて子どもの問題行動について回答を求めた。児童・生徒には、Depression Self-Rating Scaleを用いて抑うつ症状について回答を求めた。
【結果】
交絡変数を調整した多変量回帰分析の結果、幼少期の逆境体験の数が多い母親を持つ子どもほど、問題行動が多く見られ(p for trend < 0.001)、抑うつ症状がある(p for trend < 0.001)ことが明らかとなった。また、母親の現在のメンタルヘルスの問題は、母親の幼少期の逆境体験と子どものメンタルヘルスの問題との関係を媒介していた。
【結論】 母親の幼少期の逆境体験は、世代を超えて、思春期児童の問題行動および抑うつ症状に悪影響を与えることが示唆された。今後は、母親の幼少期の逆境体験とその子どものメンタルヘルスの関連を媒介するその他の要因について詳しく検討する必要がある。
-
Morishita S, Yoshii T, Inose H, Hirai T, Yuasa M, Matsukura Y, Ogawa T, Fushimi K, Okawa A, Fujiwara T. Comparison of Perioperative Complications in Anterior Decompression With Fusion and Posterior Decompression With Fusion for Cervical Spondylotic Myelopathy: Propensity Score Matching Analysis Using a Nationwide Inpatient Database. Clin Spine Surg. 2021 Aug 1;34(7):E425-E431.
-
Mizuki R, Fujiwara T*. Validation of the Japanese version of the Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-J). Psychol Trauma. 2021 Jul;13(5):537-544.
日本語アブストラクト
「Childhood Trauma Questionnaire-Short Form(幼少期トラウマ質問票 短縮版)の日本語版(CTQ-J)の妥当性」
【背景と目的】
子ども虐待の報告が急増している日本では、簡潔な評価ツールが必要である。幼少期トラウマ質問票(CTQ)は、子ども虐待の評価ツールとして国際的に認められているが、その日本語版の妥当性はまだない。本研究では、CTQの日本語版(CTQ-J)の妥当性を検討した。
【方法】
首都圏の入所施設に入所している日本人青年(施設入所群、n=31)と施設入所経験のない青年(地域入所群、n=46)でCTQ-Jを実施した。CTQ-Jの総スコアと5つの下位尺度スコアについて、虐待を受けた施設入所群、虐待を受けなかった施設入所群、および施設入所経験のない対象群の間で群間比較した。CTQ-Jで評価されるスコアの識別力は、ROC分析を用いて計算し、マルトリートメントのカットオフを特定した。
【結果】
内部整合性は、すべての下位尺度において「良好」~「許容範囲」であった(Cronbach's alpha > .74)。各マルトリートメントタイプにおいて,マルトリートメント経験がある施設入所群は,他の群に比べ有意に高いCTQ-Jスコアを示した。AUCは、CTQ-Jの総得点(0.95)および各下位尺度(0.98-0.86)において高い識別性を示した。
【結論】
本研究は,CTQ-Jの信頼性を「良好」~「許容」レベルで示し,施設入所において児童福祉記録中の文書化されたマルトリートメント事例を特定することで基準妥当性を支持したが,その適用には慎重を期す必要がある。より代表的なサンプルを用いて、CTQ-Jがより深刻でない形態のマルトリートメントを識別する能力をテストするために、さらなる研究が必要である。 -
Doi S, Kobayashi Y, Takebayashi Y, Mizokawa E, Nakagawa A, Mimura M, Horikoshi M. Associations of autism traits with obsessive compulsive symptoms and well-being in patients with obsessive compulsive disorder: A cross-sectional study. Front Psychol. 2021 Jul 30;12:697717.
日本語アブストラクト
「強迫性障害患者における自閉症特性と強迫症状およびウェルビーイングの関連性: 横断研究」
【目的】
強迫性障害患者における自閉症特性と長期的な強迫性障害(OCD)症状およびウェルビーイングの関連性を検討した。
【方法】
参加者は、医療機関に通院する外来患者18名と、日本の大手インターネットマーケティング調査会社に登録された、Mini-International Neuropsychiatric InterviewによるOCD基準を満たす、20歳から65歳の成人100名である。臨床的特徴、Autism Spectrum Quotient(AQ)を用いて評価した自閉症特性、Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale(Y-BOCS)を用いて評価したOCD症状、Flourishing Scaleを用いて評価したウェルビーイングを評価した。
【結果】
重回帰分析の結果、AQの合計得点および下位因子である「想像力」得点が高いほど、Y-BOCSの得点が高いことが示された。AQ合計得点、「社会的スキル」、「想像力」の下位因子得点が高いほど、ウェルビーイング得点が低くなることが示された。自閉症特性、特に想像力の欠如は、より重度なOCD症状と関連していた。さらに、自閉症特性、特に社会的スキルの問題や想像力の欠如は、ウェルビーイングの低さと関連していた。
【結論】
治療前に自閉症特性を評価し、自閉症特性を持つOCD患者のためにデザインされたアプローチが必要である。 -
Tani Y*, Hanazato M, Fujiwara T, Suzuki N, Kondo K. Neighborhood sidewalk environment and incidence of dementia in older Japanese adults: the Japan Gerontological Evaluation Study cohort. Am J Epidemiol. 2021 Jul 1;190(7):1270-1280.
日本語アブストラクト
「近隣の歩道環境と日本人高齢者の認知症発症率:日本老年学的評価研究コホート(JAGES)の結果」
【背景と目的】
歩道は身体活動を促すという点で、日常生活において欠かすことのできない環境資源である。しかし、歩道の普及率は先進国でも低い。我々は、日本における近隣の歩道環境と認知症との関連性を検討した。
【方法】
地域在住の高齢者を対象とした人口ベースのコホート研究である「日本老年学的評価研究(JAGES)」の参加者を対象に、3年間の追跡調査(2010年~2013年)を実施した。公的介護保険制度から76,053名の参加者の認知症発症率を把握した。地理情報システム(GIS)を用いて、436の住宅地内の歩道カバー率(道路面積に占める歩道面積の割合)を算出した。マルチレベル生存モデルを用いて、認知症の発生率に関するハザード比を推定した。
【結果】
追跡調査中、5,310人の認知症患者が確認された。都市部では、個々の共変数を調整した結果、歩道カバー率が最も低い四分位と比較して、ハザード比は最高四分位で0.42(95%信頼区間:0.33、0.54)であった。他の近隣要因(土地の傾斜、病院、食料品店、公園、鉄道駅、バス停の数、教育水準、失業率)を調整しても、ハザード比は統計的に有意であった(ハザード比=0.71、95%信頼区間:0.54、0.92)。
【結論】
歩道の設置率が高い地域に住んでいることは、都市部における認知症発症率の低さと関連していた。 -
Matsuyama Y, Aida J, Takeuchi K, Koyama S, Tabuchi T. Dental pain and worsened socioeconomic conditions due to COVID-19 pandemic. J Dent Res. 2021 Jun;100(6):591-598.
日本語アブストラクト
「COVID-19パンデミックによる社会経済的状況の悪化と歯の痛みの関連」
【背景と目的】
コロナウイルス感染症2019(COVID-19)のパンデミックにより、経済が収縮し、社会が大きく制限されるようになった。経済へのショックは、歯の健康を含む身体的な健康成果の悪化につながる可能性がある。本研究では、日本におけるCOVID-19パンデミックによる社会経済状況の悪化と歯の痛みとの関連性を調査した。また、心理的苦痛と口腔保健関連行動の媒介効果も評価した。
【方法】
2020年8月から9月に実施した「JACSIS調査」の横断データ(n = 25,482、年齢範囲、15~79歳)を分析した。多変量ロジスティック回帰モデルを適用し、COVID-19パンデミックによる世帯収入減少、仕事減少、仕事喪失と1ヶ月以内の歯の痛みとの独立した関連性を評価した。
【結果】
歯の痛みは9.8%が報告した。家計の減少、仕事の減少、および仕事の喪失は、交絡因子調整後、歯の痛みと独立に関連していた(オッズ比: オッズ比:1.42[95%信頼区間(CI)、1.28-1.57]、1.58[95%CI、1.41-1.76]、2.17[95%CI、1.64-2.88]、それぞれ).世帯収入の減少に関連する関連は、心理的苦痛、歯科受診の延期、歯磨き行動、食間の食事行動によって、それぞれ21.3%(95%CI、14.0-31.6)、12.4%(95%CI、7.2-19.6)、1.5%(95%CI、-0.01-4.5)および9.3%(95%CI、5.4-15.2)媒介した。
【結論】
今回の結果から、COVID-19パンデミックによる社会経済状況の悪化が歯の健康を悪化させることがわかった。所得や職の喪失を保護する政策は、パンデミック後の歯の健康問題を軽減する可能性がある。 -
Yamaoka Y, Obikane E, Isumi A, Miyasaka M, Fujiwra T. Incidence of hospitalization for abusive head trauma in Chiba City, Japan. Pediatrics International. 2021 Jun 30 ;64(1):e14903.
日本語アブストラクト
「千葉市における虐待による頭部外傷の入院症例の発生率」
【背景】本研究では住民ベースのサンプルを用いて、千葉市における12ヶ月未満の乳児における虐待よる頭部外傷(Abusive Head Trauma: AHT)の入院症例の発生率を推測するために実施した。
【方法】2011〜2015年に千葉市内の全ての小児二次医療・三次医療機関に入院した乳児の診療記録を後方視的に調査した。多職種による院内虐待対応チームによってAHTと評価された13例を、さらに1人の小児放射線科医と2人小児科医が頭部CT画像と診療記録をレビューし、臨床的にAHTが強く疑われる症例と中程度疑われる症例と判定した。
【結果】乳児人口10万人年あたり、AHTの発生率は34.5人(95%信頼区間: 18.4-59.1)であり、そのうち強く疑う事例が 13.3人(95%信頼区間: 4.3-31.0)、中程度の疑い事例が 21.3人(95%信頼区間: 9.2-41.9)であった。強く疑われる症例と中程度疑われる症例ではCT所見には統計学的な有意差は認められなかった。
【結論】住民ベースの乳児におけるAHTの入院症例の発生率は、他諸国で報告されているものと類似していた。 -
Tani Y, Ochi M, Fujiwara T. Association of nursery school-level promotion of vegetable eating with vegetable consumption behaviors and BMI: A multilevel analysis of Japanese children. Nutrients. 2021 Jun 29;13(7):2236.
日本語アブストラクト
「保育園の野菜から食べる健康教育(ベジファースト)と野菜摂取行動およびBMIとの関連性: 日本人未就学児のマルチレベル分析」
【背景と目的】
保育園は、子どもたちが野菜消費を含む健康的な食行動を身につける上で重要な役割を果たすことができる。しかし、学校レベルの野菜摂取促進が野菜消費と体格指数(BMI)に及ぼす影響は、依然として不明である。本研究では、食事の際に野菜を最初に食べるという保育園レベルのプロモーションが、日本の子どもたちの野菜消費行動やBMIとどのような関連性があるのかを検討した。
【方法】
日本の東京都足立区にある全133の認可保育園の3~5歳児クラスの子どもたち7402人について、2015年、2016年、2017年に収集した横断データを使用した。保育者は、子どもの食行動(野菜を食べる頻度、野菜を食べる意欲、食べた野菜の種類数)、身長、体重について調査した。保育園レベルでのベジファーストの推進は、子どもが食事で野菜を優先的に食べたと回答した保育者の割合を学校レベルの浸透度の代理とした。学校レベルのベジファースト推進と野菜消費行動およびBMIとの関連を調べるために、マルチレベル分析を行った。
【結果】
ベジファースト推進度が1四分位範囲高い学校の子どもは、野菜料理を食べる頻度が高く(β = 0.04; 95% CI: 0.004-0.07) 、野菜を食べる意欲が高く(調整オッズ比 = 1.17; 95% CI: 1.07-1.28) 、野菜の種類も多く(調整オッズ比 = 1.19 倍; 95% CI: 1.06-1.34 )、また野菜の種類も多かった。学校レベルの野菜食推進は、BMIと関連しなかった。
【結論】
野菜を最初に食べるという学校レベルの健康戦略は、子どもの野菜摂取量を増やすことには有効かもしれないが、太りすぎを防ぐことには有効ではない。 -
Miyamura K, Nawa N, Isumi A, Doi S, Fujiwara T*. The association of passive smoking and dyslipidemia among adolescence in Japan: Results from A-CHILD Study. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Jun 16;106(7):e2738-e2748.
日本語アブストラクト
「日本での思春期児童における受動喫煙と脂質異常症の関連:A-CHILD Study」
【背景】子どもの受動喫煙と脂質異常症との関連は欧米では報告されているが、アジアでの報告は少なく、またその関連の性差については明らかになっていない。本研究では日本の思春期児童を対象に男女における受動喫煙と脂質異常症との関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】2016年、2018年に実施された足立区子どもの健康・生活実態調査(Adachi Child Health Impact of Living Difficulty (A-CHILD) study)の中学2年生1166名の横断データを用いた。質問紙により調査した受動喫煙の頻度と脂質(総コレステロール値、LDLコレステロール値、HDLコレステロール値)の関連を男女で層別化し、多変量解析で評価した。
【結果】男子においてのみ、受動喫煙に全く曝露されていない場合、受動喫煙に頻繁に曝露されている場合と比較しHDLコレステロール値が3.19㎎/dl (95%信頼区間 -5.84, -0.55)低かった。総コレステロール値及びLDLコレステロール値については男女とも受動喫煙との関連はみられなかった。
【結論】日本の思春期児童において男子でのみ受動喫煙とHDLコレステロール値との関連がみられた。今後縦断研究により同様の関連が見られるか確認する必要がある。
-
三瓶舞紀子、伊角彩、藤原武男. 妊娠期における乳幼児揺さぶられ症候群の教育的動画視聴による知識向上効果の検証. 日本公衆衛生雑誌. 2021 Jun 25;68(6)393-404.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jph/68/6/68_20-061/_article/-char/ja/
-
Kawatani K, Nambara T, Nawa N, Yoshimatsu H, Kusakabe H, Hirata K, Tanave A, Sumiyama K, Banno K, Taniguchi H, Arahori H, Ozono K. A human isogenic iPSC-derived cell line panel identifies major regulators of aberrant astrocyte proliferation in Down syndrome. Commun Biol. 2021 Jun 14;4(1):730.
-
Matsumoto Y, Fujino J, Shiwaku H, Miyajima M, Doi S, Hirai N, Jitoku D, Takagi S, Tamura T, Maruo T, Shidei Y, Kobayashi N, Ichihashi M, Noguchi S, Oohashi K, Takeuchi T, Sugihara G, Okada T, Fujiwara T, Takahashi H. Factors affecting mental illness and social stress in hospital workers treating COVID-19: paradoxical distress during pandemic era. J Psychiatr Res. 2021 May;137:298-302.
-
Koyama Y, Nawa N, Yamaoka Y, Nishimura H, Sonoda S, Kuramochi J, Miyazaki Y, Fujiwara T*. Interplay between social isolation and loneliness and chronic systemic inflammation during the COVID-19 pandemic in Japan: Results from U-CORONA Study. Brain Behav Immun. 2021 May;94:51-59.
日本語アブストラクト
「COVID-19パンデミックにおける社会的孤立・孤独感と慢性全身性炎症との相互作用:U-CORONA研究」
【背景】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の大流行によって、ソーシャルディスタンシングやロックダウン政策が実施され、結果として多くの人が社会的孤立や孤独に陥った。社会的孤立や孤独と心身の健康状態の悪化、そのメカニズムの一つとして慢性的な炎症が知られているが、社会的孤立と孤独の相互作用については明らかになっていない。そこで、本研究は、COVID-19パンデミックにおいてどのように社会的孤立と孤独が相互に作用し、慢性炎症マーカーと関連するかを明らかにすることを目的とした。
【方法】宇都宮市在住の無作為抽出された世帯を対象とした「宇都宮 新型コロナウイルス感染症調査(U-CORONA)」(2020年実施)のデータから、成人624人(18-92歳、平均51.4歳)を解析対象とした。社会的孤立は、日常的に担っている社会的役割の数を評価し、孤独感はUCLA孤独感尺度で測定した。慢性炎症のバイオマーカーとして好中球-リンパ球比(NLR)と高感度C反応性蛋白質(CRP)の濃度を測定した。一般化推定方程式(GEE)を用いて解析を行った。
【結果】男性において、孤立-孤独状態がNLRの上昇と関連していた。また、女性および労働年齢層において、非孤立-孤独状態がCRPの低下と関連していた。
【考察】社会的に孤立していること、孤独を感じていることは相互に作用しあい、慢性炎症と関連していることが明らかとなった。社会的孤立と孤独感の両方を評価することは、特にCOVID-19パンデミック下において、社会的関係と健康の影響を緩和するための適切な介入を行うために重要である。 -
Matsuyama Y, Jürges H, Dewey M, Listl S. Causal effect of tooth loss on depression: evidence from a population-wide natural experiment in the United States. Epidemiol Psychiatr Sci. 2021 May 25;30:e38.
日本語アブストラクト
「歯の喪失がうつ病に及ぼす因果関係:米国における集団規模の自然実験からのエビデンス」
【背景と目的】
うつ病は人々の健康や幸福に深刻な影響を与える。口腔疾患はうつ病との関連が示唆されているが、今のところ因果関係のあるエビデンスはない。本研究では、自然実験研究において、米国成人のうつ病に対する歯の喪失の因果関係を明らかにすることを目的とした。
【方法】
BRFSSの2006年、2008年、2010年調査に参加した1940-1978年生まれの169,061人のデータを用いて操作変数分析を行った。幼少期のフッ化物への曝露の違いによる歯の喪失のランダムな変動を操作変数として利用した。
【結果】
幼少期にフッ化物飲料水への曝露を受けた米国成人の残存歯数は、より多く、したがって、頑健な操作変数であった(F = 73.4)。歯を1本失うごとに、8項目のPatient Health Questionnaire depression(PHQ-8)スコアによる抑うつ症状が0.146(95%CI 0.008-0.284)増加し、臨床上の抑うつ状態の確率は0.81ポイント(95%CI:-0.12 から1.73) 増加した。
【結論】
歯の喪失は、米国成人のうつ病を増加させる原因となった。10本以上の歯を失うと、抗うつ薬を投与していない大うつ病性障害の成人と同程度の影響があった。 -
Nawa N, Yamaoka Y, Koyama Y, Nishimura H, Sonoda S, Kuramochi J, Miyazaki Y, Fujiwara T. Association between Social Integration and Face Mask Use Behavior during the SARS-CoV-2 Pandemic in Japan: Results from U-CORONA Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Apr 28;18(9):4717.
日本語アブストラクト
「日本におけるSARS-CoV-2流行時の社会的統合とフェイスマスク使用行動との関連性: U-CORONA研究の結果」
フェイスマスクの使用は、SARS-CoV-2の蔓延を防ぐために重要な行動である。我々は、宇都宮市(日本)の世帯の無作為サンプルにおいて、COVID-19パンデミック時の社会的統合とフェイスマスク使用の関連性を評価することを目的とした。データには、パンデミックの第1波後の2020年6月14日から2020年7月5日の間に宇都宮市で実施された宇都宮COVID-19 seROprevalence Neighborhood Association (U-CORONA) 研究の成人645人を用いた。パンデミック前の社会的統合は、コーエンの社会的ネットワーク指数に基づき、社会的役割の数を数えることで評価した。パンデミック前とパンデミック中のフェイスマスク使用はアンケートで評価し、参加者は一貫したマスク使用者、新規使用者、現在の非使用者に分類された。多項ロジスティック回帰分析により、社会的統合スコアの低下とフェイスマスク使用との関連性を検討した。サンプリングバイアスの可能性を考慮し、母集団の分布に基づき参加者の重みを使用した。参加者645名のうち、172名(26.7%)が一貫したマスク使用者、460名(71.3%)が新規使用者であり、13名(2.0%)が現在非使用者であった。社会的統合度が低いほど、マスクを使用しない傾向があることが分かった(RRR:1.76、95%CI:1.10、2.82)。フェイスマスクの使用を促進するためには、社会的統合が重要である可能性がある。 -
Fukuya Y, Fujiwara T, Isumi A, Doi S, Ochi M. Association of birth order with mental health problems, self-esteem, resilience and happiness among children: results from A-CHILD study. Front Psychiatry. 2021 Apr 14;12:638088.
日本語アブストラクト
「出生順位と子どものメンタルヘルス、自尊心、レジリエンス、幸福感との関連:A-CHILD研究の結果」
【目的】
本研究は、小学4年生(9~10歳)の子どもたちのメンタルヘルス、自尊心、レジリエンス、幸福感と出生順位の関連を調査することを目的とした。
【方法】
2018年に東京都足立区の公立学校の小学4年生の児童を対象とした人口ベース研究である足立区子ども健康・生活実態調査(A-CHILD)研究のデータを用いた横断研究である(N = 3,744)。子どものメンタルヘルスを評価するために、親が評価するStrengths and Difficulties Questionnaire(SDQ)および自己評価によるレジリエンス、幸福、自尊心のスコアを使用した。連続的なアウトカムについては重回帰分析、二項アウトカムについてはロジスティック回帰を用いて、出生順位とメンタルヘルス、レジリエンス、幸福感、自尊心の関連を検討した。解析は、子どもの性別、母親の年齢、母親の教育、介護者の抑うつ症状、世帯収入、祖父母との同居を調整した。
【結果】
SDQの困難度スコアは、末子が最も低く、一人っ子が最も高かった(p < 0.001)。向社会的行動スコアは、末子で最も高かった(p < 0.001)。レジリエンススコアも末子で最も高く、次いで長子、中間子、一人っ子の順であった。幸福感のスコアは中間子で最も低かった。自尊心スコアは、兄弟姉妹のタイプによる差はなかった。これらの関連は、調整モデルやロジスティックモデルでも同様であった。
【結論】
出生順位が子どものメンタルヘルスに与える影響は、ポジティブまたはネガティブな側面の双方にわたり存在することがわかった。出生順位と行動問題の発生との関連、および子どものレジリエンス、幸福感、自尊心といったポジティブな側面との関連のメカニズムを明らかにするために、さらなる研究が必要である。 -
Koyama Y, Fujiwara T*, Isumi A, Doi S, Ochi M. The impact of public assistance on child mental health in Japan: results from A-CHILD study. J Public Health Policy. 2021 Mar;42(1):98-112.
日本語アブストラクト
「生活保護が子どものメンタルヘルスに及ぼす影響:足立区子どもの健康・生活実態調査より」
【背景】日本は子どもの貧困率が2015年現在で13.9%であり、他のOECD諸国と比較して高い。貧困対策として、現金給付は広く行われている政策であり、日本における生活保護はその一つである。しかし、スティグマや羞恥心などを含めたメンタルヘルスに対する影響については明らかになっていない。本研究では、生活保護が子どものメンタルヘルスに与える影響を明らかにすることを目的とした。
【方法】足立区子どもの健康・生活実態調査のデータより、2015年度および2017年度の小学1年生6920人を対象に解析を行った。親子を「生活保護受給群」「生活保護非受給・貧困群」「生活保護非受給・非貧困群」の3つのグループに分類し、子どものメンタルヘルスについて問題行動・向社会的行動・レジリエンス・登校しぶりについてアセスメントを行った。背景因子についてプロペンシティスコアマッチングを行い、子どものメンタルヘルスについて比較を行った。
【結果】相対的貧困下で生活する子どもは、問題行動が多く、レジリエンスが低く、より多くの子どもが登校しぶりを示す傾向があることが分かった。貧困世帯群間でマッチングを行い比較したところ、受給世帯と非受給世帯との間で生活様式については有意な差は見られなかったが、受給世帯では非受給世帯に比べて、登校しぶりを示す子どもの割合が高い傾向のあることが明らかとなった(OR=4.00, 95%CI 0.85-18.84)。
【考察】本研究では、生活保護が子どもの問題行動・レジリエンス・登校しぶりと関連していることを示す十分なエビデンスは得られなかった。
-
Takizawa M, Kawachi I, Fujiwara T*, Kizuki M, Nawa N, Kino S. Association Between Maternal Working Status and Unintentional Injuries Among 3 to 4-Month-Old Infants in Japan. Matern Child Health J. 2021 Mar;25(3):414-427.
日本語アブストラクト
「日本における3~4ヶ月児の母親の就労状況と不慮の事故との関連性」
【目的】
世界的にも、不慮の事故は乳幼児の死因の一つである。乳幼児期の傷害のリスク要因としては、ひとり親家庭、社会経済的不利、母親の産後うつ病などが確立されている。我々は、日本における母親の就労状況と乳幼児期の不慮の事故との関連性を検討することを目的とした。
【方法】
愛知県の3カ月または4カ月の健康診断に参加した母親を対象とした質問票のデータを使用した。さまざまな種類の不慮の傷害を一つでも経験したかを主要アウトカムとし、「転倒」「溺れかけ」の経験も副次的アウトカムとして検討した。共変量を調整した多変量ロジスティック回帰分析を実施した。また、有給雇用グループと無給雇用グループの共変量のバランスをとるため、傾向スコアマッチングを実施した。
【結果】
6,465件の有効回答(回答率67%)のうち、9.8%の乳児が不慮の事故を経験していた。母親の就労傾向に関するマッチング(26の共変量に基づく)を行った結果、有給の母親の乳幼児は、転倒の可能性が1.60倍(95%CI:1.14-2.24)高いなど、怪我を経験する確率が1.35倍(95%CI:1.04-1.74)高いことが判明した。溺れかけは、母親の就労と有意な関連はなかった。また、父親の就業状況は転倒のリスクと正の相関があることがわかった。
【結論】
多変量ロジスティック解析と傾向スコアマッチング解析の結果、母親の有給雇用の状況は、日本人の乳幼児における不慮の事故と関連することがわかった。乳幼児の怪我を予防するためには、働く家庭への包括的な支援を検討する必要がある。 -
Morita A*, Fujiwara T. Association between Positive Grandparental Involvement during Childhood and Generativity in Late Life Among Community-Dwelling Cognitively Intact Older Adults in Japan. Geriatr Gerontol Int. 2021 Mar.21(3);331-337.
日本語アブストラクト
「子どもの頃に祖父母から受けたポジティブな養育経験と高齢期における世代性(次世代の育みに関する関心や関与)の関連」
【背景】 世代性(次世代の育みに関する関心や関与)は地域社会の活力の基礎であり、またヘルシー・エイジングの鍵としても注目されています。中高年期における世代性と子どもの頃に親から受けた養育経験が関連することはわかっていますが、祖父母から受けた養育経験との関連は明らかになっていません。本研究では、認知機能が健康な日本の地域高齢者を対象に、子ども期に祖父母から受けたポジティブな養育経験と高齢期の世代性の関連を検証することを目的としました。
【方法】 2017年に実施された涌谷町中高年者の健康と生活実態調査のデータと健診データをプールし、認知機能が健康な地域在住高齢者(N = 173)を対象としました。重回帰分析を用いて、18歳以前における祖父母からの勉学や趣味の応援、悩み相談、経済的支援、しきたりや経験の継承の有無に基づくポジティブな養育経験の程度(低・中・高)が、Loyola Generativity Scale日本語訳の短縮版を用いて測定した世代性の程度と関連するかを検証しました。
【結果】年齢、性別、記憶力、抑うつ症状、子どもの頃の社会経済的状況および親の関わりを調整した結果、祖父母からのポジティブな養育経験が低い群よりも多い群の方が、世代性が高いことが示されました。世代性を発揮する機会に寄与すると考えられる教育歴や孫育ての機会を調整しても、同じ関係がみられました。
【結論】日本の認知機能が健康な地域在住の高齢者において、子どもの頃に祖父母から受けたポジティブな養育経験が、次世代の育みに関する高い関心や関与と関連していることが示唆されます。
-
Fukuya Y, Fujiwara T, Isumi A, Doi S, Ochi M. Association between parenting and school refusal among elementary school children in Japan: results from A-CHILD longitudinal study. Front Pediatr. 2021 Mar 26;9:640780.
日本語アブストラクト
「日本の小学生における子育てと登校しぶりの関連性:A-CHILD研究の結果」
【目的】
本研究の目的は、日本の小学生において、1年生(6~7歳)における親子の関わりや児童虐待を含む子育てと、2年生(7~8歳)および4年生(9~10歳)における登校しぶりの関連性を検討することである。
【方法】
データは、2015年、2016年、2018年に東京都足立区で実施された「足立区子ども健康生活実態調査(A-CHILD)」を用いた。2015年に小学1年生の全児童(N = 5,355)を対象に質問票を配布した。有効児童総数4,291名(回答率:80.1%)のうち、3,590名と3,070名がそれぞれ小学2年生と4年生までフォローアップした。養育者は、親子の関わりと、小学1年生ではネグレクト、身体的虐待、心理的虐待を含む子どものマルトリートメント、小学2年生と4年生では登校しぶりに関するアンケートに回答した。欠損データについては、多重代入法を行った。分析には、小学1年生における子どもの精神的健康と社会人口学的特性を調整した多変量ロジスティック回帰モデルを使用した。
【結果】
登校しぶりの割合は、小学2年生で1.8%(n=64)、小学4年生で2%(n=60)であった。共変量で調整した結果、小学1年生では親子の関わりと子どものマルトリートメント、小学2年生と4年生ではそれぞれ登校しぶりとの関連は見られなかった。
【結論】
親子の関わりや子どものマルトリートメントなどの子育てと小学生の登校しぶりは関連しない可能性がある。学校しぶりに影響する仲間関係や学校環境などの他の要因を解明するために、さらなる縦断的研究が必要である。 -
Matsuyama Y, Subramanian SV, Fujiwara T. Relative deprivation and educational aspiration of 15-year-old adolescents in Japan. Soc Psychol Educ. 2021 Mar 17;24:573-588.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-021-09619-w
日本語アブストラクト
「日本の15歳の青少年の相対的剥奪と大学進学希望との関連」
高等教育は、健康で成功した人生を送る可能性を高める。本研究では、日本の青少年における相対的剥奪と大学教育への希望との関連性を調査した。2001年に日本で生まれた乳児を追跡する全国規模の出生コホート研究である「21世紀出生児縦断調査」の2016年調査のデータを分析した(参加者は15歳、n=17,662)。12歳時の相対的困窮度、すなわち同じ市町村を参照群としたイツザキ係数は、別の全国調査から得た。イツザキ係数と大学進学希望との関連を調べるために、ランダム切片を用いた3レベル多値ロジスティック回帰(レベル1:個人、レベル2:自治体、レベル3:県)用いて、性別、親の学歴、世帯収入の絶対値、ソーシャルサポート知覚、居住都市の大きさを調整した。66%の青少年が大学教育への希望を抱いていた。イツザキ係数が高いことは、すべての共変数を調整した後、大学教育への願望を持つことと有意に正の相関があった(オッズ比:四分位範囲-変化尺度あたり1.18、95%信頼区間:1.09、1.28)。相対的剥奪の正の影響は、世帯収入が高い青年においてより大きかった。この結果は、相対的剥奪が青少年の教育意欲を動機付ける可能性があることを示唆しているが、それは高所得者においてより顕著であった。貧困の連鎖を断ち切るためには、貧困下にある青年の願望をより高い教育達成度に変換して支援する政策が必要である。 -
Machida M, Takamiya T, Amagasa S, Murayama H, Fujiwara T, Odagiri Y, Kikuchi H, Fukushima N, Kouno M, Saito Y, Yoshimine F, Inoue S*, Shobugawa Y. Objectively measured intensity-specific physical activity and hippocampal volume among community-dwelling older adults. J Epidemiol. 2021 Mar 13. doi: 10.2188/jea.JE20200534. [Epub ahead of print]
-
Isumi A*, Takahashi K, Fujiwara T. Prenatal sociodemographic factors predicting maltreatment of children up to 3 years old: A prospective cohort study using administrative data in Japan. Int J Environ Res Public Health. 2021, 18(5), 2505.
日本語アブストラクト
「3歳児までの虐待を予測する妊娠期の社会的属性要因:日本の業務データを用いた前向きコホート研究」
【背景】妊娠期からリスク要因を把握することは虐待を予防する上で重要である。しかし、妊娠届出時に把握している妊娠期のリスク要因を検証した研究は少ない。本研究では、妊娠届のポピュレーションデータを用いて、3歳児までの虐待を予測する妊娠期のリスク要因を特定することを目的とした。
【方法】愛知県で協力の得られた5市町において2013年10月から2014年2月の間に3–4カ月健診に対象となったすべての子どもの母親を対象とし、子どもが3歳になるまで追跡した。虐待があったことを示唆する要保護児童対策協議会(要対協)への登録データを妊娠届データと突合した(N=893)。精確ロジスティック回帰を用いて分析を行った。
【結果】3歳になるまで要対協に登録があった児童は11名(1.2%)であった。要対協への登録と有意な関連があった妊娠届時のリスク要因は、未婚、中絶経験、妊娠前および妊娠中の喫煙であった。また、これらのリスク要因を合計してリスクスコアを算出したところ(0〜7点)、このリスクスコアは高い予測精度を示し(ROC曲線下面積0.805、95%信頼区間0.660–0.950)、2点以上がカットオフ値と考えられた(感度72.7%、特異度83.2%)。
【結論】妊娠届で把握できるリスク要因によって3歳までの虐待を予測できる可能性が明らかになった。
-
Nawa N, Yamaguchi K*, Kawakami C, Nakagawa M, Fujiwara T, Akita K. Differential effects of interprofessional education by gender and discipline among medical and dental students in Japan. MedEdPublish. 2021 Feb 22. doi: 10.15694/mep.2021.000052.1
Differential effects of interprofessional education … | MedEdPublish
日本語アブストラクト
「日本の医学生・歯学生における多職種連携教育の性別・分野別の効果の違い」
【背景と目的】
多職種連携教育(IPE)ワークショップの効果が学生の特性によって異なるかどうかを調査した研究では、さまざまな結果が出ている。本研究の目的は、IPEワークショップの影響と、それが学生の分野や性別とどのように関連しているかを評価することである。
【方法】
本学のIPEワークショップに参加した医学部学生と歯学部学生(N=108)のデータを解析した。IPEワークショップの前後でアンケート調査を受講学生を対象に実施した。ワークショップ終了後、ワークショップの満足度を評価した。IPEワークショップに関する質問の得点の変化と学生の満足度との関係を、回帰分析によって評価した。また、自由形式の質問に対する学生の回答は、定性的に分析した。
【結果】
医学部学生と歯学部学生において、ワークショップの必要性のスコアの上昇が満足度と関連していた。医学部学生では、IPEにおける自身の役割について議論する傾向があった。歯学部学生では,職種間の視点の違いに気づくことが満足度と関連した(OR:6.3,95%CI:1.7,23.9)。医学部学生では、男女ともに、ワークショップの必要性、患者さんに関する理解、各職種の役割に関するスコアの増加が満足度と関連した。男子学生では、自分の役割や限界を理解することに関するスコアの増加が満足度と関連した。
【結論】
ワークショップの満足度に寄与する要因は、学生の分野や性別によって異なり、これは受講者の特性に応じて最適なワークショップを計画するための重要な情報を提供するものであると考えられた。 -
Sonoda S*, Kuramochi J, Matsuyama Y, Miyazaki Y, Fujiwara T. Validity of clinical symptoms score to discriminate COVID-19 patients among common cold out-patients in general practitioner in Japan. J Clin Med. 2021 Feb 19;10(4), 854.
日本語アブストラクト
「日本の開業医における発熱外来患者におけるCOVID-19患者の鑑別のための臨床症状スコアの妥当性」
【目的】
コロナウイルス感染症2019(COVID-19)は日本を含め世界的に流行している。しかし,COVID-19と非COVID-19を鑑別する臨床症状については,開業医外来ではほとんど知られておらず,効率的な症例検出のために重要である.本研究の目的は,2020年8月に日本でCOVID-19パンデミック第2波が発生した際に,開業医の外来患者においてCOVID-19患者と非COVID-19患者を識別する臨床症状を検討することであった。
【方法】
2020年8月1日から14日までに感染症が疑われ受診し,COVID-19 PCR検査を受けた患者360名の記録を用いた.患者は考えられる臨床症状および感染経路に関する質問票に回答した。多変量ロジスティック回帰を用いて、臨床症状とCOVID-19の有無との関連を検討した。
【結果】
COVID-19陽性患者は17例(4.7%)であった。多重ロジスティック回帰分析の結果、嗅覚障害(オッズ比(OR):25.94、 95%信頼区間(CI):7.15-94.14、p<0.001)、頭痛(OR、3.31, 95%CI、0.98-11.20、p=0. 054)、喀痰(OR、3.32, 95%CI、1.01-10.90;p = 0.048)、居酒屋やバーへの来店歴(OR、4.23, 95%CI、0.99-18.03;p = 0.051)は、COVID-19陽性と関連していた。このモデルは中等度の予測力を示した(AUC=0.870、 95%CI、0.761~0.971)。
【結論】
嗅覚障害、頭痛、喀痰分泌、居酒屋やバーへの来店歴がCOVID-19と関連することがわかった。本研究で得られた知見は、日本や国民皆保険制度のある他の国々の診療所や病院で検証される必要がある。 -
Shiwaku H, Doi S, Miyajima M, Matsumoto Y, Fujino J, Hirai N, Jitoku D, Takagi S, Tamura T, Maruo T, Shidei Y, Kobayashi N, Ichihashi M, Noguchi S, Oohashi K, Takeuchi T, Sugihara G, Okada T, Fujiwara T, Takahashi H. Novel brief screening scale, Tokyo Metropolitan Distress Scale for Pandemic (TMDP), for assessing mental and social stress of medical personnel in COVID-19 pandemic. Psychiatry Clin Neurosci. 2021 Jan;75(1):24-25.
-
Funakoshi Y, Xuan Z, Isumi A, Doi S, Ochi M, Fujiwara T*. The association of community and individual parental social capital with behavior problems among children in Japan: results from A-CHILD longitudinal study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2021 Jan;56(1):119-127.
日本語アブストラクト
「地域レベル、個人レベルでのソーシャル・キャピタルと子どもの問題行動との関連:A-CHILD縦断研究」
【背景】子どもの問題行動に関連する種々の要因が示唆されているが、個人、地域双方のレベルでのソーシャル・キャピタルと子どもの問題行動との関連を縦断的に検討した研究は少ない。
【目的】個人および地域のソーシャル・キャピタルと子どもの問題行動との関連を検討すること。
【方法】本研究は2015年、2016年に悉皆追跡調査を行った「足立区子どもの健康・生活実態調査(A-CHILD Study)」のデータを用いた(対象者5,494名)。東京都足立区内の全公立小学校69校を対象とし、小学校1年生の保護者を対象に質問紙調査を実施、小学校2年生時に追跡調査を行った。ソーシャル・キャピタルはそれぞれ信頼、凝集性、互酬性を測る3つの質問への回答をもとに評価した。子どもの問題行動は日本語版のStrengths and Difficulties Questionnaire(SDQ)を用いて連続値で評価した。向社会的行動と問題行動について、2015年と2016年のSDQ得点の差をアウトカムとし、個人をレベル1、小学校区をレベル2としたマルチレベル解析を行った。本研究では、両年でソーシャル・キャピタル、問題行動に有効な回答があった3,656名を解析対象とした。
【結果】共変量を考慮後、地域のソーシャル・キャピタルは向社会的行動の増加と正の相関がみられたが (偏回帰係数: 0.19; 95%信頼区間:
0.03 , 0.36)、問題行動の増加との関連は見られなかった。一方、個人のソーシャル・キャピタルは向社会的行動の増加と正の相関(偏回帰係数:0.27; 95%信頼区間: 0.12, 0.41)、問題行動の増加と負の相関がみられた(偏回帰係数: -0.54; 95%信頼区間:-0.89, -0.19)。
【結論】地域レベルのソーシャル・キャピタルは子どもの向社会的行動の増加と関連すること、個人レベルのソーシャル・キャピタルは子どもの向社会的行動の増加と問題行動の減少の双方と関連することが示唆された。個人と地域のソーシャル・キャピタルを高めることは子どもの健康を推進する方策の一つとなりうる。
-
Hibiya S, Matsuyama Y, Fujii T, Maeyashiki C, Saito E, Ito K, Shimizu H, Kawamoto A, Motobayashi M, Takenaka K, Nagahori M, Kurosaki M, Yauchi T, Ohtsuka K, Fujiwara T, Okamoto R, Watanabe M. 5-aminosalicylate-intolerant patients are at increased risk of colectomy for ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2021 Jan;53(1):103-113.
-
Mikami R, Mizutani K, Gohda T*, Gotoh H, Matsuyama Y, Aoyama N, Matsuura T, Kido D, Takeda K, Izumi Y, Fujiwara T, Iwata T. Association between circulating tumor necrosis factor receptors and oral bacterium in patients receiving hemodialysis: A cross-sectional study. Clinical and Experimental Nephrology. 2021 Jan;25(1):58-65.
-
Badrakhkhuu N, Matsuyama Y, Araki MY, Yasuda YU, Ogawa T, Tumurkhuu T, Ganburged G, Bazar A, Fujiwara T*, Moriyama K*. Association between malocculusion and academic performance among Mongolian adolescents. Front Dent Med. 2021 Jan 22. doi: 10.3389/fdmed.2020.623768.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdmed.2020.623768/full
-
Udagawa T*, Matsuyama Y, Okutsu M, Motoyoshi Y, Okada M, Tada N, Kikuchi E, Shimoda M, Kanamori T, Omori T, Takahashi M, Imai K, Endo A, Fujiwara T, Morio T. Association between Immunoglobulin M and steroid resistance in children with nephrotic syndrome: A retrospective multicenter study in Japan. Kidney360.
-
Ito K, Doi S, Isumi A, Fujiwara T*. Association between Childhood Maltreatment History and Premenstrual Syndrome. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 18;18(2):781. doi: 10.3390/ijerph18020781.
日本語アブストラクト
「子ども期の虐待歴と月経前症候群の関連性」
【背景と目的】
子ども期の虐待歴は、様々な精神・身体疾患との関係が知られているが、月経前症候群(PMS)との関連はほとんど知られていない。本研究では、日本の若い女性を対象に、子ども期の虐待歴とPMSの関連について調査した。
【方法】
日本のある都市で、婦人科クリニックと一般診療所1カ所を受診した10~60歳の女性3815人を参加者とした。小児期の虐待歴とPMSに関する質問票を実施した。
【結果】
小児期の虐待歴のある女性は、そうでない女性と比較して、PMSのリスクが有意に高いことが確認された(オッズ比:1.47、95%信頼区間:1.20-1.81)。特に、子ども期の身体的・精神的虐待を受けた女性は、PMSとの関連性が強く、他の形態の子ども期の虐待(感情的無視、親密なパートナーからの暴力の目撃、性的虐待)は、PMSと関連しなかった。
【結論】
この結果は、小児期の虐待がPMSの危険因子である可能性を示している。 -
Doi S, Isumi A, Fujiwara T*. Association Between Serum Lipid Levels, Resilience, and Self-Esteem in Japanese Adolescents: Results From A-CHILD Study. Front Psychol. 2021 Jan 12;11:587164. doi: 10.3389/fpsyg.2020.587164. eCollection 2020.
日本語アブストラクト
「思春期児童における血清脂質濃度とレジリエンスおよび自己肯定感との関連:足立区子どもの健康・生活実態調査より」
【背景】血清脂質濃度は、成人期のメンタルヘルスの問題と関係していることがわかっています。しかし、血清脂質濃度が、思春期に発達するレジリエンスや自己肯定感といったメンタルヘルスのポジティブな側面に関係するかは明らかになっていません。本研究では、日本の思春期児童を対象に、血清脂質濃度とレジリエンスおよび自己肯定感との関連を検証することを目的としました。
【方法】2016年と2018年に実施された足立区子どもの健康・生活実態調査(A-CHILD)のデータをプールし、足立区の中学2年生とその保護者(N=1,056)を対象としました。児童のレジリエンスは保護者による質問紙、自己肯定感は児童による質問紙で評価されました。児童の血清脂質濃度(総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール)、身長、体重は学校健診で測定されました。重回帰分析を用いて標準化した総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロールが、子どものレジリエンスおよび自己肯定感と関係するかを検証しました。
【結果】思春期児童のBMI、生まれ月、性別、親の有無、世帯年収、保護者のメンタルヘルス、児童の生活習慣(食生活、身体活動、睡眠など)を調整した結果、LDLコレステロールの高さがレジリエンスの低さに関係していました。また、総コレステロールとLDLコレステロールの高さが自己肯定感の低さと関係していました。一方で、HDLコレステロールはレジリエンスおよび自己肯定感には関係がありませんでした。
【考察】日本の思春期児童において、総コレステロールとLDLコレステロールが、レジリエンスおよび自己肯定感のバイオマーカーとなる可能性が示唆されました。
-
Ochi M, Isumi A, Kato T, Doi S, Fujiwara T*. Adachi Child Health Impact of Living Difficulty (A-CHILD) study: Research protocol and profiles of participants. J Epidemiol. 2021 Jan 5;31(1):77-89.
日本語アブストラクト
「足立区子ども健康・生活実態調査(A-CHILD)研究のプロトコールおよび参加者の概要」
【背景】
社会経済的要因と子どもの健康との関連を明らかにするとともに、子どもの貧困問題の政策評価のためのデータを蓄積するために、2015年から「Adachi Child Health Impact of Living Difficulty(A-CHILD)研究」を実施した。本論文では、A-CHILD研究の目的と研究デザイン、参加者のベースラインプロファイルについて、本コホート研究の今後の枠組みを解説する。
【方法】
東京都足立区の全公立小学校の小学1年生を対象とした第1次調査として2015年に開始した完全標本追跡調査と、2016年に一部の小中学校(小4、小6、中2)で開始した2年ごとの追跡調査の2種類の継続調査を実施した。アンケートは、対象となる全児童の保護者が回答し、小学4年生以上は児童本人も回答した。また、A-CHILDのデータは、全学年児童の学校健診で得られた情報と、2016年以降の中学2年の生徒の血液検査・血圧測定の結果をリンクさせた。
【結果】
第1次調査での有効回答は4,291件(80.1%)であった。世帯収入が少ない、物質的に困窮しているなどの「生活困難」世帯は1,047世帯(24.5%)であった。
【結論】
A-CHILD研究は、貧困が子どもの健康格差に与える影響の解明に貢献し、地域で介入し改善する方途を示すものである。




